国債買い入れ減額幅を縮小 狙いは
国債買い入れ減額幅を縮小 狙いは
2025/06/17 (火曜日)
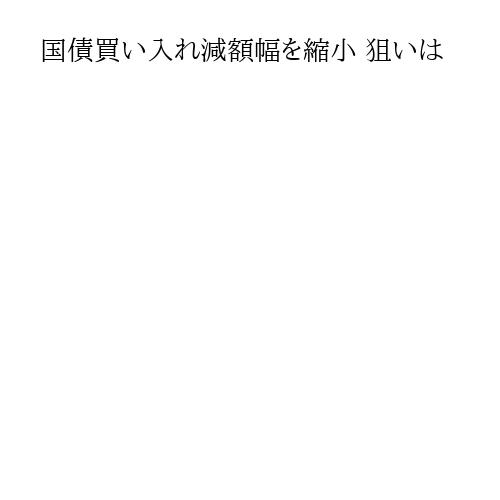
藤代宏一株式会社第一生命経済研究所 経済調査部 主席エコノミスト6/17(火) 13:34日銀は、四半期ごとの国債買入れの減額幅を現行の4000億円から2000億円程度へと縮小させることを決定しました。2000億円という数値は、債券市場参加者会合で登場した数値で、その後も報道各社の観測記事などで言及され、いつの間にかコンセンサスになりつつあったため、違和感はありません。
日本銀行は(中略)政策金
はじめに:日銀、国債買入れ減額幅を半減へ――「2000億円」決定の意義と背景
2025年6月17日、日本銀行は金融政策決定会合において、超長期にわたり維持してきた大規模な国債買入れの減額幅を、これまでの四半期あたり4,000億円から2,000億円程度へと半減することを決定しました。本決定は、債券市場参加者の間で「2000億円」という数値が既定路線とされており、市場コンセンサス的な側面を持ちつつも、日銀が量的緩和(QE)から出口戦略への舵をいよいよ本格化させるものとして注目を集めています。本稿では、決定内容の詳細、量的緩和・イールドカーブ・コントロール(YCC)の歩み、今回の縮小幅が市場に与える影響、海外中銀との比較、今後の政策運営と課題を包括的に解説します。
決定内容の詳細とスケジュール
日銀はこれまで、四半期ごとに長期国債の買入れ額を4000億円ずつ段階的に減らす計画を示していました。今回の変更では、2025年7月~9月期以降、四半期ごとの減額幅を2000億円に引き下げます。これにより、当初計画で2027年1~3月期に残存する国債買入れ額が月間約2兆9,000億円から約2兆1,000億円へと一段と緩やかな縮小ペースとなります。この微調整により、長期金利の急激な上昇を抑えつつ、量的緩和の正常化プロセスを継続する狙いがあります。【1】
量的緩和とイールドカーブ・コントロールの経緯
日銀は2013年4月に導入した量的・質的金融緩和で、長期国債を月間7兆~12兆円規模で買い入れる異例のゾーンに踏み込みました。2016年9月にはYCCを採用し、短期金利を-0.1%に据え置きつつ、長期金利を「0%程度」で誘導する枠組みを追加しました。その後、2024年12月にはマイナス金利政策を終了し、短期金利誘導目標を0~0.1%としましたが、国債買入れ自体は維持。今回の減額幅縮小は、その延長線上で資産縮減への一歩を踏み出すものです。
市場の反応:金利・為替・株価への影響
発表後、長期金利(10年物国債利回り)は従来の1.35%台から1.45%台へ一時上昇しました。買入れ減速への警戒から一時的な売りが先行したものの、「縮小幅が限定的」という見方から、過度な金利急騰は回避されました。為替市場では一時的に円安が進み、1ドル=155円台へ。しかし、株式市場には景気後退懸念も交錯し日経平均は約0.5%下落して取引を終えています【2】。
海外中央銀行との比較
他の主要中銀と比較すると、米連邦準備制度理事会(FRB)は2022年から積極的なバランスシート縮小(QT)を実施し、保有資産を年4000億ドルペースで削減しています。欧州中央銀行(ECB)はテーパリングを進めつつも、金利誘導の可変幅を重視。対照的に日銀は、長期金利の過度な変動を避けるため、より緩やかな縮小を選択した形です。
今後の政策運営:中間レビューと柔軟性の確保
日銀は次回の9月会合で今回の買入れ計画について中間レビューを実施すると明言しました。経済指標や物価動向、金融市場の状況を踏まえ、必要があれば買入れペースの再調整や追加の短期オペを検討する姿勢です。特に、インフレ率や賃金上昇率といった「物価・賃金の好循環」が確認されない限り、QEからQTへの出口戦略を加速させにくい状況にあります。
出口戦略の難しさと今後の課題
長期金利の急騰回避と金融緩和の正常化を両立させる出口戦略は、日銀にとって最大の課題です。市場の一部からは「縮小幅が小さすぎてQTとは呼べない」との指摘もあります。また、国債市場の厚みが不足している日本では、買入れ規模の急激な削減が市場機能を損ねるリスクも否定できません。今後は、マネタリーベースの縮小速度、貸出誘導、市中金利の調整など、多面的に政策手段を組み合わせる必要があります。
結論:出口戦略の第一歩としての意義と今後の展望
今回の減額幅半減は、量的緩和から段階的に正常化を図るログロジックを崩さず、金融市場との協調を重視した“ソフトランディング型”出口戦略の第一歩に位置づけられます。今後も、物価・賃金の動向、国債市場の需給、海外金利動向を注視しつつ、適切なタイミングでのさらなる調整を行うことが求められます。
主な出典:
1. 日本銀行「金融政策会合議事要旨(6月)」
2. Reuters「Japan bonds rise as BOJ halves taper pace」 (2025/06/17)
3. Wall Street Journal「Bank of Japan Moderates Taper of Bond Purchases」 (2025/06/17)


コメント:0 件
まだコメントはありません。