スキマバイトの「タイミー」で採用の作業員死亡 JR東の車両を屋外で清掃中に体調不良
スキマバイトの「タイミー」で採用の作業員死亡 JR東の車両を屋外で清掃中に体調不良
2025/07/04 (金曜日)
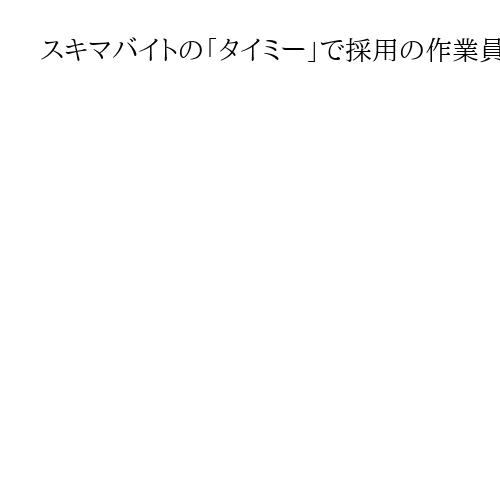
グループ会社のJR千葉鉄道サービスによると、作業はJR東から千葉鉄道サービスに委託され、さらに複数の会社へ委託されていた。作業員は6月21日午前10時過ぎから作業を始め、体調不良を訴え、空調の効いた車内で休む時間帯もあった。午前の作業後に休憩室で意識を失い、24日に死亡した。作業員がこの車両清掃に従事するのは初めてだったという。作業員の性別や年代は明らかにしていない。
JR車両清掃作業員が死亡 委託構造と熱中症リスクの背景を検証
2025年6月24日、グループ会社・JR千葉鉄道サービス(JRTS)の下請け作業員が千葉市内の車両清掃休憩室で意識を失い、その後死亡が判明した。6月21日午前から清掃作業に従事していたが体調不良を訴え、冷房車内で休憩をはさみながら作業を続けていたという。死亡した作業員は同種作業が初めてであった。
1.事故の概要
- 発生日:2025年6月24日
- 被災者:非公開(JRTS下請け会社所属の作業員)
- 作業内容:JR東日本からJRTSへ、さらに複数の下請け会社を経て委託された車両内清掃
- 経過:6月21日午前10時過ぎから清掃開始→体調不良で数回冷房車内で休憩→午前作業後の休憩室で意識消失→翌24日に死亡判明
- 特徴:清掃は初経験、外気温と車両内高温環境が想定される中、十分な熱中症対策なし
2.委託構造と作業環境の実態
大手企業が保線や車両清掃を外部委託する構造は、コスト削減と柔軟な人員確保を両立する一方、作業者の労働条件把握が困難になりやすい。JRTSはJR東から直請け後、さらに下請け業者に再委託しており、管理責任の所在が曖昧化しがちだ。
- 外注化の推移:2000年代以降、鉄道清掃業務は大手→中小→個人請負へと分散化
- 休憩場所:車両基地内のプレハブ休憩室や空調車両を利用するが、運用ルールが現場で周知不足
- 健康管理:作業前後の体調チェックや水分補給・塩分補給の指導が不十分
3.法制度と熱中症対策の歴史
労働安全衛生法(1972年施行)は、使用者に「健康障害を防止するため必要な措置」を義務づけるが、熱中症は近年顕在化した職場災害だ。厚労省は2015年に「暑さ指数(WBGT)閾値」に基づく屋外労働の休憩指針を策定。室内作業に関しても同様の指針が適用されるが、鉄道車両内は気候管理区域外とみなされるケースがあり、統一的な運用ガイドラインが求められている。
- 1994年:熱中症職場対策ガイドライン初版
- 2015年:WBGTに応じた休憩時間や水分塩分補給基準を明示
- 2020年:コロナ禍対策と兼ねたマスク着用下の熱中症リスク評価が追加
4.類似事例との比較
- 2018年・熊本県:送電線保守中の作業員が熱中症で死亡。WBGT管理と巡回チェック義務化後の事案。
- 2021年・大阪市:清掃業務外注先でビル清掃作業員が休憩不足で意識不明→重度障害。
- 2023年・名古屋市:地下鉄車両基地で床下清掃中の作業員が熱中症で搬送、休憩指示が守られず。
5.再発防止策と業界の取り組み
- WBGTモニタリング:作業エリアにセンサー設置し、閾値超過時に自動警報を発信
- 休憩・水分補給計画:作業前に詳細スケジュールを作成し、定期的なチェックを義務化
- 作業者教育:委託元・元請・下請の三者で合同研修を実施し、熱中症リスクと応急処置を周知
- 管理責任明確化:再委託先まで含めた安全管理責任を契約書に明記し、定期監査を実施
- 健康管理体制:作業日報に体温・体調チェック欄を追加し、異常時は直ちに医療機関へ送致
6.今後の課題と展望
- 法令整備の強化:鉄道車両内清掃など特殊環境作業を明文化した熱中症防止指針の追加
- 業界ガイドライン策定:JR全社と関連業界団体で標準的な安全管理マニュアルの策定
- ICT技術の活用:ウェアラブルセンサーで作業員の生体情報をリアルタイム把握し危険通知
- 労働安全文化の醸成:下請け・孫請けを含む全作業者が「自分の命は自分で守る」意識を共有
まとめ
今回の死亡事故は、外注化が進む中で管理責任が連鎖的に希薄化し、特殊環境下での熱中症リスク管理が徹底されなかったことが要因と考えられます。1972年の労働安全衛生法施行以来、熱中症対策指針は整備されてきましたが、鉄道車両内など「規制の穴」を突く作業環境が依然残っています。再発防止には、WBGT等の客観的指標を用いた警報体制の確立と、委託構造の末端まで責任を共有する契約・監査制度の導入が急務です。ICTによる生体情報モニタリングや、業界横断のガイドライン策定を通じて、全ての作業者が安全かつ健康に働ける環境を実現することが、日本の労働安全文化の成熟につながるでしょう。
(出典:産経新聞)


コメント:0 件
まだコメントはありません。