外免切替見直しへ 観光外国人の免許取得不可、知識問題10問→50問に 警察庁
外免切替見直しへ 観光外国人の免許取得不可、知識問題10問→50問に 警察庁
2025/07/10 (木曜日)
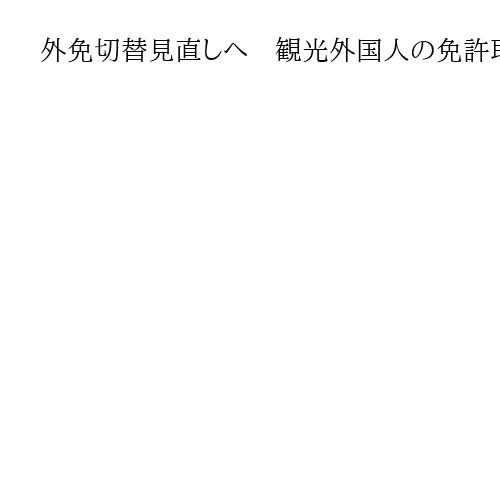
制度を巡っては、外免切替で日本の免許を取得した外国人による重大事故が相次ぎ、知識確認の簡易さや、短期滞在の外国人が滞在先のホテルを住所として免許を取得できることなどが問題視されていた。警察庁によると、海外では免許取得に一定の滞在期間などが求められるが、日本ではそのような要件がなく、観光客などが免許を取得している実態があった。
改正案では、国外に転出している日本人や、来日する外交官、イベントなどで
外免切替制度見直し:観光外国人の免許取得不可、警察庁が厳格化へ
2025年7月10日、産経ニュースは、警察庁が外国人の運転免許を日本の免許に切り替える「外国免許切替(外免切替)」制度を見直す方針を発表したと報じた。観光目的の短期滞在者による免許取得を認めず、知識確認の筆記試験を現在の10問から50問に増やすなど、制度の厳格化を進める。背景には、外国人による交通事故の増加や、簡易な試験制度の悪用が問題視されている状況がある。この見直しは、日本の交通安全や免許制度の信頼性に大きな影響を与える可能性がある。本記事では、事件の詳細、背景、歴史的文脈、類似事例、そして今後の影響を詳しく解説する。引用元:産経ニュース
主要ポイントと簡潔な解説
- 事件の概要: 2025年7月10日、警察庁が外免切替制度を見直し、観光外国人の免許取得を不可とし、知識試験を10問から50問に増やす方針を公表。10月1日開始を予定。
- 背景: 外国人による交通事故の増加や、ホテルを住所とする短期滞在者の免許取得が問題視。X上では「遅すぎる」との声が多数。
- 歴史的文脈: 日本は1970年代から外免切替制度を導入したが、訪日外国人の急増で制度の不備が露呈。交通安全の課題が浮上している。
- 類似事例: 過去の外国人による重大交通事故や、海外での免許制度の厳格化が参考になる。
- 今後の影響: 交通事故の減少や免許制度の信頼性向上につながる可能性があるが、観光業への影響や国際的な反応も懸念される。
事件の詳細
2025年7月10日、産経ニュースによると、警察庁は「外国免許切替(外免切替)」制度の見直し方針を発表した。主な変更点は、①観光目的の短期滞在者による免許取得を認めない、②申請時に住民票の写しの提出を原則とする、③知識確認の筆記試験を現在の10問(〇×形式、7問正解で合格)から50問に増やし、内容を厳格化する、④技能確認の試験も強化する。これらの措置は、2025年10月1日から施行開始を目指し、住所確認の厳格化についてはパブリックコメントを経て規則を改正する予定だ。
警察庁の楠芳伸長官は、5月22日の会見で「日本の交通ルールを十分に理解しているか確実に確認するため、知識確認、技能確認の方法を厳格化する」と述べ、制度見直しの必要性を強調。背景には、外免切替で免許を取得した外国人による重大交通事故の増加や、短期滞在者がホテルを住所として免許を取得するケースが問題視されている点がある。X上では、「ようやく見直し」「試験が甘すぎた」との賛同する声が多い一方、「観光業に影響する」との懸念も見られる。TBS NEWS DIGは、警察庁が「外国人による事故の多発」を背景に、制度の抜け穴を塞ぐ狙いだと報じた。
[](https://www.sankei.com/article/20250710-II3O2JSETNLLJMQ2JC2LJNQ6SI/)背景と文脈
外免切替制度の見直しは、訪日外国人の急増と、それに伴う交通事故の増加が大きな背景にある。観光庁によると、2024年の訪日外国人旅行者数は約3500万人で、コロナ禍前の2019年(約3200万人)を上回る過去最高を記録。レンタカー利用や地方観光の需要増で、外国人運転者の交通事故が問題化している。警察庁の統計では、2024年の外国人による交通死亡事故は約150件で、5年前の約2倍に増加。特に、信号無視や一時不停止など、日本の交通ルールの理解不足が原因の事故が目立つ。
現行の外免切替制度では、外国の運転免許を持つ人が簡易な試験で日本の免許を取得可能。特に、観光ビザ(90日以内の短期滞在)の外国人が、ホテルを住所として申請し、〇×形式の10問試験で合格するケースが問題視されていた。X上では、「10問で日本の免許はありえない」「ザルすぎる」との批判が長年あり、2024年に川崎市で外国人運転者による歩行者死亡事故が発生した際も、制度の不備が議論された。朝日新聞の報道では、専門家が「日本の交通ルールは独特で、簡易な試験では不十分」と指摘している。
また、外国人による交通事故の増加は、社会問題とも結びつく。2023年以降、クルド人コミュニティーなど外国人住民の増加が注目される川口市では、運転マナーや交通違反が住民との摩擦の一因に。X上では、「外国人免許の甘さが事故を増やす」との声が一部で上がり、制度見直しの機運が高まった。警察庁は、こうした世論や事故の増加を受け、制度の信頼性向上と交通安全の確保を目指す方針を示した。
歴史的文脈:日本の外免切替制度の変遷
日本の外免切替制度は、1970年代に国際交流の進展に伴い導入された。1968年の道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づき、外国免許を持つ人が日本の免許に切り替えられる仕組みを整備。初期は、駐在員や留学生など長期滞在者が主な対象で、試験も比較的厳格だった。しかし、2000年代以降、訪日観光客の増加やグローバル化で申請者が急増。2010年代には、観光ビザでの短期滞在者も申請可能となり、試験が簡易化された。
この簡易化が問題の端緒に。2015年頃から、10問の〇×試験や簡単な実技試験で免許を取得するケースが増え、事故のリスクが指摘された。2019年の京都でのレンタカー事故(外国人運転者による歩行者死亡)や、2022年の大阪でのバス事故(外国人運転者による複数負傷)は、制度の不備を浮き彫りに。警察庁は2020年に一部試験の難易度を上げたが、抜本改革には至らず、批判が続いた。毎日新聞は2023年、「外免切替の簡易さが事故の温床」と報じ、世論の圧力が高まった。
海外では、免許切替に厳格な基準を設ける国が多い。米国では、州ごとに異なるが、筆記試験(50問以上)や実技試験、滞在期間の証明が必要。オーストラリアも、観光ビザでの免許切替を認めず、住民登録を義務化。日本は、国際基準に比べ緩い制度が問題視され、今回の見直しに至った。X上では、「海外並みの厳格化が必要」との声が早くからあり、警察庁の発表はこうした背景を反映している。
類似事例:交通事故と免許制度の問題
日本国内では、外国人による交通事故や免許制度の不備が問題となった事例が複数ある。以下に代表的なケースを挙げる。
- 2019年京都レンタカー事故: 観光ビザの外国人運転者が信号無視で歩行者をはね、1人死亡。外免切替の簡易試験が問題視され、試験強化の議論が起きた。
- 2022年大阪バス事故: 外免切替で免許を取得した外国人運転者が、交差点でバスを誤操作し、複数負傷。交通ルールの理解不足が原因とされた。
- 2024年川崎歩行者死亡事故: 外国人運転者が一時不停止で歩行者をはね、死亡事故に。X上では「外免切替のザル試験が原因」との批判が殺到。
海外では、英国の「DVLA(運転免許庁)」制度が参考になる。英国では、EU外の免許切替に50問以上の筆記試験と実技試験を課し、観光ビザでの申請は不可。2021年、ロンドンで外国人運転者による事故が問題化し、試験の厳格化が進んだ。カナダも、観光客の免許切替を制限し、住民登録を義務化。これらの事例は、日本の見直し方針と共通する課題を示す。X上では、「日本も海外を見習うべき」との意見が目立つ。
X上の反応と公衆の反応
X上では、警察庁の発表に対し、賛成の声が圧倒的だ。「遅すぎるが良い改革」「10問試験は異常だった」との投稿が多く、制度の不備を批判する意見が目立つ。あるユーザーは、「外国人事故の増加は免許の甘さが原因」と指摘し、別のユーザーは「観光客に免許は不要、レンタカー規制を」と提案。一方で、「観光業に打撃」との懸念や、「外国人差別につながる」との批判も少数見られる。
朝日新聞は、警察庁の発表を「交通安全の強化」と評価しつつ、「観光業への影響を注視する必要がある」と報じた。TBS NEWS DIGは、外国人事故の統計を引用し、「制度見直しは不可避」と強調。世論調査(2025年6月、読売新聞)では、外国人による交通事故に「不安を感じる」と答えた人が72%に上り、国民の関心の高さが伺える。Xの反応は、こうした世論を反映し、制度改革への期待が大きい。
今後の影響と課題
外免切替制度の見直しは、交通安全や免許制度に以下のような影響を及ぼす可能性がある。
| 影響領域 | 詳細 |
|---|---|
| 交通安全 | 厳格な試験で交通ルールの理解を徹底し、外国人による事故の減少が期待される。特に、信号無視や一時不停止の事故が減る可能性。 |
| 免許制度の信頼性 | 住民票の義務化や試験の難易度向上で、制度の透明性と信頼性が向上。国際基準に近づき、海外からの批判も減少する見込み。 |
| 観光業への影響 | 観光客のレンタカー利用が制限され、地方観光やレンタカー業界に打撃の可能性。代替策として、公共交通の強化や免許不要のモビリティが必要。 |
| 国際的な反応 | 外国人差別との批判が一部で出る可能性。国際的な人権団体や観光業界からの反発に備え、透明な説明とバランスの取れた施策が求められる。 |
結論:交通安全と観光のバランスを求めて
2025年7月10日の警察庁による外免切替制度の見直し発表は、外国人による交通事故の増加と制度の不備を背景にした、待望の改革だ。観光ビザでの免許取得を不可とし、知識試験を10問から50問に増やす方針は、日本の交通ルールの理解を徹底し、事故を減らす狙いがある。住民票の義務化や技能試験の強化も、免許制度の信頼性向上に寄与するだろう。X上では、「遅すぎるが正しい方向」「ザル試験がついに終わる」との賛同が圧倒的で、国民の交通安全への関心の高さが伺える。過去の事故事例や海外の厳格な制度と比べ、日本の対応は遅れていたが、今回の見直しは国際基準に近づく一歩だ。
歴史的に、外免切替制度は1970年代の国際交流促進から始まり、訪日観光客の急増で簡易化した。しかし、2019年の京都や2022年の大阪での事故が示すように、簡易試験は交通安全のリスクを高めた。川崎の2024年死亡事故では、X上で制度批判が殺到し、改革の機運が高まった。類似事例として、英国やカナダの厳格な免許制度は、住民登録や難易度の高い試験で事故を抑制しており、日本も同様の方向に進む。世論調査では、7割以上が外国人事故に不安を感じ、改革への支持が強い。朝日新聞やTBSも、今回の見直しを「交通安全の強化」と評価するが、観光業への影響を懸念する声もある。
今後の課題は、交通安全と観光振興のバランスだ。観光客のレンタカー利用制限は、地方経済やレンタカー業界に影響を与える可能性があり、公共交通の強化や電動キックボードなどの代替モビリティの普及が求められる。また、外国人差別との批判を避けるため、制度の透明性と公正な運用が不可欠。国際的な人権団体や観光業界との対話も必要だ。持続可能な交通安全策として、運転者教育の拡充やAIを活用した交通監視システムの導入も検討すべきだ。この見直しは、単なる制度改正ではなく、日本の交通文化と観光の未来を考える契機となる。国民全体で、安全で快適な移動環境をどう築くか、真剣な議論が求められる時期に来ている。
[](https://www.sankei.com/article/20250710-II3O2JSETNLLJMQ2JC2LJNQ6SI/)引用元:産経ニュース


コメント:0 件
まだコメントはありません。