好みの女性の車に「見守り機器」 GPSストーカーの恐怖、帰宅や出勤が犯人にばれている
好みの女性の車に「見守り機器」 GPSストーカーの恐怖、帰宅や出勤が犯人にばれている
2025/06/16 (月曜日)
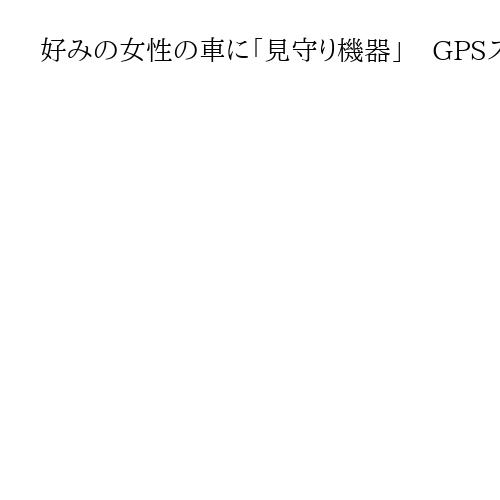
警察へのストーカーの相談件数が高止まりする中、GPS(衛星利用測位システム)機器などで位置情報を無断取得するケースが増加している。令和3年にストーカー規制法の対象となった行為だが、GPS機器の小型化や位置情報共有アプリケーションの普及といった技術革新の悪用が目立つ。子供を犯罪から守るための機器を使った事件も起き、警察当局は警戒を強めている。
ストーカー行為に関する警察相談件数
2025年現在、ストーカー行為に関する警察相談件数は高止まりの状態が続いており、中でもGPS機器やスマートフォンアプリを悪用した無断位置情報取得による被害が深刻化しています。令和3年(2021年)に改正されたストーカー規制法では、他人の居場所を特定する行為も規制対象に加えられましたが、技術の進化に伴い、より小型で高機能なGPS発信機や、無料・手軽に利用できる位置情報共有アプリケーションが登場。これらを駆使した新たなストーカー手法が後を絶たず、子どもや高齢者を狙った事案も発生しています。本稿では、GPS悪用型ストーカーの現状と法的枠組み、具体的事例、警察当局の対応、企業・自治体の取り組み、今後の対策について包括的に解説します。
1.ストーカー規制法とGPS位置情報取得行為の位置づけ
ストーカー規制法は2000年に施行され、つきまといなど従来型のストーカー行為を取り締まってきました。令和3年の改正では、「GPS等の機器を用いて相手の位置情報を取得する行為」も新たに「つきまとい等」に含められ、違反すると6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることとなりました。しかし、具体的な捜査・立証には、犯行機器の特定や通信傍受など、高度な捜査技術と専門知識を要するため、摘発件数は十分に伸びていないのが実情です。
2.GPS機器・アプリの進化と悪用手口
かつては車両に取り付けるサイズのGPSしか存在しませんでしたが、現在市販される「超小型GPS発信機」は乾電池で数か月稼働し、わずか数グラムの重さでバックルや鍵、靴底に貼り付け可能です。位置情報はBluetoothや4G回線を通じて加害者のスマートフォンにリアルタイム送信され、地図アプリ上に被害者の移動軌跡が表示されます。
また、SNS連携が可能なアプリでは「家族間・友人間で位置を共有する」機能が悪用され、被害者が承諾を示す前に招待リンクを送りつける手口も横行。知らぬ間に共有設定がオンになり、行動パターンをすべて監視されるケースも多発しています。
3.具体的事例紹介
事例1:20代女性が交際相手から小型GPSを下着入れに仕込まれ、出勤先や通院先、自宅から行動範囲まで常時監視された。女性は不審に思い調査を依頼、GPS発信機を発見。被害届を提出し、パートナーは逮捕された。
事例2:小学3年生の男児が、見守り用として親が購入した子ども用スマートウォッチに加害者が遠隔操作で位置共有を許可。男児の帰宅・外遊び時間をすべて把握され、身元調査や「声掛け」が複数回行われた。
事例3:離婚調停中の夫婦間で、元配偶者が元妻の車に無線式GPSを取り付け、子どもと面会する日時・場所をすべて特定。複数の児童相談所や家庭裁判所で調査を受け、最終的に元配偶者は起訴された。
4.被害者の心理的・社会的影響
位置情報を無断で追跡される被害者は、常に「誰かに監視されている」という強い恐怖感にさいなまれます。外出や通勤が困難となり、仕事を辞めざるを得なかったケースや、不登校に陥った子どもも報告されています。加害者が位置情報を逐一送信するSNSチャットにしつこくコメントを残すことで、被害者の精神的負担は深刻化し、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症する例もあります。
5.警察当局の対応と課題
警察はストーカー相談の一環として、GPS悪用事案を専門に扱う「サイバー犯罪対策官」を各県警に配置し、発信機の検出装置やデジタルフォレンジック技術を導入しています。しかし、被害者が相談に訪れるタイミングが遅い場合や、機器が極小で発見困難な場合が多く、加害者特定までに時間を要することが課題です。また、位置情報アプリの招待履歴やログを捜査令状で入手する手続きも煩雑で、迅速な証拠保全が難しい点が指摘されています。
6.企業・自治体の取り組み
位置情報共有アプリの開発企業は、「家族モード」と「合意済み共有」に明確に区分し、初期設定時に厳格な同意手続き(PINコード認証や生体認証)を導入。無断共有を検知した際には、被害者に通知が行く仕組みを整備しています。また、地方自治体ではストーカー被害を防ぐため、防犯GPS貸与事業や、子ども用GPSリストバンドの配布を実施。専門相談窓口を設置し、警察や民間団体と連携したワンストップ支援体制を構築しています。
7.今後の展望と対策強化
技術進化に伴い、加害手段も高度化する一方で、防御策も追いつかなければなりません。今後は、以下の取り組みが重要です。
- ストーカー規制法の追加改正による罰則強化と、位置情報悪用行為の明文化
- 警察捜査技術の高度化(人工知能によるログ解析、遠隔機器特定技術など)
- 位置情報アプリ開発ガイドラインの策定と業界団体による自主規制強化
- 地域コミュニティを巻き込んだ防犯教育プログラムの全国展開
- 被害者支援体制の一層の充実(心理ケア・法的支援・シェルター確保)
まとめ
GPS機器や位置情報アプリを悪用したストーカー被害は、被害者の安全を根底から脅かす深刻な問題です。技術革新は利便性を高める一方で、それを悪用する者から守る仕組みづくりと法整備が追いついていません。警察、行政、企業、地域住民、そして利用者一人ひとりが協力し、安全安心な位置情報活用のルールと意識を共有することが、犯罪被害を未然に防ぐ最良の策と言えるでしょう。


コメント:0 件
まだコメントはありません。