工藤会トップ 複数土地を家族信託
工藤会トップ 複数土地を家族信託
2025/06/16 (月曜日)
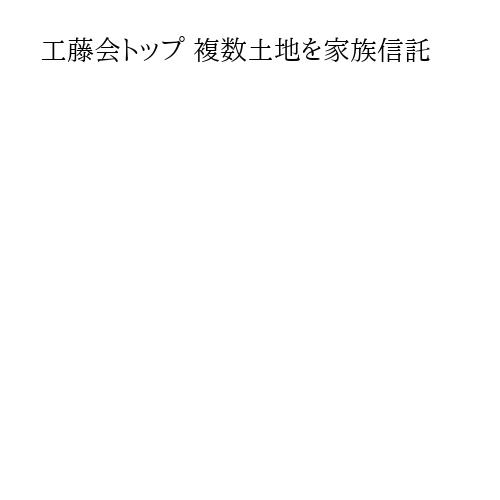
工藤会トップ、複数の土地を家族信託 福岡県警「賠償逃れ」指摘
工藤会トップ、複数の土地を家族信託 福岡県警「賠償逃れ」指摘|はじめに
2025年6月16日、福岡県警捜査2課は、九州最大級の指定暴力団・工藤会(くどうかい)の実質的トップであるA容疑者(66)が、複数の所有地を自らの名義から家族信託に移転し、資産を信託受益権という形式で管理させていたと発表しました。県警は「賠償金支払いなど法的責任を回避するための悪質な資産隠し行為」と指摘。今回は、工藤会トップによる家族信託の手口と法的問題、警察・司法の対応、信託制度の濫用防止策などを詳しく解説します。
1.工藤会トップA容疑者の経歴と背景
工藤会は1960年代に発足し、九州地方を中心に覚せい剤密輸や組織的暴力事件で知られる指定暴力団です。2016年に逮捕された前トップの引退後、A容疑者が実質的な最高指導者として組織運営を取り仕切ってきました。県警によれば、A容疑者は不動産投資にも精通し、長年にわたり福岡市内外の農地や宅地を取得。被害者への賠償金や税金が膨らむ中で、資産防衛のための策を講じたとみられます。
2.家族信託とは何か
家族信託は、自分の財産を信頼できる家族に託し、受託者(例えば子や妻)が運用・管理する制度です。従来の贈与や遺言と異なり、生前から柔軟な資産移転が可能で、成年後見制度による制約も回避できます。高齢化に伴う資産管理ニーズや事業承継対策として活用が進む一方で、第三者への無断流用や脱税・隠匿の温床になりかねないリスクも指摘されています。
3.A容疑者の信託スキームの手口
県警の調べでは、A容疑者は2019~2023年にかけ、福岡県糸島市や遠賀郡など計5か所の農地・宅地を順次家族信託に移行。受託者には三男(38)と長女(42)を据え、受益権を同族間で保有させる形を採用しました。信託契約書には「農業振興を目的とする」と記載されたものの、実際には耕作されず、所有地は駐車場経営や資材置き場として転用されていたというのが県警の見立てです。
4.県警の「賠償逃れ」指摘と法的問題
A容疑者は2017年、組員による覚せい剤密売事件で約2億円の賠償命令を福岡地裁で受けています。しかし、信託移転後は自己財産が信託外となり、強制執行による差押え対象から外れるため、賠償回収がほぼ不可能となりました。県警は「信託を悪用した脱法的資産隠し」と断じ、組織犯罪処罰法や暴排条例に基づく捜査を継続中です。
5.弁護士・研究者の見解
弁護士の松村浩一氏は「家族信託自体は適法だが、脱税や強制執行回避を目的とした設計は違法行為のほう助にあたる可能性がある。契約の公序良俗違反を問える余地がある」と指摘。一方、信託法研究者の田中恵教授は「脱法リスクを放置すれば信託制度全体への信用失墜につながる。仕組みの透明化や信託登記の厳格化が必要だ」と述べています。
6.警察・司法の対応と今後の捜査動向
県警は信託契約書や受託者への資金移動記録を押収・分析し、背任や詐欺的手段の立証を目指します。弁護士や司法書士も含む捜査チームを編成し、信託の実体を突き崩す方針です。また、福岡地裁では信託登記を無効とする仮処分申請が検討され、強制執行への足がかりとする構えです。
7.信託制度の濫用防止策
金融庁・法務省は2025年中に「家族信託ガイドライン」を改訂し、非営利目的の明示や受託者の適格性審査を強化予定。また、信託登記制度のオンライン化と不動産登記情報との連携を深め、信託後の土地利用実態を定期的にモニタリングできる仕組みを導入する方針です。弁護士や司法書士には、信託契約のリスク説明義務が課されます。
8.全国の暴力団対策への示唆
工藤会トップの家族信託事案は、指定暴力団の資産隠匿対策として自治体・警察が連携強化を図る契機となります。全国の警察本部は信託登記情報の定期照会や、暴排法に基づく資産凍結手続きの迅速化を進めています。暴力団排除条例の改正議論も再燃し、「信託による組織犯罪資金循環の防止」を明文化する動きが地方議会で活発化しています。
まとめ
工藤会トップによる複数土地の家族信託は、合法制度の盲点を突いた脱法的資産隠しの典型例です。信託制度の本来の目的である高齢者の財産管理や相続対策を守るためにも、濫用防止策の充実と、警察・司法による厳正な監視が不可欠です。今後の捜査と法整備の動向に注目が集まっています。


コメント:0 件
まだコメントはありません。