無断複製した合鍵で同僚女性宅に侵入、洋服など盗む 室内も撮影か 容疑で27歳男を逮捕
無断複製した合鍵で同僚女性宅に侵入、洋服など盗む 室内も撮影か 容疑で27歳男を逮捕
2025/06/17 (火曜日)
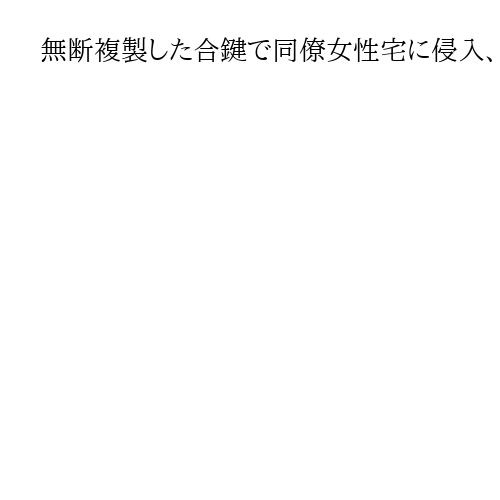
逮捕容疑は、3月30日午前0時ごろ、20代の同僚女性が暮らす東京都大田区のマンションに侵入し、洋服や防犯カメラなど6点(時価約1万5000円相当)を窃取したとしている。
同署によると、容疑者は女性のバッグに入っていた鍵のメーカーや番号などを盗み見て記録し、合鍵を作成。昨年8月以降、20回以上にわたって女性の部屋に侵入していたとみられ、容疑者のスマートフォンには、室内の様子を撮影した写真も残されて
はじめに:同僚女性宅へ20回超の侵入 合鍵窃盗事件が示す身近な「鍵の危機」
2025年3月30日未明、東京都大田区のマンションで、20代の同僚女性宅に無断で作成した合鍵を使い侵入、洋服や防犯カメラなど6点(時価約1万5千円相当)を盗んだとして、27歳の会社員男性が住居侵入・窃盗容疑で逮捕されました。警視庁蒲田署の調べでは、昨年8月以降、実に20回以上にわたって同女性宅に侵入し、室内の様子を撮影した写真約300枚をスマートフォンに保存していたといいます。被疑者は「LINEを無視された恨みで嫌がらせしたかった」と動機を供述していますが、身近な「鍵の危機」があらためて浮き彫りになりました。
1.事件の経緯:鍵から合鍵、20回超の侵入
被疑者は昨年8月、勤務先のオフィスで同僚女性のバッグから鍵を盗み見し、メーカー名や鍵番号をメモ。ネット上の業者に依頼して合鍵を作製し、不在の深夜帯を狙って部屋へ侵入しました。昨年9月~今年3月にかけ、洋服やバッグ、防犯カメラなどを繰り返し盗み、室内写真を撮影。被害女性は3月下旬、「衣類や小物が減っている」と不審に気づき、防犯カメラを設置するもそれも盗まれたため蒲田署に相談し、捜査が始まりました。
2.合鍵窃盗の現状と防犯意識の課題
合鍵を使った住居侵入は、2010年代以降に急増傾向にあります。警視庁によると、2024年の住居侵入・窃盗事件のうち「合鍵型犯行」とみられる件数は前年比約12%増。単純な空き巣よりも「顔見知りによる侵入」が多く、被害者の警戒心や防犯意識が緩い「身内リスク」が大きな問題となっています。
3.法的背景:住居侵入罪と合鍵作製の違法性
刑法では、住居侵入罪(第130条)と窃盗罪(同第235条)が適用され、いずれも3年以下の懲役または10万円以下の罰金刑が科されます。合鍵の作製自体は正当な手続きを経ない限り違法行為とされ、鍵番号や印影を無断で複製すれば、建造物侵入を助長したとして「器物損壊罪」や「不正アクセス禁止法」適用にも議論が広がっています。今回のケースでも、メモした鍵情報の入手経緯が争点となり得ます。
4.過去の類似事例との比較
2018年には同僚女性宅から合鍵を作製し数十回侵入して現金を盗んだ事件が発生し、東京地裁は実刑判決(懲役3年)を言い渡しました。また、2022年には遠隔解錠デバイスを用いた「スマートロックハッキング」事案が社会問題化し、合鍵犯行の手口多様化が指摘されています。こうした事例はいずれも「身近な相手」が犯人である点を共通し、防犯対策の見直しを迫りました。
5.防犯対策:合鍵流出を防ぐ6つのポイント
- 〈鍵管理の徹底〉バッグやコート内ポケットなどに鍵を無造作に入れず、必ず施錠ポーチに保管。
- 〈鍵番号の非表示〉玄関ドア外側に刻印された番号を隠すシールを貼り、複製を難しくする。
- 〈合鍵依頼の証明〉合鍵作成時は証明書を発行する鍵業者を選び、依頼履歴を自分で保管。
- 〈スマートロック導入〉暗証番号変更履歴や遠隔解錠履歴が確認できる製品なら、不正開錠を早期検知できる。
- 〈防犯カメラの多角化〉外周だけでなく、共用廊下や玄関前に広角カメラを設置し、映像を遠隔監視。
- 〈周囲への警戒〉長期不在時は近隣住民に通知し、防犯パトロールや郵便物の回収を依頼。
6.企業と社会の役割:社員教育と地域防犯
今回の被疑者は勤務先で同僚女性の鍵情報を入手しており、職場における個人情報の管理が不十分だったといえます。企業は社員教育の一環として、オフィス内での私物管理ルールや相談窓口を整備し、不審行動を早期に察知する仕組みを構築する必要があります。また、地域コミュニティや警察が連携して「見守りパトロール」を強化し、不審者情報を共有することが再発防止に有効です。
結論:鍵の安全は日常の意識改革から
合鍵をめぐる今回の20回超の住居侵入は、鍵管理の“ほんの隙”が重大事件を招くことを示しました。物理的防犯だけでなく、個人の意識改革と企業・地域社会の連携が不可欠です。自宅の安全を守る小さな取り組みを積み重ね、安心して暮らせる環境づくりを進めていきましょう。


コメント:0 件
まだコメントはありません。