きょう施行の改正風営法 初の摘発
きょう施行の改正風営法 初の摘発
2025/06/28 (土曜日)
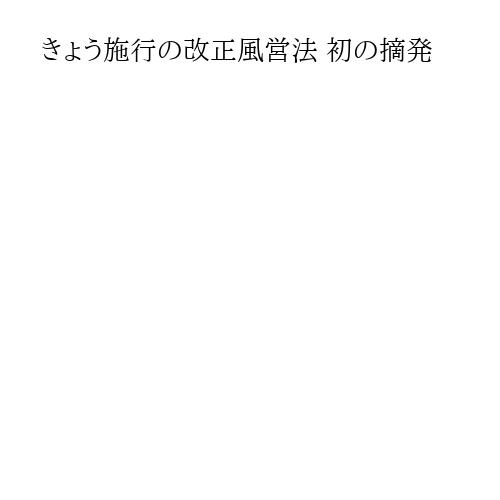
【速報】改正風営法 きょうから施行 新宿・歌舞伎町のガールズバーを摘発 無許可で接待営業か 警視庁 全国初
改正風営法施行で新宿歌舞伎町ガールズバー摘発──全国初の無許可接待営業取り締まり
2025年6月28日から施行された改正風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(改正風営法)に基づき、警視庁は同日未明、東京都新宿区歌舞伎町のガールズバー数店舗を摘発し、無許可で接待営業を行っていたとして関係者を逮捕・送検した。これが改正法施行後、全国初の摘発事例となる(出典:Yahoo!ニュース)。
改正風営法の背景と目的
風営法は1948年に制定され、風俗営業や深夜酒類提供飲食店(いわゆる「深夜営業」)の許可制度と規制を定めてきた。また、2003年の法改正ではキャバクラやパブ、スナックなどが対象となった。近年、インターネットやSNSの普及で従来型業態以外にも夜間接待を伴う業態が増加し、警察や行政の規制が追いつかない状況にあった。そこで2023年に閣議決定された改正風営法では、「接客を伴う飲食店営業」を明確化し、無許可営業の一層の厳罰化と適正運営を図ることが目的とされた。
改正法の主なポイント
- 「接待営業」の定義を拡大し、飲食を伴う女性・男性による接客を明示的に規制対象に
- 無許可営業への罰則を強化(罰金上限を従来の300万円から500万円へ引き上げ)
- 許可要件として営業所の構造基準や防犯設備の設置を厳格化
- 深夜(午後0時~午前5時)に酒類を提供する飲食店にも適用範囲を拡大
- 警察への営業計画届出制度を新設し、行政との情報共有を促進
施行直後の全国初摘発事例
摘発されたのは歌舞伎町の複数ガールズバーで、客席での立ち歩きやお酌など、法が禁止する「カウンタ越しの接客」を無許可で継続していた。警視庁は取締りに先立ち、3か月間の事前指導期間を設け、許可取得を促していたにも関わらず、申請を行わず営業を継続していたことから厳正に対処。店長ら数名を逮捕し、営業停止命令を行政処分として併せて通知した。
各地での対応状況
改正法施行に伴い、全国の公安委員会は許可申請の受付と並行して既存店舗への一斉検査を実施。大阪、福岡、札幌など主要都市では未許可の深夜営業飲食店300店超に文書指導を行い、約半数が許可申請段階に移行している。都道府県警察本部は「摘発だけでなく、適正営業化への導入を目的とした指導と情報提供を強化する」としており、違反店舗の全数把握を急ぐ構えだ。
歴史的経緯と比較
戦後まもない時期に制定された初期の風営法は、売春防止や治安維持を最優先に設けられた。高度経済成長期には接待飲食業が歓楽街の中心を担い、当局は許可制度より摘発を通じた抑止力を重視。一方、2000年代以降は健全化と産業育成の狭間で規制緩和と引締めを繰り返し、接待飲食業は「グレーゾーン」で存続してきた。本改正はこうした積み残し規制を一気に解消する意図を持つ。
業界・経営者の反応
接待飲食業組合は「地域経済への影響を懸念しつつも、健全な業態維持には一定の理解を示す」とする一方、中小店舗経営者からは「許可取得に数百万円の改装費や行政手続きが必要となり、資金力のない業者は廃業を余儀なくされる」との声が上がる。また、一部専門家は「健全化は進むが、規制強化が過度だと地下化を招く恐れがある」と警鐘を鳴らす。
海外の類似規制との比較
欧米主要都市では、ナイトライフ規制が都市計画や騒音規制の枠組みで整備されており、ロンドンやニューヨークではライセンス制を厳格に運用。特にカウンタ越しの接客に関しては、アルコール販売業許可に加え、ナイトクラブ許可やダンス許可が別途必要とされる例もある。本改正風営法は、こうした多層的許可制度を日本でも導入する初の試みと言える。
今後の課題と展望
改正法の真の目的は、摘発ではなく夜間経済と地域社会の調和を図ることである。そのためには、行政と業界の協議体制構築や、許可取得コスト低減のための支援策が不可欠だ。また、取り締まり後の監視・評価体制や、許可後のコンプライアンス教育も重要となる。今後は風営法を「規制の網」ではなく「安心・安全の保障」として定着させる取り組みが鍵となるだろう。
まとめ
改正風営法の施行により、新宿歌舞伎町のガールズバー摘発は「全国初」の強制力行使事例として注目を集めた。戦後から続く接待飲食業の規制ギャップにメスを入れ、健全なナイトライフの創出を目指す今回の改正は、日本の歓楽街や夜間経済に大きな転換点をもたらす。許可取得のための手続きや設備要件、監督体制の強化など課題は多いが、透明性ある制度運用と業界との連携が進めば、地域の安全・安心と経済活動の両立が実現可能だ。今後は全国各地の公安委員会や地方自治体、業界団体が協力し、規制と支援を両輪に夜間経済の質的向上を図ることが求められている。


コメント:0 件
まだコメントはありません。