シニアカーの男性 はねられ重体
シニアカーの男性 はねられ重体
2025/06/13 (金曜日)
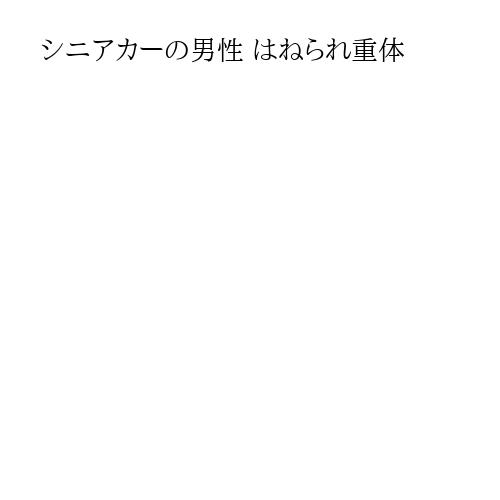
90代くらいの高齢男性が重体「(シニアカーが)見えていたが、止まるだろうと思っていた」事故起こした中学教諭を現行犯逮捕 兵庫・明石市
事故の概要
2025年6月13日午前10時ごろ、兵庫県明石市魚住町長坂寺の県道交差点で、シニアカー(ハンドル型電動車いす)を運転していた90代くらいの男性が軽自動車にはねられ、頭部出血や肋骨骨折などの重傷を負い、一時意識不明の重体となりました。警察は自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)の疑いで、軽自動車を運転していた同市の中学校教諭・32歳の男を現行犯逮捕し、「(シニアカーが)見えていたが、止まるだろうと思っていた」と供述しています 。
シニアカー(電動車いす)の特徴と法規制
シニアカーは歩行困難な高齢者や障害者の移動を支援する車いす型電動車両で、最高速度は概ね6km/h〜10km/hに制限されています。道路交通法上は歩行者として扱われ、歩道走行が原則とされる一方で、信号機や横断歩道のない交差点では自動車と同様の注意が求められます。特に見通しの悪い交差点では、ドライバーとシニアカー利用者双方の安全確認が不可欠です。
高齢者交通事故の動向
警察庁の「令和6年における交通事故の発生状況」によると、2024年の交通事故死傷者数は全体で減少傾向にあるものの、65歳以上の高齢者による死亡事故は増加し、75歳以上の運転者では死亡事故率が75歳未満の約2倍に達しています 。シニアカー利用中の事故件数は公表統計には含まれませんが、歩行中や自転車乗用中の高齢者事故と同様に「見落とし」や「死角」の問題が深刻です。
交差点におけるリスク要因
今回の現場は信号機や横断歩道のない交差点であり、右左折車両と直進する歩行者・シニアカーが交錯しやすい構造でした。交差点での「一時停止義務」や「安全進行義務」がドライバーに課される一方、シニアカー利用者には十分な減速・停止・目視確認が難しいケースもあります。この種の交差点は全国的にも高齢者事故が多発する地点として指摘され、見通し改善や安全施設の整備が求められています。
類似事故との比較
2023年には埼玉県内で同様にシニアカーと乗用車が衝突し、80代女性が重傷を負う事故が発生しています。また、横断歩道のない交差点での事故例として、2022年には京都市で高齢者が自転車で渡ろうとした際に右折車と衝突したケースがあります。いずれも「思いやり運転」の欠如と環境整備不足が背景にあり、今回の事例も同様の教訓を示しています。
過失運転致傷罪と教職員の責務
自動車運転処罰法第2条は、過失により人を負傷させた場合に「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」を定めています。公務員や教職員が事故を起こした場合、その社会的責任は一層重く問われます。今回逮捕された中学教諭は、安全確認義務を怠った点で公務員倫理にも抵触する可能性があり、刑事のみならず懲戒処分や免許停止の対象となる見込みです。
高齢社会と移動支援の課題
日本は高齢化率が30%を超え、シニアカー利用者も今後増加が見込まれます。公共交通の利便性向上とともに、歩道や道路構造のバリアフリー化、交差点における視界確保のためのミラー設置や一時停止標識の追加といったインフラ整備が急務です。また、高齢者やドライバー向けに「交差点安全研修」を強化し、双方の安全意識を高める取り組みが求められます。
地域での対策と今後の展望
明石市では市内各地で交差点改良工事を進めており、今秋には魚住町内の複数交差点において一時停止義務化と視認性向上のための路面マーキングが計画されています。さらに、シニアカー利用者を対象とした交通安全教室の開催や、地域ボランティアによる見守り活動が強化される予定です。高齢者の安全確保と安心できる移動環境の実現には、行政・住民・ドライバーが一体となった取り組みが不可欠です。
まとめ
今回の明石市での事故は、「シニアカーが止まるだろう」というドライバーの甘い判断と、信号機・横断歩道のない交差点が重なった悲劇でした。高齢化社会が進む中、シニアカー利用者と自動車ドライバー双方の安全意識向上と、道路インフラの再整備を急ぐことが、同様の事故を未然に防ぐ鍵となります。


コメント:0 件
まだコメントはありません。