国内投資40年度に200兆円 政府案
国内投資40年度に200兆円 政府案
2025/06/06 (金曜日)
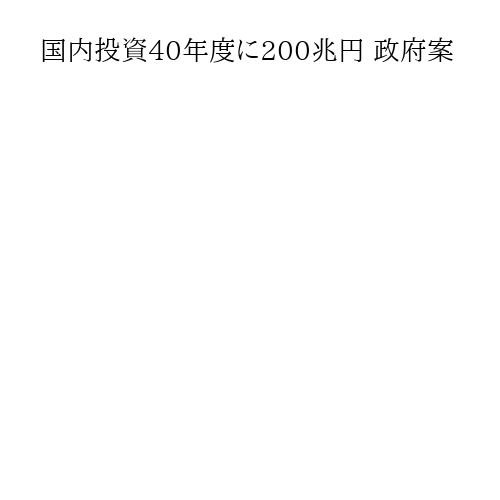
年1%の賃金上昇へ国が「先導役」に、「新しい資本主義」全容判明…医療・介護の公定価格引き上げも
政府の成長戦略「新しい資本主義実行計画」案の全容が5日、判明した。実質賃金の年1%程度の上昇定着を目指し、国や自治体による企業などへの発注で物価に合わせた価格の引き上げを徹底するほか、医療や介護など公定価格の引き上げを進め、賃上げに取り組む姿勢を示した。官民による国内投資を2040年度に200兆円とする目標も明記し、民間企業の「稼ぐ力」の向上を後押しする。
要約
政府は2025年6月5日、「新しい資本主義実行計画」(案)を公表しました。これには実質賃金の年1%程度の上昇を社会全体に定着させるため、国や自治体が発注する公共事業の価格を物価上昇にあわせて引き上げ、受注企業のコスト負担を軽減して賃金引き上げ余力を作ること、さらに医療・介護・保育・障害福祉など公的サービスの報酬である公定価格を大幅に引き上げて待遇改善を図る方針が盛り込まれています。また、官民連携で2040年度までに国内投資額を200兆円に高める目標も設定し、「稼ぐ力」の強化を通じた持続的な成長を図る姿勢を示しました。これまでのデフレ下では企業収益が伸びても賃金に十分反映されず、消費と投資が低迷する悪循環が続いてきたため、この計画では「賃金と物価の好循環」を強く打ち出しています。
1. 背景と歴史的経緯
日本は1990年代のバブル崩壊以降、長期にわたってデフレに苦しみました。企業の利益は上がっても、賃金が上昇しにくい状況が続き、家計の可処分所得が伸び悩んだことで消費が拡大せず、結果として企業も十分な投資を控えるという「賃金低迷→消費低迷→投資低迷」の負のサイクルが定着しました。特に2000年代以降、デフレ対策として実施された大規模な金融緩和や財政出動(アベノミクスなど)でも一時的な景気回復は見られましたが、賃上げにはつながりにくく、低成長状況が続いています。
こうした状況を打破するため、岸田文雄首相は2020年に『新しい資本主義』の構想を打ち出しました。その趣旨は、「成長と分配の好循環」を実現し、国民が所得向上を実感できる経済社会を作ることです。しかし、初期の取り組みでは具体的な「賃金引き上げをいかに実現するか」という点が曖昧で、実際の賃金上昇効果は限定的でした。そこで今回の実行計画案では、より直接的な賃上げ政策として、公共事業価格の物価連動や公定価格の改定を明確に盛り込むことで、構造的な賃上げを促す点に大きく舵を切りました。
2. 実質賃金1%上昇定着へ:公共事業価格の物価連動
実質賃金を年1%程度上昇させるために、政府は国や自治体が発注する公共事業の価格を、資材価格や人件費の高騰分を十分に反映させた形で適正に引き上げる仕組みを徹底するとしています。具体的には、道路や橋、トンネル、防災インフラ整備などの工事、公共施設の改修・建設、情報システム開発などにあたって、見積段階から物価高騰分を織り込むように発注要件を見直します。これにより建設・サービス業を中心とする受注企業は、コスト上昇による利益圧迫を回避しやすくなり、現場の作業員や技術者に対して賃上げや待遇改善を行いやすくなるという見込みです。
さらに、こうした発注価格の引き上げを「公共事業に限らず、生産財や役務提供の際の価格交渉においても当たり前」とするマインドセットを社会全体に浸透させ、「賃金を上げない企業は受注機会すら失う」という認識を定着させたい狙いがあります。これによって民間企業でも賃金の引き上げが経営判断の必須要件となり、賃上げの波及効果を広げることが期待されています。
3. 医療・介護・保育・障害福祉など公定価格の引き上げ
医療、介護、保育、障害福祉といった分野では、政府がサービス単価(診療報酬、介護報酬、保育所運営費の補助など)を定めていますが、長年にわたり物価や人件費上昇を十分に反映できず、サービス提供事業者の収益力が伸び悩んでいました。その結果、看護師や介護職員、保育士、障害福祉サービス職員らの待遇改善が進まず、慢性的な人手不足が深刻化しています。
実行計画案では、次回の診療報酬・介護報酬改定において、物価動向や人件費高騰分を十分に反映した大幅な引き上げを行い、関係業界の賃金底上げを図る方針が打ち出されました。たとえば医療分野では、病院経営の厳しさを軽減しつつ、医師や看護師らの給与を引き上げる予算を確保します。同じく介護分野でも、利用者の高齢化に伴う業務負荷増加に対応した加算や特定処遇改善加算を拡充し、介護職員の給与引き上げを後押しします。保育・障害福祉でも、運営費補助の増額や定員基準の見直しを通じた賃金改善が検討されており、いずれも早期に実施する姿勢を強調しています。
これにより医療・介護・保育・障害福祉分野の待遇改善と人材確保が進み、サービス品質の維持・向上にもつなげることが期待されています。また、待遇改善された職員がさらに消費を拡大し、地域経済を活性化させることで、全体的な成長効果を高める循環モデルを目指します。
4. 官民国内投資200兆円目標と成長分野支援
実行計画案では、官民を合わせた国内投資額を2040年度までに200兆円とする数値目標を明確に掲げています。2023年度実績は約140兆円程度であり、2040年度までの間に約60兆円の積み増しを図る必要があります。このうち公共投資はインフラ老朽化対策やデジタル化・グリーン化に向けた案件で増額を検討し、民間投資については以下のような支援策で促進を図ります。
- 半導体・電池・再生可能エネルギー・脱炭素技術などの重点分野に対して税額控除や補助金を拡充
- デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するための研究開発支援、データセンター整備支援を強化
- 中小企業向けの機械設備更新や省エネ化投資に対する補助制度を拡充し、生産性向上を後押し
- スタートアップ企業への投資促進策(ベンチャーキャピタルへの税制優遇、創業支援補助金)を拡大し、新産業創出を支援
これらの支援策を組み合わせることで、企業が設備投資や研究開発投資を躊躇せずに実行できる環境を整備し、新たな成長エンジンの創出と既存産業の高度化を図ります。特に、半導体・バッテリーなどは国際的なサプライチェーン再編が進む中で日本の競争力を高める要素と位置づけられ、重点的な支援が求められます。
5. 地域経済活性化と地方分散
新しい資本主義実行計画案では、地域ごとに適正な値付け慣行を確立し、賃金や物価上昇を地域全体で共有する構造づくりを目指しています。具体的には、道路や公共施設などのインフラ維持管理コストを物価動向に合わせて引き上げつつ、その発注先となる地元建設業やサービス事業者が賃金を引き上げる好循環を促します。これにより都市部だけでなく地方においても賃金水準向上の波及を狙います。
また、企業版ふるさと納税や地方創生推進交付金を活用し、地方の産業基盤を強化する施策も盛り込みました。地方に研究開発拠点やコワーキングスペースを整備し、スタートアップ企業の地方移転を促進することで、地方のイノベーション拠点化を図ります。この結果、首都圏一極集中の是正や地域間格差縮小を目指し、地方の雇用創出や地域経済の自立的成長を支援する方針です。
6. 制度設計と実効性確保に向けた課題
本実行計画案では、公共事業価格の物価連動や公定価格の改定といった大胆な政策を掲げていますが、現実の運用面では以下のような課題が想定されます。
- 発注価格の実行力:公共工事費の見積もりでは最終的にコスト削減圧力が働く場合があり、名目上の引き上げが現場コスト削減に回されてしまうリスクがある。そのため、発注時に物価上昇分を明示的かつ継続的に反映させる仕組みを厳格にルール化する必要がある。
- 公定価格改定の財源確保:医療・介護・保育などの報酬引き上げには財政負担が伴い、国・地方の財政健全性との両立が課題となる。具体的には、改定率を決定する際の財源配分や、診療報酬改定サイクルの再検討が必要となる。
- 企業投資誘導策の有効性:税制優遇や補助金だけでは、企業が将来の需要見通しや海外市場との競争を考慮して投資を慎重に行う場合がある。投資後の収益性向上や人材確保を支援する包括的な環境整備が求められる。
- 労働市場・家計のマインドシフト:「賃金が上がることは当たり前」という価値観を定着させるには、企業側だけでなく労働者側の意識改革が必要。労働生産性向上やスキルアップ支援を通じて、生産性が給与に反映される仕組みを強化することが求められる。
7. 国際的・歴史的文脈
世界的には2008年のリーマン・ショック以降、「格差是正と成長の両立」をめざすインクルーシブ資本主義やステークホルダー資本主義が提唱され、欧米の先進国でも「分配強化策」を含む成長戦略が検討されてきました。日本ではバブル崩壊後の失われた30年でデフレが定着し、企業収益が賃金に還元されない構造が続いてきました。アベノミクス期には金融緩和と財政刺激策で景気は持ち直したものの、賃金上昇は限定的で、分配面での成果は不十分でした。
岸田内閣は2021年に「新しい資本主義実現本部」を設置し、賃上げや人への投資を打ち出してきましたが、当初は賃上げを誘発する具体的な政策が弱く、成果は限定的でした。今回の実行計画案は、公共部門の価格政策や公的サービス料金の抜本見直しを通じて、賃金引き上げを制度的に後押しする点で、これまでの成長戦略から一歩踏み込んだ内容といえます。
8. 今後のスケジュールと展望
政府は2025年6月中に実行計画案を閣議決定し、速やかに制度設計の詳細を詰める方針です。公定価格改定は2025年末から2026年初頭にかけた診療報酬・介護報酬改定で実施し、2027年度以降の公共事業発注価格見直しも段階的に進めます。さらに、地方自治体に対しては公共事業や公定価格改定の財源支援を行い、地方ごとの事情に応じた対応を促します。
企業投資支援策については、2026年度予算で関連法改正や税制優遇措置を盛り込み、2027年度以降に本格的な効果が現れる見込みです。また、民間調査機関や研究機関によるフォローアップを行い、賃上げや投資拡大の進捗状況をモニタリングしながら、必要に応じて追加の対策を講じる予定です。
2040年度までに国内投資200兆円を達成し、実質賃金を年1%上昇させる目標を着実にクリアするためには、政府・企業・労働者・地方自治体が一体となって制度運用を進める必要があります。特に中小企業や地方の事情を考慮しつつ、分配と成長の好循環を実現するための制度設計と現場実装が今後の焦点となるでしょう。
9. まとめ
「新しい資本主義実行計画」案は、長年のデフレ・低成長から脱却するため、賃金上昇と投資拡大を同時に打ち出す政策パッケージです。公共事業価格の物価連動、公定価格(医療・介護・保育・障害福祉)引き上げといった具体策により、現場でのコスト負担軽減と待遇改善を促します。また、官民合わせた国内投資を2040年度までに200兆円とする数値目標は、資本形成を通じて企業の競争力強化と生産性向上を図る狙いです。
歴史的には、バブル崩壊以降、賃金が伸び悩み成長の好循環が実現しなかった問題を踏まえ、政府が制度的に賃上げを後押しする初の試みといえます。ただし、実際に現場で価格転嫁を徹底し、公定価格改定を適切に実行するには、財源確保や制度運用上の課題が多く残ります。今後は、政府と地方自治体、産業界、労働界が連携し、継続的なモニタリングと柔軟な政策対応を行うことで、賃上げと投資拡大の好循環を本当に実現できるかが試されます。


コメント:0 件
まだコメントはありません。