北村晴男弁護士、中国人の日本への帰化は「非常にリスクある」 参院選立候補会見で持論
北村晴男弁護士、中国人の日本への帰化は「非常にリスクある」 参院選立候補会見で持論
2025/07/01 (火曜日)
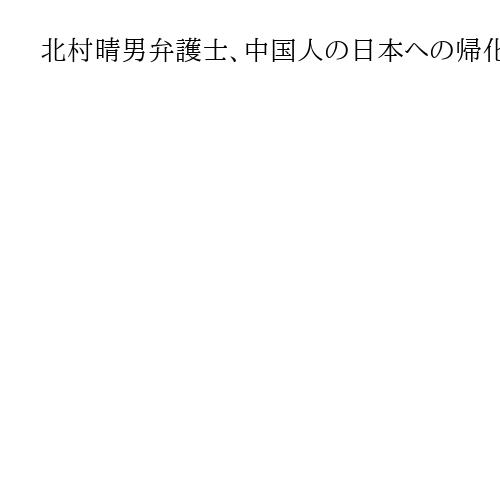
国内ニュース
北村氏はまず、「日本人に対して苛烈な憎悪をあおる国が近隣にある」と切り出した。「小さいころから(中国国内で日本に抗うような)激しい教育をして、そうやって育った人に日本人になってもらうことには非常にリスクがある」と述べた。
そのうえで、中国について「天安門事件(1989年)以降、『日本軍が戦前、ありえないようなひどいことをした。日本に報復する』という、とんでもない教育を行ってきた」と語った。
「
中国の反日教育と愛国主義教育の実態──国家プロパガンダとしての歴史と展開
「小さいころから激しい教育をして、日本に抗う人に育てる」──北村晴男氏が指摘するように、中国では長年にわたり教科書・メディア・法律を駆使した「反日教育」が国家プロパガンダとして徹底されてきた。本稿では、その歴史的背景、法制度、教育現場での実態、国際比較、そして日本への影響を多角的に検証する。
1. 反日教育の起源:建国期から毛沢東時代
中華人民共和国建国(1949年)直後から、中国共産党は歴史教育を国民統合の手段として活用した。当初は反帝国主義論の一環として日本の旧植民地支配や侵略行為を批判の対象とし、1950~60年代には毛沢東思想のもとで「日本=旧帝国主義」のイメージを強調。文化大革命期(1966~76年)には、反日キャンペーンと同時に国内の「反革命分子」排除に利用され、歴史が統制された。
2. 天安門事件以降の「愛国主義教育」強化
1989年の天安門事件弾圧後、共産党は政権基盤の再強化を図るため、江沢民政権下で「愛国主義教育キャンペーン」を全国展開。1990年代末には学校の教科書・授業から社会人向け講座まで「日本軍の残虐行為」を繰り返し教えることで、国民の「日本憎悪」を固定化した。
3. 教科書・メディアを通じたプロパガンダ
2000年代以降の教科書改革では、日中戦争や南京大虐殺の描写が拡大され、「日本が中華民族に行った非人道的行為」を詳細に記述。テレビ・新聞・インターネットでは国営メディアが「日本=敵」のメッセージを反復し、ドラマや映画でも反日要素を盛り込むことで世論をあおり続けている。
4. 法制化された愛国主義教育:2024年「愛国主義教育法」
2023年10月、全国人民代表大会常務委員会は「愛国主義教育法」を可決し、2024年1月1日より施行。法第1条は「中華民族の偉大なる復興のため、愛国主義を全社会で推進する」と定め、教育機関のみならず、インターネット事業者にも「愛国的コンテンツ」の提供義務を課した。
5. 若年層への影響:ナショナリズムと「精日」排斥
愛国主義教育の強化により、若年層の間ではSNS上で「日本製品不買」や「精日(精神的日本人)排斥」の動きが活発化。世論調査では60~70%が反日感情を肯定し、大学生のナショナリズムは日本批判を愛国心の証とする傾向が顕著である。
6. 他国との教育制度比較
ドイツや韓国では、自国の戦争責任を教育の一部として冷静に扱い、和解教育や多文化共生を重視。一方、中国の愛国主義教育は戦争責任を強調するのみで、和解や相互理解を教えない点で大きく異なる。
7. 日本へのリスクと外交・経済への影響
中国国内で「憎日教育」を受けた世代が日本に留学・就労する場合、相互理解が難航し、人的交流の減少やビジネス摩擦の増大を招く恐れがある。また、政治的対立を煽る世論により、日中間の経済協力や外交協議が歴史問題でたびたび停滞している。
まとめ
中国の反日教育は、建国期からの国家戦略として始まり、天安門事件以降に愛国主義教育法の制定で制度化された。教科書・メディア・法制度による多層的なプロパガンダは、若年層へ深く浸透し、日本への敵対感情をあおっている。今後、日本側は歴史教育の国際比較や二国間交流の再構築を通じて、偏った教育に対抗し、真の相互理解を促進する取り組みが不可欠である。


コメント:0 件
まだコメントはありません。