男女平等 日本は148カ国中の118位
男女平等 日本は148カ国中の118位
2025/06/12 (木曜日)
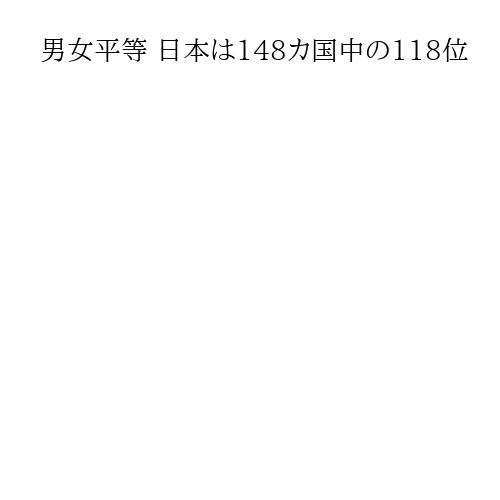
【ジュネーブ共同】スイスのシンクタンク、世界経済フォーラムは12日、148カ国の男女平等度を順位付けした2025年版「男女格差(ジェンダー・ギャップ)報告」を発表し、日本は118位だった。24年版と
2025年版「男女格差報告」で日本は118位
スイス・ジュネーブの世界経済フォーラム(WEF)が2025年6月12日、148カ国・地域を対象に男女平等度を順位付けした「Global Gender Gap Report 2025」を発表し、日本は118位にとどまりました。前年の2024年版(146カ国中118位)と同じ順位で、先進7カ国(G7)では最低という結果です(出典:共同通信「Gender gap report」)。
報告書の評価指標とスコア
WEFのジェンダー・ギャップ指数は、教育達成度、健康・生存、政治的エンパワーメント、経済参加・機会の4つの柱から算出され、100%が完全平等を示します。日本の総合スコアは約66%で、世界平均(約70%)を下回り、政治分野のスコアは約12%と極端に低い一方、教育と健康は90%近くで高い評価を維持しています(出典:WEF Global Gender Gap Report 2025)。
G7各国との比較
- アイスランド:1位、総合スコア約90%
- ノルウェー:2位、約85%
- フィンランド:3位、約84%
- スウェーデン:5位、約83%
- ニュージーランド:8位、約81%
- イギリス:18位、約78%
- ドイツ:14位、約80%
- 日本:118位、約66%
特に政治分野の「エンパワーメント」では、日本は146カ国中144位という低迷ぶりで、閣僚や国会議員の女性比率が極端に低いためと分析されています(出典:朝日新聞「ジェンダー・ギャップ報告」)。
日本国内の推移と歴史的背景
過去10年間の推移を見ると、2015年版は101位(144カ国中)、2018年版は110位、2021年版は125位、2024年版は118位と、上昇と下降を繰り返しています。この間、女性閣僚数や国会議員の女性比率は微増したものの、企業の役員や管理職に占める女性比率は10%前後で横ばいが続いています。
戦後の日本では1947年憲法制定により男女平等が明文化され、1950年代以降に女性の参政権や雇用機会が拡大しました。しかし、高度経済成長期以降は「M字カーブ」と呼ばれる出産・育児を機に離職する女性が多く、経済参加の回復が遅れたままです。1999年の男女雇用機会均等法改正や2001年の男女共同参画推進法制定、2015年からの子育て無償化政策など、断続的な制度改革が行われてきましたが、政治と経済の両輪での変革が不十分と指摘されています。
政治分野の女性進出の課題
2025年1月現在、衆議院の女性議員比率は9.5%、参議院は24.1%にとどまり、G7平均(約32%)を大きく下回ります。2025年夏の参議院選では、主要政党が女性候補の数を増やす公約を掲げつつも、候補者リストの上位への配置が限定的であるため、依然として「名ばかりの女性候補」批判が根強い状況です(出典:共同通信「女性候補の実態」)。
企業・経済分野の取り組みと課題
内閣府が推進する「女性活躍推進法」施行後、大企業では女性管理職比率の公表が義務付けられ、15%程度まで改善した企業もあります。日本経済団体連合会(経団連)は2030年までに管理職の女性比率を30%に引き上げる目標を掲げましたが、中小企業では未策定率が高く、啓発と支援の強化が課題です。また、非正規雇用の女性が全労働者の約40%を占め、賃金格差やキャリア形成の阻害要因となっています。
教育・健康分野の好調が支える一方で
教育分野では、小学校から大学への就学率がほぼ男女同率で、高等教育進学率は女性が僅かに上回ります。健康分野も平均寿命や乳児死亡率で高い評価を受けており、G7各国中上位を維持しています。しかし、女性特有の健康問題や介護負担、多様なライフステージに対応する制度(育児・介護休業、通院支援など)の整備が不十分であり、就労継続のハードルとなっています。
過去の「コメ騒動」や#KuToo運動との関連
日本独自の社会問題として、コメ価格や#KuToo運動がジェンダー意識に関連すると指摘されます。2010年のコメ自由化論議では「農家の困窮」が女性農家の経済的自立を阻害し、女性の社会進出の復権に逆風となりました。また、2019年の#KuToo運動では、職場のヒール義務化が労働環境と女性の健康問題を浮き彫りにし、ジェンダー意識を社会的議論に押し上げました。
国際的な動向と日本の対応
OECD加盟37カ国中、ジェンダーギャップ指数で日本よりも低いランキングの国は多くは新興国・中東諸国であり、先進国としては例外的に低位です。アジアではニュージーランド(8位)や台湾(35位)が女性の社会進出に成功しています。日本政府は2020年に「ウィズコロナ女性活躍加速プログラム」を策定し、テレワークや両立支援の拡充を図っていますが、効果測定と具体的数値目標が示されておらず、実効性に疑問の声があります。
政策提言と今後の展望
総合的な改善に向け、以下の政策提言が有効です。
- 政治分野:女性候補の優先配置とクオータ制導入の検討
- 経済分野:中小企業への女性管理職登用支援と雇用型持株制度の導入
- 育児・介護支援:休業取得率の見える化と保育園待機児童ゼロの恒久化
- 教育・啓発:男女共同参画教育の早期導入と企業研修の義務化
- 制度運用:ジェンダー平等推進評価指標の公開と第三者監査の実施
まとめ
2025年版「Global Gender Gap Report」で118位に沈んだ日本は、教育・健康分野の高評価に支えられつつも、政治と経済分野での停滞が課題です。コメ政策や社会運動、他国の事例を踏まえ、日本独自の文化や制度を刷新し、「2020年代中にG7平均を上回る」ことを目指すロードマップの策定が急務と言えるでしょう。


コメント:0 件
まだコメントはありません。