中国の国連への影響力拡大 日本には目標・戦略あるのか
中国の国連への影響力拡大 日本には目標・戦略あるのか
2025/06/22 (日曜日)
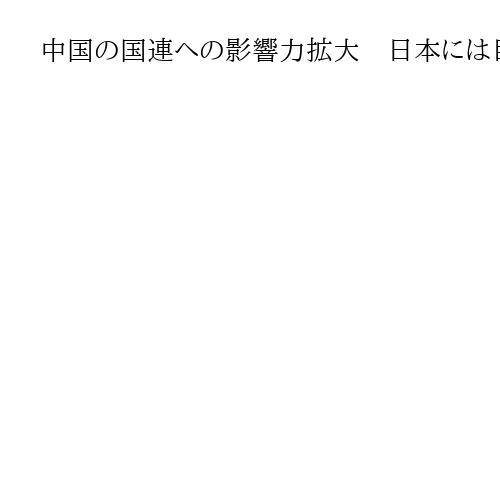
国際ニュース
中国が国連などの多国間組織を活用してグローバルサウスへの影響力を拡大させ、欧米主導の国際秩序を根底から塗り替えようとしている。米国の国連離れはこうした動きを一層加速させかねない。
序章:中国の国連活用と米国の後退
2025年6月22日付産経新聞は、中国が国連をはじめとする多国間組織を戦略的に活用し、途上国(グローバルサウス)への影響力を急速に拡大しつつあると報じました。これに対し、トランプ米政権は予算削減の一環として国連平和維持活動やWTOへの拠出金を凍結・削減する計画を進めており、欧米主導のリベラル国際秩序に亀裂が生じています。(出典:産経新聞2025年6月22日)
1.米国の国連離れと予算削減の実態
2025年4月、ホワイトハウスの行政管理予算局(OMB)は国連平和維持活動への資金拠出打ち切りを提案し、その背景にはマリやレバノン、コンゴ民主共和国での活動の成果不足が挙げられました。米国は国連の通常予算の約22%、平和維持予算の約27%を拠出する最大の資金供給国であり、その削減案は国連事務局の予算逼迫を招いています。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
さらに同年3月には、トランプ政権が世界貿易機関(WTO)向け拠出金の支払いを凍結し、対外開発援助大手のUSAIDについても大幅削減を実施。これらの動きは、米国第一主義を掲げる政権方針の一環と位置づけられ、国連の人道・開発活動に与える影響を懸念する声が高まっています。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
2.中国の多国間組織戦略と南南協力
中国は1955年のアジア・アフリカ会議以来、発展途上国との連携を重視してきましたが、近年は国連安全保障理事会の常任理事国としての影響力を強化しつつ、1964年結成のG77に代表される途上国グループへの働きかけを強めています。2025年版『台頭するグローバル・サウスと中国』では、中国の南南協力戦略が詳細に分析されており、開発援助や技術移転を「外交のツール」とする手法が確認されています。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
この文脈で注目を集めるのが「グローバル開発イニシアティブ(GDI)」で、2021年に習近平国家主席が国連総会で提唱した枠組みです。SDGs達成を共通目標としながら、中国主導の資金・技術協力ネットワークを構築し、途上国の支持を集めています。UNDPやWHOなど国連専門機関への資金拠出拡大とプログラム設計権の強化を通じ、多国間フォーラムでの中国案採択率を高める狙いが鮮明です。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
3.BRICS・一帯一路構想との連動
中国はBRICS(ブラジル・ロシア・インド・中国・南アフリカ)の拡大を推進し、イランやアルゼンチンなど最大12カ国超に拡大。さらに「一帯一路」構想を通じてアジアから欧州・アフリカに至る広域インフラ投資を展開し、現地経済の中国依存度を高めています。これにより、途上国が国連決議や資金拠出の場面で中国支持を示す事例が増加しています。
こうした経済的・開発的アプローチは、1960年代にソ連が第三世界で展開した支援戦略と類似点を持ちますが、今日の中国は巨額の資金力と内発的成長力を背景に、制度的フレームワーク(AIIB、RCEP、AIIB)を併用しながら多層的な影響力を確立している点で異なります。:contentReference[oaicite:4]{index=4}
4.国連専門機関での影響力強化
近年、中国はWHO、UNESCO、国連食糧農業機関(FAO)などの専門機関トップポストを獲得し、予算配分やプログラム優先度の決定に直接的に関与しています。2021年の国立国会図書館調査報告書によれば、国連専門機関15機関中4機関のトップが中国人であり、中国は途上国票を背景に選挙戦略を展開。これにより、衛生・教育・農業分野の国連活動が中国の政策目標と整合的に運営されるケースが増えています。:contentReference[oaicite:5]{index=5}
5.法的枠組みとガバナンスの再編
中国は国際法や既存の多国間条約を活用しつつ、「共通運命共同体」や「グローバル文明イニシアチブ」といった文化・価値観を含む新たな概念を提唱。これにより、欧米諸国が重視する人権・民主主義議題を「内政不干渉」の原則でかわし、開発・安定優先の課題設定へと国連議論の焦点を移行させています。
一方、米国が分担金や任意拠出金を削減・凍結する動きは、国連の財政基盤を揺るがし、多国間協力の持続可能性に疑問符を投げかけています。UN事務局が37億ドルの予算を20%削減し、約6,900人の職員削減を検討しているとの内部メモも明らかになっており、多国間機関の将来像が問われています。:contentReference[oaicite:6]{index=6}
6.今後の展望と課題
中国の多国間組織戦略は、国際ルール形成の初期段階での「策定権」を獲得し、途上国の賛同を拡大することで、欧米主導の枠組みを再編しつつあります。しかし、現地での債務負担やガバナンス透明性の欠如、地域安全保障への影響というリスクも指摘されており、持続可能性の担保が問われます。
今後、米国やEUが拠出金復元やODA再編、国連安保理改革を通じてリベラル国際秩序の再活性化を図るかが重要なカギとなります。日本や欧州は、多国間協力の実利と価値観の両立を目指し、途上国ニーズに即した支援プログラムを提供する必要があります。価値観の対立ではなく、開発・人道・環境など共通の課題解決を軸とした協調ルール構築が、次世代の国際秩序を左右するでしょう。


コメント:0 件
まだコメントはありません。