邦人女性1人の死亡を確認 ペルー最高峰ワスカラン登山中遭難、パートナーは救助搬送中
邦人女性1人の死亡を確認 ペルー最高峰ワスカラン登山中遭難、パートナーは救助搬送中
2025/06/26 (木曜日)
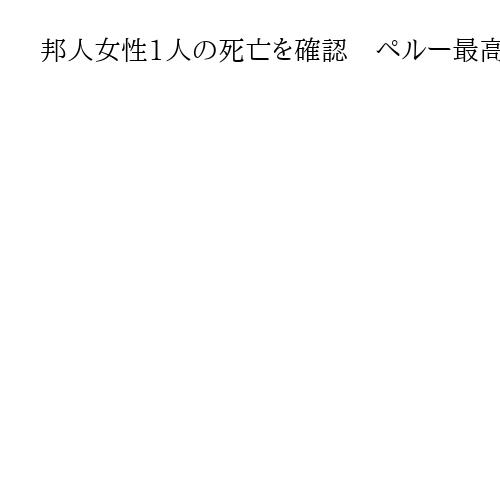
国際ニュース
2人は約2週間前にペルーに入国。ワスカラン山に登山中だった。標高6500メートル付近で動けなくなり、24日に稲田さんが低体温症で行動不能となり、救助を求めていた。
WMAジャパンによると、現地警察などが救助活動を開始。当初は2人とも意識があったが、山は雪に覆われていることなどから捜索は難航。26日(現地時間25日)に救助隊が到着した際には稲田さんは意識がなかったという。WMAジャパンによると、稲
はじめに
2025年6月24日、ペルー・アンデス山脈のワスカラン山(Huascarán、標高6,768メートル)に登山中の日本人登山者2人が遭難しました。テラダ・サキさん(36)とイナダ・チアキさん(40)は、約2週間前にペルーに入国し、単独でワスカランに挑戦していましたが、標高約6,500メートル付近で動けなくなり、稲田さんが低体温症で行動不能となったことから衛星電話で救助要請を発信。現地警察や山岳救助隊、民間救助団体が懸命の捜索を行い、6月26日(現地時間25日)に現場に到着した際、稲田さんは意識不明、寺田さんは辛うじて意識を保っていたものの容体は極めて厳しい状態でした(出典:産経ニュース)。本稿では、今回の遭難の経緯と背景、ワスカラン山の特性、遭難救助の難しさ、過去の事例比較、安全対策のポイントを詳述します。
1.遭難の経緯と当日の状況
2人は2025年6月初旬にペルーに入国し、首都リマで装備を整えた後、車でワスカラン国立公園に移動。現地ガイドを伴わず、自己計画での登山を開始しました。ワスカランは標高差が大きく、登頂ルートは氷河と雪壁が連続するため、通常は数日の高所順応が必須とされます。24日、標高約6,500メートルの“キャンプ3”付近で2人は悪天候に見舞われ、低体温症や高山病の症状を訴え始めました。稲田さんは足が動かなくなり行動不能に陥り、寺田さんが衛星電話で救助要請を行いました。現地救助隊が26日に到着したものの、氷雪の厚いルートと強風のためヘリの着陸ができず、徒歩でのアクセスとなり、到着時には稲田さんは極度の低体温状態でした。
2.遭難者のプロフィールと登山経験
テラダ・サキさん(36)は登山歴10年を誇り、富士山をはじめ日本アルプスでの高所登山経験が豊富でした。昨年は南米アンデスのアコンカグア(6,960m)にも挑戦し、酸素瓶を使わずの登頂に成功しています。イナダ・チアキさん(40)は登山歴12年で、欧州アルプスやヒマラヤのベースキャンプまでの複数ルートを経験。ともに経験豊かな中上級者とみられますが、ワスカランの氷河混じりのルートや急変する気象条件への対応が最後の最後で裏目に出た形です。
3.ワスカラン山の地理的特徴と危険性
ワスカラン山はペルー北部に位置するアンデス山脈最大の氷河を擁し、国立公園にも指定されています。主峰の北峰は6,768メートル、南峰は6,654メートル。岩壁と氷壁が複雑に入り組み、落石や氷塊の崩落(氷河キャリナ)による事故が多発します。また、標高5,500メートル以上は酸素濃度が平地の半分以下となり、対応が遅れると高山肺水腫や脳浮腫を引き起こしやすいのが特徴です。2022年には同じルートで米国人パーティが滑落死する事例も発生しており、登山道整備が難しいことから毎年遭難者が後を絶ちません。
4.高山病と低体温症のメカニズム
高山病は急激な標高上昇により酸素不足が生じ、頭痛・吐き気・倦怠感を伴います。重症化すると高山肺水腫(呼吸困難)や高山脳浮腫(意識障害)に進展します。低体温症は気温0℃以下の環境で体熱を奪われ、体温が35℃以下になると手足の機能が低下し、さらに重度になると意識喪失に至ります。ワスカラン山頂付近は夜間風速20m/sを超えることも珍しくなく、保温装備が万全でも数時間で体温を奪われる危険があり、即時の下山や救助が困難になります。
5.救助活動の難航ポイント
今回の救助にはペルー山岳警察(Policía de Montaña)、地元山岳協会、民間救助団体WMAジャパンなどが連携しましたが、〈1〉悪天候によるヘリ着陸困難、〈2〉高所での薄氷や雪壁による徒歩アクセスの危険、〈3〉携行酸素や医療装備の運搬難、〈4〉通信途絶のリスク――などが重なり、到着に時間を要しました。到着後も、稲田さんは意識を失っていたため、アイスクライミング技術と医療的ケアを同時に行わねばならず、通常の山岳レスキュー以上の困難を伴いました。
6.同地域における過去の遭難事例比較
ワスカランでは2006年の大地震による氷河崩落で多くの登山者が犠牲となったほか、2019年には高所順応不足による喘息発作で米国人登山家が死亡しました。これらの事例では、ガイド付きパーティの装備不足や天候予測ミスが主因とされており、今回の2人も無ガイド・自己判断での登頂を選択した点が共通しています。一方で、救助体制は過去10年で整備が進み、米国・欧州の衛星救助信号システムが導入されたことから、以前よりは早期発見につながる可能性が高まっています。
7.ペルーにおける登山規制とガイド義務化の動き
ペルー政府は近年、マチュピチュやコルカ渓谷と同様に、環境保護と遭難防止のため「標高5,000メートル以上の登山には公認ガイドの同行を義務化」する法規制を検討中です。ワスカラン国立公園管理局(SERNANP)では、ガイド未同行の登山者に対し罰金や登山許可の停止を科す制度草案を公開しており、2026年から施行される見通しです。これにより、無ガイド登山による事故抑止と環境負荷低減が期待されています。
8.安全登山の心得と装備選定
- 高所順応:標高差500~700m/日程度でキャンプを設置し、数度往復して体を慣らす
- 気象情報:現地気象台や衛星データを活用し、常に最新情報を入手する
- 保温装備:ダウンジャケット、防寒ビブラムブーツ、顔面保護マスクを完備
- 通信機器:衛星電話・PLB(位置情報発信ビコン)・携帯GPSを携帯
- 医療装備:高山病薬、酸素ボンベ、応急担架を最小限同伴
9.国際救助協力のあり方と課題
今回の救助では、ペルー国外からの衛星救助システム導入が功を奏しましたが、現地要員との連携不足や言語・医療プロトコルの不統一が課題として浮上しました。将来的には、日本山岳救助機構(JRO)や国連の国際CLG(国際山岳レスキュー連合)などが主導し、訓練や装備標準化を進める必要があります。また、民族地域の文化・伝統に配慮した救助ルールの整備も求められます。
まとめ
ワスカラン山での日本人2人の遭難事故は、高所登山のリスクと救助体制の現状を改めて突きつけるものでした。経験豊富なクライマーでも厳しい気象と高所環境には背を向けられず、自己判断だけでは限界があります。今後はペルー政府のガイド同行義務化や国際的救助協力強化に加え、登山者自身の安全意識向上と装備・順応計画の徹底が不可欠です。無事の救出と早期回復を祈りつつ、世界中の登山愛好者にとって教訓となる事例として記憶されるでしょう。
出典:産経ニュース「ワスカラン山で日本人登山者2人が遭難、低体温症で行動不能に(2025年6月26日)


コメント:0 件
まだコメントはありません。