米国家情報長官 異例の核廃絶主張
米国家情報長官 異例の核廃絶主張
2025/06/11 (水曜日)
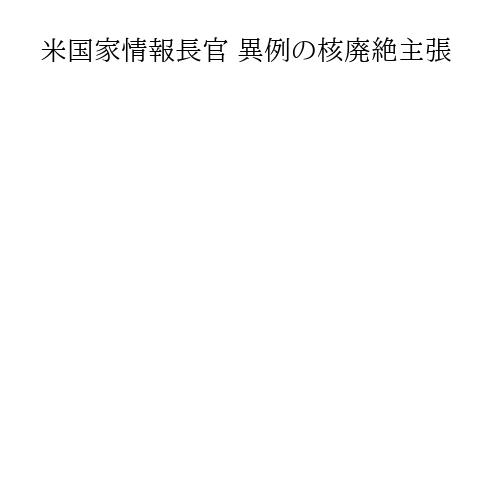
国際ニュース
米情報長官、異例の核廃絶訴え 広島・長崎触れ「狂気に終止符を」
米国家情報長官ギャバード氏の異例の訴え
2025年6月10日、米国家情報長官のシェブロン・ギャバード氏は自身のX(旧ツイッター)で、広島・長崎の被爆体験に触れつつ「核兵器廃絶が必要だ」と異例のメッセージを発信しました。動画の冒頭で「私は最近、広島を訪れ、ヒバクシャの証言と絵画から胸を締め付けられる悲しみを受け止めた」と語り、核戦争の現実的危険性を強調しました。
ギャバード氏の経歴と立場
ハワイ出身のギャバード氏は、元陸軍中佐で、アフガニスタンなどでの実戦経験を持つ異色の情報長官です。2024年に就任して以降、安全保障体制の見直しを主導してきましたが、核廃絶を公に訴えるのは在任中としては極めて珍しく、同氏の人道的視点が強く表れた発言とされています。
広島・長崎への言及と被爆体験の重み
ギャバード氏は動画で、広島で見た「ヒバクシャ」の絵画について、「写真よりも強烈に苦痛と喪失感を伝えてくる」と述べ、被爆体験の具体的苦しみを世界に訴えました。さらに「現代の核兵器は当時より圧倒的な威力を持ち、たった1発で数百万人を瞬時に葬る」と警告し、「核の冬」など使用後の人類への壊滅的影響を強調しました。
国際情勢と核抑止論との対比
現在、米露中をはじめとする核保有国間の緊張は高まっており、「抑止力」を理由に核備蓄を正当化する論調が根強い一方、「狂気に終止符を」と呼びかけたギャバード氏の主張は、抑止論への疑問を突きつけるものです。彼は「政治的エリートや戦争推進派が恐怖と緊張をあおっている」と指摘し、抑止の限界を訴えました 。
核廃絶運動の歴史的経緯
核廃絶を目指す動きは1945年以降、被爆者や市民団体を中心に継続してきました。1982年の国際反核デーや1996年の核不拡散条約(NPT)強化会議、2017年の核兵器禁止条約(TPNW)採択など、法的・市民社会的に発信力を持つイベントが重ねられ、2017年の批准国は122カ国に達しています。しかし核大国の不参加が続いており、条約の実効性には限界があります。
他国指導者の発言との比較
過去には1985年にゴルバチョフ大統領が「核兵器なき世界」を提唱し、1994年にネルソン・マンデラ氏も「核時代の終わり」を訴えました。また2023年には前国連事務総長が「核兵器は道徳的に容認できない」と述べましたが、現役情報長官の立場から核廃絶を直接呼びかける事例は極めて珍しく、ギャバード氏の行動は国際的にも注目されています。
日本国内の反応
被爆地を擁する日本では、政界からも賛同の声が上がりました。被爆者団体は「米政府の高官が被爆地を訪れ、その悲惨さを世界に訴えた意義は大きい」と評価し、野党からは「核廃絶を真正面から議論すべきだ」との声が相次ぎました。一方、政府・与党は慎重なコメントにとどめています。
今後の課題と展望
ギャバード氏の訴えを受け、国際社会で核廃絶へ向けた具体的措置を模索する動きが加速する可能性があります。①核兵器禁止条約への署名・批准、②核軍縮交渉の再開、③核備蓄削減の実行メカニズム構築、などが現実的課題です。特に米露中の三極間で実効的な軍縮交渉を再開できるかが焦点となるでしょう。
結論
米国家情報長官という安全保障の最前線に立つ立場から、被爆地を背景に「狂気に終止符を打つ必要がある」と核廃絶を訴えたギャバード氏。この発言は、核抑止を前提とする従来の安全保障論を揺さぶり、人類が直面する破滅的リスクを改めて世界に知らしめるものです。今後、彼の呼びかけがどのように国際交渉や世論に影響を与えるか注視されます。


コメント:0 件
まだコメントはありません。