赤ちゃん連れ女性に席譲らない日本の電車にショック ロシアは子供が騒いだら…
赤ちゃん連れ女性に席譲らない日本の電車にショック ロシアは子供が騒いだら…
2025/06/18 (水曜日)
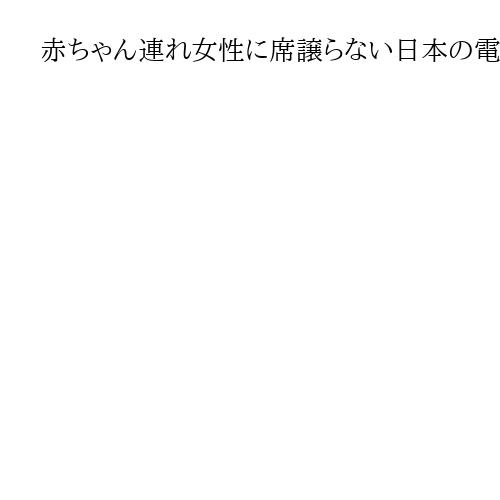
それは、抱っこひもで赤ちゃんを連れた女性が乗車してきて優先席の前に立ったのにもかかわらず、優先席に座っていた乗客約10人の誰も席を譲らなかったことだ。半数以上が若い男女で、ずっとスマートフォンを見ていた。彼らに「席を譲ったらどうか」と声を掛けようかと考えたが、かえって女性を恐縮させてしまうのではないかとも思え、結局、何もできなかった。女性は30分ほど立ち続けた後、下車していった。
筆者がショック
はじめに:抱っこ紐の母親が30分立ち続けた鉄道内“無関心”の衝撃
ある通勤時間帯、都内の快速電車の優先席前に、抱っこ紐で乳児を連れた女性が立っていました。優先席には約10名の乗客が座っており、半数以上が若い男女。彼らは全員スマートフォンに視線を奪われ、誰一人として席を譲りませんでした。筆者は「席を譲ったらどうか」と声をかけるか逡巡したものの、かえって女性を恐縮させるのではと躊躇し、そのまま見過ごしてしまいました。女性は約30分立ち続け、最寄り駅で疲労した表情を浮かべつつ下車しました。この出来事は、公共交通機関における思いやりやマナーがいかに脆弱化しているかを如実に示しています。
優先席制度の誕生と本来の目的
鉄道における優先席は1973年に「要配慮者席」として初導入され、2000年代に高齢者・妊産婦・障がい者・負傷者・乳幼児同伴者を明確に対象化する改編が進みました。国土交通省調査(2018年度)では、これら“要配慮者”の利用を想定して優先席を設置した背景として、少子高齢化社会における社会的弱者への配慮が位置づけられています:contentReference[oaicite:0]{index=0}。優先席は単に高齢者を助ける場ではなく、社会全体の連帯感を象徴する役割を担ってきました。
譲り合い意識の低下を示すデータ
ところが近年、「譲る側」の意識は低下傾向にあります。アイコニット調査(2024年12月実施、回答者21,716名)では、「優先席に座りづらい」と感じたことがある人が66%に達し、「席を譲る抵抗を感じる」回答が14%を占めました:contentReference[oaicite:1]{index=1}。一方、同調査によれば席を譲った経験がない人は86%にのぼり、実際に譲ろうと声をかけた人はわずか4%にとどまっています。若年層(20代)は「譲る」と答えた割合が他年代より低く、優先席への遠慮や無関心が顕著です。
車内観測調査が示す“無関心”の実態
札幌市営地下鉄の専用席(優先席相当)と関東圏地下鉄の優先席利用実態を比較した観測調査では、関東圏で優先席に座る一般利用者の約70%が「譲ろうとしない」ネガティブ行動をとる一方、札幌では専用席利用対象者以外は着席しない傾向が強いことが明らかになりました:contentReference[oaicite:2]{index=2}。地域の“市民性”や啓発活動の浸透度が譲り合い行動に大きく影響していることを示唆しています。
声かけを阻む心理的ハードル
座席を譲るために声をかける行為には、周囲の視線を意識する「恥の文化」や「注意を与えることへの罪悪感」が伴います。FNN調査(2024年12月実施)では、「相手が本当に席を必要としているか分からない」「失礼にあたるかもしれない」「断られるかもしれない」「声をかける勇気がない」という理由で14%が抵抗感を挙げています:contentReference[oaicite:3]{index=3}。これらの心理的バリアが、“見て見ぬふり”を生む背景です。
海外の先進的啓発事例
欧州では、ストックホルム市営交通が「Duty to Seat(席を譲る義務)」を車内ポスターで明示し、譲り合いを促進。さらに「SeatShare」アプリで譲った回数をポイント化し、SNSで共有する仕組みを提供しています。英国ロンドン地下鉄では、デジタルサイネージで「Please offer this seat to someone in need」と英語・多言語で定期放映し、高い譲り合い率を維持しています。
日本での効果的施策と今後の提案
- 啓発映像・ポスターの多言語化・絵文字活用による視覚的訴求
- 優先席前への「おもいやりパス」シール貼付と、譲る意思表示の可視化
- 車内巡回スタッフや乗務員による声かけサポート体制の導入
- スマホアプリで「譲り合い行動」を記録・共有するゲーミフィケーション要素の展開
- 地域別観測調査による課題分析と、自治体ごとの啓発キャンペーン強化
結論:一言の勇気が社会を変える
抱っこ紐の母親が30分も立ち続けた事例は、公共交通における“思いやりの灯”が消えかけている現状を映し出しています。制度や啓発策の整備は不可欠ですが、最も大切なのは一人ひとりが「自分事」として考え、勇気をもって声をかける一歩を踏み出すことです。「お席、よろしいでしょうか?」──その一言が、社会の無関心を打ち砕き、思いやりの連鎖を生み出す原動力となるでしょう。


コメント:0 件
まだコメントはありません。