USS買収 米表明の「黄金株」とは
USS買収 米表明の「黄金株」とは
2025/06/13 (金曜日)
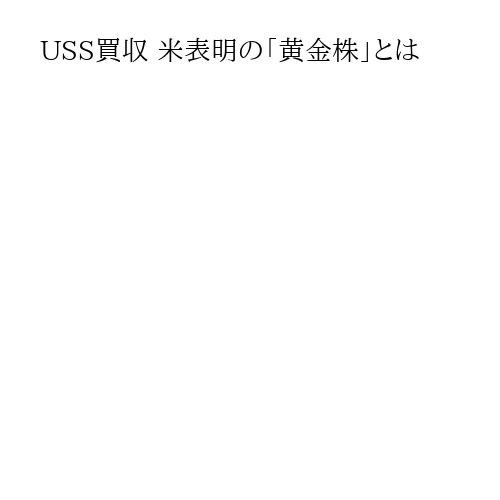
久保田博幸金融アナリスト6/13(金) 11:41(写真:ロイター/アフロ) トランプ米大統領は12日、日本製鉄のUSスチール買収計画について、経営上の重要事項に関して通常より強い拒否権を持つ「黄金株」を米政府が保有し、51%の所有権を米国が握ると表明した。
黄金株とは、株主総会で会社の合併等の重要議案を否決できる特別な株式のことで、拒否権付き株式ともいわれる。株式を買い占められる敵対的買収へ
速報:トランプ大統領の「黄金株」保有表明
2025年6月12日、トランプ米大統領はホワイトハウスで行われた日本製鉄(Nippon Steel)による米国鉄鋼大手USスチール(United States Steel)買収案件をめぐり、「我々は米国政府としてUSスチールの経営上の重要事項に拒否権を持つ『黄金株(golden share)』を保有し、結果的に51%の所有権を握る」と表明しました。トランプ氏は「この黄金株によって、合併や資産売却など重要議案について、米国政府が最終決定権を持つ」と強調したものの、株式の具体的な発行構造や権限行使の条件など詳細は明らかにされていません。USスチール社および日本製鉄側からの即時コメントは得られていないと報じられています 。
「黄金株」とは何か──概念と沿革
「黄金株」は、国家や他の特定株主が会社発行済み株式とは別に取得する特別株式で、企業の合併・買収や資産譲渡などの重要決定に対し「拒否権(veto)」を行使できる権利を持ちます。一般株主の議決権を上回る決定権を有し、いわゆる「拒否権付き株式」とも呼ばれます。英国の民営化初期(1984年のロイター民営化、BTの株式売却など)を契機に導入され、政府が国家的インフラや戦略的企業の経営に関与し続けるための手段として用いられてきました 。
今回の適用経緯とCFIUSの関与
日本製鉄によるUSスチール買収案は、2023年12月に合意に達した14.9兆円規模の案件で、両社は株式交換比率や買収価格(1株当たり55ドル)で合意済みでした。しかし、対米外国投資委員会(CFIUS)が国家安全保障上の懸念を指摘し、米政府の承認が必要となりました。CFIUSは「鉄鋼はインフラ防衛や製造業基盤として戦略的重要性が高い」として、合併承認の前提条件に「黄金株」の導入を要求したと伝えられています 。
経済・産業への影響と論点
米国政府の「51%支配権」表明は、従来の民間企業買収とは一線を画す介入と受け止められています。労働組合や株主からは「合併の透明性や公平性が損なわれる」「日本製鉄の技術導入や雇用創出効果が不透明になる」との懸念が上がる一方、一部の議会関係者は「国家安全保障上の最低限の措置」と評価しています。市場関係者は、USスチールの株価が一時5%超急騰した後、権利行使の具体性を見極めたいとして上下に乱高下する状況が続いています 。
過去の黄金株活用事例との比較
英国では1984年のBT 民営化時に政府が「ゴールデンシェア」を保有し、民間株主による敵対的買収を阻止したほか、1997年まで同株を通じて経営監視を行いました。ロシアにおいても1992年に大統領令で軍需企業などに政府の「黄金株」が導入されました。中国では近年、データ企業や半導体企業に「特別管理株式(黄金株)」を導入し、国家安全保障を理由に政府が重大決定をチェックする動きが強まっています。各国で制度設計や行使範囲に違いはあるものの、「国家の最終的な統制手段」としての共通点があります 。
法的・規制上の論点
米国においては、憲法的に議会の権限を政府が企業運営に介入する行為が許されるかが議論になります。先例として、欧州連合(EU)は2003年に英国政府のBAA(空港運営会社)「黄金株」保有をEU市場統合ルールに抵触するとして違法と判断しました。また、イタリアの「ゴールデンパワー(Golden Powers)」制度も、2024年にユニクレディトの合併案件で限定的に行使されました。米国でも司法判断を経て範囲や行使要件が明確化される可能性があります 。
今後の展望と注目ポイント
- トランプ政権下での行使要件・手続きの具体化と、後任政権による継続性の可否
- CFIUS提言の正式採用と議会承認のプロセス
- 日本製鉄側の対応──合併条件の再交渉や追加的保証提案
- 株主訴訟リスク──USスチール株主が「合併価値の毀損」を理由に提訴する可能性
- グローバルM&A慣行への波及──国家安全保障を理由にした「黄金株」導入案件の増加懸念
まとめ
今回の「USスチールにおける米政府の黄金株保有」表明は、従来のM&A市場では例を見ない国家介入の形態を示しました。国家安全保障とグローバル資本の自由な移動のせめぎ合いが鮮明になり、今後は法的整備や国際ルールの議論が不可欠です。特に、CFIUSによる審査基準の透明化や、米国内外の合併当事者に対するガイドライン整備が求められるでしょう。


コメント:0 件
まだコメントはありません。