TOEICでまたも不正事件 背景は
TOEICでまたも不正事件 背景は
2025/06/19 (木曜日)
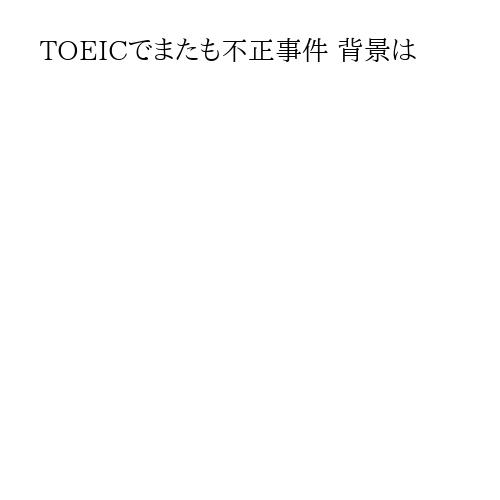
6月上旬、東京都内で行われた英語の国際テスト「TOEIC」で中国籍の受験者10人が警視庁から任意の事情聴取を受けていたことがわかった。5月には同じ「TOEIC」で京都大学大学院に在籍する中国人が替え玉受験をして逮捕されたばかりだ。
毎日新聞の記事によると、今回はそれとは別の「教え役」がいたとみられる。背景にあるのは中国特有の
はじめに:TOEIC試験で中国籍受験者10人を事情聴取──新たな組織的不正疑惑の実態
2025年6月上旬、東京都内で実施された英語コミュニケーション能力を測る国際試験「TOEIC(トーイック)」の会場で、警視庁は中国籍受験者10人を任意の事情聴取しました。受験票の偽造や小型通信機器を用いたカンニングなど、複数の不正手口が疑われており、聞き取りでは「教え役」とみられる人物の関与も浮上しています。5月には京都大学大学院在籍の中国人留学生による“替え玉受験”事件が起きており、今回の摘発は別グループによる組織的不正が横行している可能性を示唆するものです。
1.取り調べを受けた10人の概要
事情聴取を受けた10人はいずれも20歳代とみられ、同一住所を受験申込に登録。会場では小型イヤホン型デバイスや骨伝導ヘッドセット、スマートグラスといった電子機器を用い、外部の「教え役」とリアルタイムで通信しながら解答を作成していた疑いがあります。事情聴取では「高得点が就職・進学に有利だから」「数千円を支払って不正サービスを利用した」と一部が認める一方で、黒幕と目される「教え役」の所在や組織的背景については今後の捜査を待つ段階です:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
2.背景にある“試験代行”ビジネスの実態
日本におけるTOEIC試験は年間約200万人が受験し、企業採用・昇進要件としてスコアが広く活用されています。この高い経済価値を狙い、近年は「試験代行」「不正解答支援」といったサービスが中国本土のSNSや掲示板で盛んに宣伝され、1件あたり数万円から数十万円で提供されています。代行業者は受験会場情報を独自に入手し、グループで標的会場に赴いて組織的に不正を行う手口を確立しています:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
3.京都大学院生逮捕との関係と違い
5月中旬には、京都大学大学院生(中国籍、27歳)が偽造身分証で“替え玉受験”を図ったとして逮捕されました。このケースでは、被疑者自身が別人の顔写真入り受験票を使用し、マイク内蔵マスクで外部指示を受けるなどハイテク手口が注目されましたが、今回の10人聴取事案は「替え玉」ではなく、本人名義で会場にいる複数人が協力してスコアを稼ぐ「集団形式」の不正とみられます。警察は両事件を別線で捜査すると同時に、不正ルートの全容解明を進めています:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
4.TOEIC不正対策の現状と課題
TOEIC運営団体のETSは、写真付き受験票と会場での顔認証確認を導入していますが、監視スタッフの配置や電子機器持ち込みチェックには限界があります。日本語字幕付きの説明用動画や試験監督員向け研修マニュアルで不正対策を強化しているものの、不正業者側の手口の巧妙化が追いつかず、抑止力が十分とは言えません。
5.法的責任と今後の処罰動向
不正行為が認められた場合、受験者は建造物侵入・詐欺罪で起訴されるほか、TOEICスコアの抹消やETSとの契約解除、さらに受験料返還や損害賠償請求の対象となる可能性があります。代行業者は「不正助長罪」として立件される場合もあり、警察当局は今後、業者摘発に向けた情報提供を呼びかけています。
6.国際的なテスト不正の比較
海外でもTOEFLやIELTSなど主要英語試験で不正が相次ぎ、SNSを介した不正スキームが問題となっています。英国では顔認証×AI監視を併用したオンライン試験監督を導入し、日本でもETSが試験場外からのライブ監視システムを試験的に導入予定です。
7.受験者・企業への影響と信頼回復策
今回の不正摘発は、誠実に試験に臨む受験者やTOEICスコアを重視する企業の信用を損なうリスクがあります。運営団体は試験の公正性を確保するため、受験者向け不正防止ガイドラインや「不正行為通報窓口」を設置。企業側にも「試験結果の真正性確認」を求める動きが広がっています。
結論:組織的不正に対抗するための多層的対策を
TOEIC試験をめぐる組織的不正は、日本の人材育成・評価制度の信頼性に直結する重大課題です。警察による摘発だけでなく、運営団体・受験機関・企業が連携して技術的・制度的抑止策を導入し、受験者教育や企業のスコア活用ルールの見直しを進めることで、公平で信頼できるテスト環境を取り戻す必要があります。


コメント:0 件
まだコメントはありません。