特攻兵にヒロポン注射 元軍医後悔
特攻兵にヒロポン注射 元軍医後悔
2025/06/21 (土曜日)

太平洋戦争末期、日本軍は爆弾を積んだ戦闘機で敵の艦船に突撃を試み、多くの若者が犠牲になった。特攻隊員は、ヒロポン(覚醒剤)を打って基地を飛び立った。新潟市の元海軍軍医蒲原宏さん=3月に101歳で死去
はじめに
太平洋戦争末期、日本軍は戦況打開を狙い、特攻作戦を実施し、若いパイロットを爆弾を搭載した戦闘機で敵艦に体当たり攻撃させました。出撃前の極度の緊張と恐怖にさらされる隊員たちに対し、海軍は覚醒剤「ヒロポン」を注射し、精神・肉体を覚醒させることで恐怖を緩和させようと試みました。新潟市に在住した元海軍軍医の蒲原宏氏(享年101)は、基地で約二百名の特攻隊員にヒロポン注射を行い、その記憶を終生自ら語り続けました。本稿では、ヒロポンの開発経緯と戦時利用、蒲原氏の証言、戦後の覚醒剤問題、そして現代への教訓を多角的に解説します。
1.特攻作戦と兵士心理の背景
真珠湾攻撃以降、連合軍の反撃で苦境に立たされた日本軍は、制空権の喪失と資源不足に直面しました。1944年10月、フィリピンや沖縄での激戦が続く中、陸海軍は「一億総玉砕」の精神論を結集し、飛行機を敵艦に突入させる特別攻撃隊(特攻隊)を編成。特攻隊員には「靖国の英霊となる栄誉」が説かれ、多くは志願したとされていますが、実際には上官の命令や集団的圧力で招集された者も少なくありません。出撃前夜、多くの隊員が恐怖と絶望に苛まれ、命令拒否を口にした者には厳罰が予想されたという証言も残ります。
2.ヒロポン(メタンフェタミン)の開発と戦時利用
ヒロポンは1938年に田辺製薬(現・田辺三菱製薬)が合成したメタンフェタミン塩酸塩製剤で、当初は疲労回復や過労対策として一般にも処方されました。戦局が悪化するにつれて、陸軍と海軍は兵士の戦闘力維持と昼夜を問わぬ行動力確保を目的に大量に配給。特攻隊員には出撃前に「精神の昂揚」を目的として注射され、隊員は眼光が鋭くなり、「恐怖感が消えた」との声もあった一方で、激しい動悸や錯乱状態を生じた例もありました。この戦時利用は、製薬会社と軍部の軍需協力の一端を象徴するものです。
3.蒲原宏氏の証言──軍医としての苦悩
蒲原宏氏は新潟県出身の医師で、戦時中は海軍軍医として鹿児島県の串良基地に配属されました。氏の証言によれば、上官から「特攻隊員に注射せよ」と命じられたヒロポンの正体は知らされず、翌朝には隊員たちが整列し、器具を前にして無言で次々と腕を差し出したといいます。氏は「戦後もこの行為が許されることなのか」と自責の念に苛まれ、生涯にわたり当時の記録を封印し続けました。しかし晩年に至り、過酷な戦時の実相を後世に伝えるべきだとして語り出しました。その証言は特攻隊員の精神的・身体的苦痛を伝える貴重な史料です。
4.戦後の覚醒剤乱用と社会問題化
戦後、ヒロポンは闇市や闇医者を通じて大量に流出し、薬物乱用の温床となりました。疲労回復やスタミナ増強を謳う宣伝が横行し、覚醒剤依存症患者は1950年代から急増。1960年には東京だけで依存症患者が数万人に達したとされ、暴力事件や窃盗事件との関連も指摘されました。世論の強い規制要求を受け、1951年に制定された覚醒剤取締法は、所持・製造・輸入・販売を厳罰化し、戦時中の医薬品としての使用も反省材料とされました。
5.法律と治療の歩み:依存から回復へ
覚醒剤取締法施行後も、依存症患者は刑事罰と医療的支援の狭間で苦しみました。1970年代には保健所による依存症治療プログラムが開始され、1980年代には精神科病院での集団療法や認知行動療法が導入。2000年代以降、保護観察や更生保護制度にリハビリテーション要素が加わり、脱法ドラッグの蔓延対策と併せて薬物依存症対策基本法も議論されるようになりました。現在は、医療機関や地域支援団体が協働し、依存者の社会復帰を支援する包括的な体制が整いつつあります。
6.現代への教訓:命の尊厳と医療倫理
特攻隊員へのヒロポン投与は、極限状況下で医療者が上官の命令と医療倫理の間で揺れ動いた歴史的事例です。医師の良心を超える軍命令が、いかに個人の尊厳を奪うかを示しています。一方で、戦後の覚醒剤問題は、一度社会に流入した薬物が如何に長期にわたり人々の健康と社会秩序を蝕むかを浮き彫りにしました。現代社会では、新しい医薬品や研究開発の段階で倫理審査を強化し、薬物依存の早期発見・支援体制を更に充実させることが求められています。
結論
太平洋戦争末期のヒロポン投与と戦後の覚醒剤乱用の歴史は、人命尊重と医療倫理の重要性を痛感させる教訓です。蒲原宏氏の証言は戦争の悲劇を後世に伝える貴重な記録であり、私たちはその痛ましい歴史を踏まえ、薬物による人権侵害を二度と繰り返さないために、医療・法制度・社会支援を総動員した取組みを続けなければなりません。
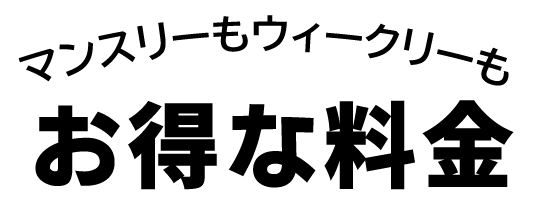

コメント:0 件
まだコメントはありません。