相模原で窃盗続く 防カメに不審者
相模原で窃盗続く 防カメに不審者
2025/06/06 (金曜日)
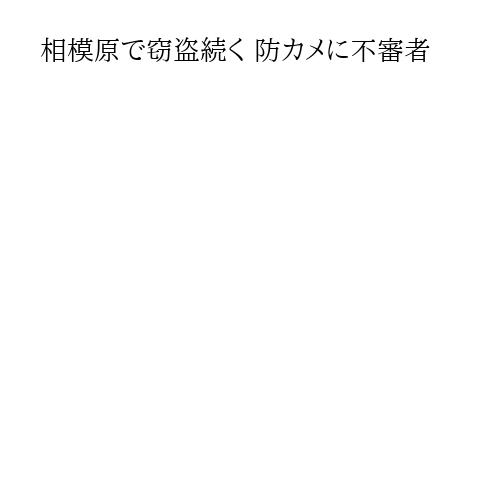
【独自】防犯カメラには深夜にうろつく複数の不審な人物 神奈川県相模原市で窃盗被害相次ぐ 被害者「起きたときに部屋が荒らされてた」 警察は窃盗事件として捜査
神奈川県相模原市の住宅で、現金や貴金属が盗まれる窃盗事件が相次ぎました。現場付近の防犯カメラには、複数の不審な人物が写っていました。
住宅街を歩く不審な人物。きのう午前1時ごろに撮影された防犯カメラの映像です。この映像が撮影されたあと、周辺では窃盗被害が相次いで明らかになりました。
警察によりますと、きのう午前4時前、相模原市緑区の住宅で「引き出しが開けられている」と110番通報がありました。その後も複数の住宅から通報が相次ぎ、窓ガラスが割られるなどして、現金や貴金属が盗まれる被害が8件確認されているということです。
被害にあった住人
「起きたときに部屋が荒らされていた。引き出しは全部引っ張られてあった。(財布の)チャックを開けたら、お金がなくって」
被害は半径数百メートル以内で相次いでいることから、警察は連続窃盗事件とみて捜査するとともに、防犯カメラに写った人物が事件に関与した可能性もあるとみて調べています。
要約
2025年6月6日未明、神奈川県相模原市緑区の住宅街で相次いだ窃盗事件について、防犯カメラに映った複数の不審人物が捜査の焦点となっています。午前1時ごろに防犯カメラが不審人物を捉えていた直後、午前4時前から同区内の半径数百メートル以内の住宅で、窓ガラスを割られたり引き出しが荒らされたりして現金や貴金属が盗まれる被害が8件確認されました。被害者の証言では、「部屋が荒らされて引き出しがすべて引き出されていた」「財布の中の現金がなくなっていた」と語っています。警察はこれらを連続窃盗事件とみなし、防犯カメラに映った複数の人物が関与している可能性を捜査中です。
1. 窃盗事件の詳細と被害状況
報道によると、2025年6月5日の夜から6日の未明にかけて、相模原市緑区の住宅街で少なくとも8件の窃盗被害が発生しました。いずれも住宅の窓ガラスを割るなどの手口で侵入し、室内で引き出しや引き戸の施錠をこじ開け、現金や指輪、ネックレスなどの貴金属を持ち去っています。被害に遭った住人の多くは深夜に寝静まっていたため、気づくのは翌朝であり、侵入から逃走までの時間を正確に把握できない状況でした。
防犯カメラの映像には、深夜1時ごろに複数の男女とみられる不審人物が住宅街の路地を歩く様子が映っており、検挙に向けた重要な手がかりと期待されています。警察は「同一グループによる連続窃盗」とみて、近隣住民への聞き込み捜査や追加の防犯カメラ映像の解析を行っています。現場は道路が入り組んだ住宅街で、夜間は街灯が少ないエリアもあり、不審者が目立ちにくい構造です。
2. 日本における住宅侵入窃盗(空き巣・忍び込み)の推移
日本では高度経済成長期以降、都市部の住宅地が拡大し、人口の増加とともに空き巣や忍び込みといった住宅侵入窃盗が社会問題となってきました。1970年代から80年代にかけては、鍵穴を壊して侵入する「サムターン回し」や窓を割っての侵入が目立ちましたが、1990年代以降は防犯意識の高まりとともに手口も高度化し、電子錠や防犯センサーをかわす巧妙な手口が増加しました。
近年は地域によって発生件数に差がありますが、全国的には年間約3万~4万件程度の住宅侵入窃盗が発生しています。2010年代後半からは防犯カメラやホームセキュリティの普及で一時的に減少傾向となりましたが、2020年のコロナ禍以降、在宅時間が増えたものの夜間外出の減少により空き巣犯のターゲットも変化し、近所の留守時間を狙う手口が多く報告されています。
3. 相模原市の地域特性と犯罪状況
相模原市は神奈川県の北部に位置し、緑区・中央区・南区の3区に分かれています。緑区は多摩丘陵の緑豊かなエリアが広がり、戸建て住宅が多く新興住宅地も点在します。隣接する東京都心部へは鉄道や高速道路でアクセスが容易なため、ベッドタウンとしての側面も持ち合わせています。一方で細い路地や夜間の人通りの少ない場所が多く、防犯面での脆弱性も指摘されてきました。
過去5年間の相模原市における住宅侵入窃盗件数は、年間約300~400件前後で推移しています。特に緑区や中央区の一部では、住宅地の開発が進む一方で古い構造の住宅が残り、セキュリティが不十分な物件も多いため、狙われやすい傾向にあります。地域住民の自主防犯活動も活発ですが、近年は空き家を狙った被害も増加しており、市内全域での防犯対策が急務となっています。
4. 侵入窃盗の歴史的背景と対策の変遷
日本における住居侵入窃盗の歴史は古く、江戸時代には「忍込み」と呼ばれる同様の手口がすでに報告されていました。明治以降、近代国家の法整備とともに窃盗罪が確立し、刑罰が強化される一方で、都市部のスラム化や貧困問題から都市犯罪が増加しました。戦後、高度経済成長期には都市化が急速に進み、住宅地が拡大する中で空き巣被害が社会問題化。これを受けて、1980年代には警視庁や地方警察が「住宅防犯モデル地区」を設定し、自治会やPTAと連携して見守り活動を強化しました。
1990年代後半から2000年代初頭にかけては、窃盗犯の手口が多様化し、電子錠のピッキングや車両の窓ガラスを壊して工具を使う手口などが見られるようになりました。これに対抗して、各地で「防犯カメラの設置補助」「住宅用防犯センサー設置の支援」「夜間パトロール強化」などが実施され、安全灯や防犯灯の増設、子ども見守り隊の結成など地域ぐるみの対策が進展しました。
2010年代以降はICタグやスマートフォンを活用したIoT型防犯システムが普及し、遠隔監視や警告音の発生、侵入時にはスマホに通知が届くなど高度化が進んでいます。一方で、この技術格差から対応が遅れる地域や世代も存在し、依然として住宅地での侵入窃盗が絶えない課題を抱えています。
5. 防犯カメラの役割と限界
今回の相模原市緑区での窃盗事件では、防犯カメラ映像が捜査の重要な手がかりとなっています。夜間に撮影された映像から、不審な人物が住宅街を徘徊する様子が確認され、複数の家で被害が連続していることと合わせ、同一グループによる犯行とみられています。最近はスマートフォンと連動するクラウド型の防犯カメラが普及し、リアルタイムで映像を共有できるため、通報後に迅速な対応が行いやすくなっています。
しかし、防犯カメラには死角や画質の問題があり、犯人の特定や顔認証には限界があります。また、カメラの設置場所が少ないと撮影範囲が限定され、逃走ルートが記録できない事例も多く見られます。さらにはカメラ自体を破壊されたり、夜間に映像が不鮮明になるため、設置後も警察や地域住民が連携してパトロールを強化する必要があります。
さらに、プライバシー保護の観点から、公共スペースと私有地におけるカメラの設置には法的制約があり、不審者が映り込んだ映像を無断公開できない場合もあります。したがって、防犯カメラはあくまで抑止・証拠収集の一要素として位置づけられ、地域全体での見守り体制が依然として重要となります。
6. 地域防犯活動と住民の役割
地域社会における防犯活動は、自治会や町内会が中心となって、夜間パトロールや見守り活動を行う「防犯パトロール隊」の結成が基本です。相模原市でも、地域防災と連携した防犯訓練が定期的に開催され、町内会長や高齢者クラブ、子ども会など多様な住民が参加しています。夜間パトロールではライトカーや自転車で通りを巡回し、不審者の存在を警察に通報する仕組みが整備されています。
また、防犯メールや防犯アプリが普及し、自治体からの警察情報がリアルタイムで配信されるようになりました。被害情報や不審者目撃情報が共有されることで、迅速な注意喚起が可能となり、被害の連鎖を防ぐ効果が期待されています。加えて、地域の高齢者世帯や一人暮らし世帯に対しては、自治会役員や民生委員・児童委員による「見守り訪問」が行われ、孤立しがちな家庭の異変を早期に察知する取り組みも進んでいます。
しかし、地域防犯活動の継続には住民の協力とリソースが不可欠です。高齢化や過疎化が進む地域では人手が不足し、防犯パトロールの参加率が低下するケースもあります。そこで相模原市では、大学生ボランティアや企業のCSR(企業の社会的責任)活動を活用し、人員と資金を補完する取り組みを模索しています。また、自治体が防犯カメラ設置に対する補助金を出すことで、個人でも手軽にカメラを導入できるよう支援を行っています。
7. 防犯機器やIoT技術の導入事例
近年、防犯技術の進化により、従来の固定カメラに加えて、モバイル型ドローンやAI解析を活用した顔認識システムなどが登場しています。相模原市内でも一部の自治会ではAI防犯カメラを導入し、深夜の路上で人の動きを自動検知すると管理者のスマートフォンに通報が届く仕組みが実証実験されています。これにより、人手による監視が難しい夜間でも早期発見が可能となり、警察への通報が速やかに行えるメリットがあります。
また、IoTセンサーを活用した窓やドアの開閉検知システムも普及しています。センサーが作動すると住人のスマホに通知が届き、遠隔地からも異常に気づくことができます。さらに、スマートロックや指紋認証を搭載した玄関錠が増え、鍵穴の破壊やピッキングを困難にしています。しかし、これらの機器導入には初期費用とランニングコストがかかるため、防犯意識や経済的余裕のある世帯が先行しているのが現状です。
相模原市でも、低所得世帯や高齢者世帯に対して防犯機器導入の補助金を出す制度が検討されており、全世帯への普及を目指した取り組みが進んでいます。特に、昼間は仕事や学校で留守にしがちな家庭には、遠隔監視機能付きのカメラ導入が有効とされています。
8. 被害者・住民の心理と社会的影響
連続窃盗事件が発生すると、被害者だけでなく近隣住民にも大きな不安が広がります。午前4時前に侵入されるような犯罪は、住民が就寝中や薄暗い時間帯に襲われる恐怖をあおり、不眠やストレスの増加を引き起こします。警察への通報が相次ぐと、地域全体で「自分の家も狙われるかもしれない」という不安感が高まり、外出自粛や家の入口に鍵を複数かけるなど過剰防備を強いられることがあります。
また、防犯意識が高まることで、コミュニティの結束が強化される一方、疑心暗鬼やイライラが募りやすくなり、近所同士のぎくしゃくした関係を生む場合もあります。相模原市では被害住民へのメンタルヘルスケアや、コミュニティ支援センターによるカウンセリングなども用意されていますが、深夜に襲われた恐怖は簡単には拭えず、住環境への信頼回復には時間を要します。
9. 警察捜査と今後の見通し
警察は現場周辺の防犯カメラ映像を解析し、映像に写った複数の不審人物の身元特定を急いでいます。また、被害が相次いだ区域の住民から聞き込みを行い、細かな犯行パターンや逃走経路を割り出そうとしています。現場では、踏み込んだ跡や足跡などの物的証拠も収集されており、指紋や足跡のDNA鑑定が進められています。
捜査関係者によれば、被害は半径数百メートル以内に集中しているため、同じグループが複数の家を回って犯行している可能性が高いとのことです。警察は「連続窃盗事件」という見立てのもと、逮捕に向けて警戒体制を強化し、地域の防犯パトロールも支援する方針です。今後、近隣の防犯カメラ映像や目撃情報を集約し、容疑者の移動経路や潜伏先特定を進めることで、早期検挙を目指します。
相模原署は被害者に対して、「現金や貴金属は目立たない場所に保管し、外出時には必ず玄関や窓の施錠を行うこと」「防犯カメラの存在を周知して、空き巣が近づきにくい環境を作ること」などを呼びかけています。また、今後は区域内の夜間パトロールを強化し、不審者情報を警察・自治会や近隣住民と共有する体制を構築していく予定です。
10. 住宅侵入窃盗を防ぐためのポイント
今回の相模原市緑区での事件を踏まえ、住宅侵入窃盗を防ぐための具体的な対策を以下に挙げます。
- 玄関・窓の二重施錠
玄関はディンプルキーや補助錠を追加し、複製が難しい鍵を使用する。窓ガラスには防犯フィルムを貼り、割られても飛散しにくい構造にする。 - 防犯カメラとセンサーライトの設置
誘導ライト型のセンサーライトや録画機能付きカメラを設置し、不審者が近づいた際に自動的に撮影・警告音が出る機能を活用する。スマホ連携で遠隔確認ができると安心感が増す。 - 不在時の見守り対策
郵便物の溜まりや庭先の落ち葉など、不在を示す兆候がないように配慮する。近所の人に「外出中である」ことを伝えず、見かけないように偽装する。 - 地域の見守りネットワーク活用
自治会や町内会の防犯パトロールに参加し、近隣住民と防犯情報を共有する。自治体の防犯アプリに登録し、不審者情報を受信する。 - 緊急連絡先の周知
怪しい音や不審人物を見かけた際には、すぐに警察(110番)や自治体の防犯連絡網に通報する体制を整える。夜間の緊急連絡先を家族や近所と共有しておく。 - 貴重品の保管場所を分散する
現金や貴金属は複数の場所に分散して保管し、一か所だけを狙われても大きな被害を防ぐ。耐火金庫や隠し金庫を利用するのも有効。 - 防犯意識の継続的な向上
定期的に防犯講習や自治体の啓発イベントに参加し、新しい手口や対策方法を学ぶ。家族全員で防犯意識を共有する。
これらの対策を実践することで、窃盗犯が侵入しづらい環境をつくり、被害を未然に防ぐことができます。また、地域全体で情報を共有し、協力体制を築くことが、防犯力を高める鍵となります。
11. まとめ
神奈川県相模原市緑区で発生した住宅侵入窃盗事件は、防犯カメラに映った複数の不審人物が逃走経路を模索しながら複数の家を次々と襲っている可能性が高く、警察は連続窃盗事件として捜査を進めています。日本全体で住宅侵入窃盗は長年にわたり問題視されてきましたが、今回の事件が示すように、夜間に複数の窃盗犯が一帯を巡回しながら犯行を繰り返す手口は依然として後を絶ちません。
住民は玄関や窓の二重施錠、センサーライト・防犯カメラの設置、地域の見守り活動など、自衛手段を強化する必要があります。さらに、自治体や警察は情報共有を進め、夜間パトロールや防犯講習を継続的に実施することで、犯罪の抑止につなげることが求められます。住宅街の治安は住民の安心・安全に直結するため、一人ひとりが防犯意識を高めつつ、地域全体で協力し合う体制を築いていくことが重要です。


コメント:0 件
まだコメントはありません。