川で溺れ死亡「救助死」なぜ続く
川で溺れ死亡「救助死」なぜ続く
2025/06/12 (木曜日)
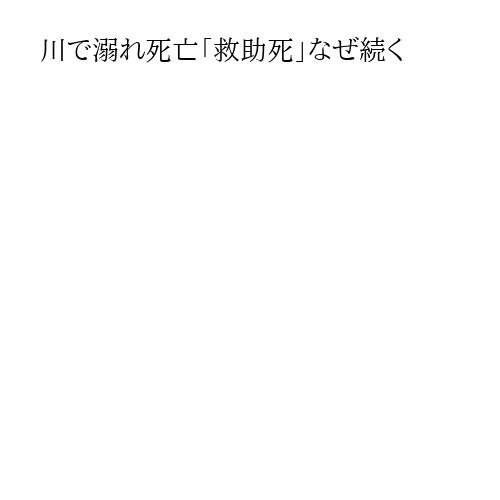
斎藤秀俊水難学者/工学者 水難学会理事/長岡技術科学大学大学院教授6/12(木) 7:44(写真:イメージマート) 昨日、岡山市で2人が亡くなる水難事故が発生しました。現場は市内を流れる旭川で、落差工と呼ばれる河川構造物の下流と思われます。まず溺れたのは中学2年生の13歳の女子生徒2人で、あとから川に入った男性(69)も溺れました。旭川では過去にも小学生が溺れています。
溺れている人を助けよう
事故の概要
2025年6月11日午後4時15分ごろ、岡山市北区中井町の旭川で、河川工事用の落差工(小規模ダム)付近の浅瀬で遊んでいた中学2年生の女子生徒(13)2人が流されました。通りかかった69歳の男性が1人を救助後、もう1人を助けようと川に入りましたが、2人とも数百メートル下流で水死体となって発見されました。搬送先の病院で死亡が確認され、同市中区の西原日菜乃さん(13)と南区の坂本秀雄さん(69)でした :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
落差工(しゅうさこう)の危険性
落差工は河川の流水エネルギーを分散・調整する構造物ですが、その下流には急深部や渦巻きが生じやすく、溺死事故の多発地点となっています。京都府の報告書によれば、落差工下流にできるくぼみは深さ2mに及び、幅10m程度にわたって危険が広がるため、遊泳・救助時のリスクは格段に高まるとされています :contentReference[oaicite:1]{index=1}。さらに、河川技術研究フォーラムの分析では、水際や落差部での転倒・流出が水難全体の約6割を占め、深みや流れの変化を予測しづらいことが事故原因と指摘されています :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
川の水理構造と流れの危険
流速がわずかに速いだけでも流体力学的には力が急増し、児童の体重では抵抗できません。FC2の研究レポートによると、流速が2倍になると水圧は4倍に増加し、浅瀬であっても川底の急深部や倒木により足場を一瞬で失う危険があると警告されています :contentReference[oaicite:3]{index=3}。加えて、増水時には通常の境界が見えなくなり、流心域と安全域の区別が困難になります。
過去の同種水難事故の傾向
旭川では2020年にも小学生の水難事故が報告され、堤防や水辺での遊びを禁止する看板設置後も事故が後を絶ちません。全国的には河川・水際での事故が全体の約60%を占め、橋脚や護岸での飛び込み事故も多発しています。特に落差工では残念ながら死亡事故を含む事例が何度も発生しており、河川管理者は安全対策・注意喚起を強化すべきとの指摘が繰り返されています :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
溺水者を見つけた際の対応
岐阜県公式Q&Aでは、溺れている人を助ける際は「公的ライフジャケットを着用」「無理に飛び込まない」「物を投げ入れて距離を保つ」などの方法が推奨されています。川での直接救助は救助者自身がさらに危険に晒されるため、ロープや浮き具を使った「陸上救助」を第一選択とし、緊急時は速やかに119番通報することが求められます :contentReference[oaicite:5]{index=5}。
長岡技術科学大学・斎藤秀俊教授の見解
水難学会理事で長岡技術科学大学大学院教授の斎藤秀俊氏は、「落差工周辺は水理構造が極めて複雑で、救助者が足場を失って同じように引き込まれる二次被害が多い。河川管理者は発生予測情報をリアルタイムで周知し、河川敷利用の制限や監視カメラ設置などの多重防護を導入すべきだ」と指摘します。
全国の河川安全対策の現状
多くの自治体は危険箇所に注意喚起看板やロープフェンスを設置していますが、「注意がない場所は安全」と誤解されがちです。専門家は「ライフジャケット着用と、水辺への立ち入り自粛を徹底し、地域住民や学校での水難教育を強化することが最も効果的」と訴えています。
学校・家庭への啓発と再発防止
教育現場では夏季の水難防止授業で「河川の危険性」「救助の仕方」「緊急連絡方法」を学ぶカリキュラムが推奨されています。家庭でも河川遊びの危険指導を徹底し、子どもだけでの水辺利用を厳禁とするルールづくりが重要です。
まとめ
旭川の落差工付近での痛ましい水難事故は、河川構造物に起因する深部・流れの危険、救助時の二次被害リスクなど、複合的要因が絡むものです。河川管理者による設備対策、地域住民への周知徹底、学校家庭での安全教育、救助時の安全確保手順の普及が一体となって初めて再発を防止できます。斎藤教授が指摘するように、「見逃さない警戒態勢」と「救助網」の強化が喫緊の課題です。


コメント:0 件
まだコメントはありません。