書店の倒産急減「滞在型」に活路
書店の倒産急減「滞在型」に活路
2025/06/03 (火曜日)
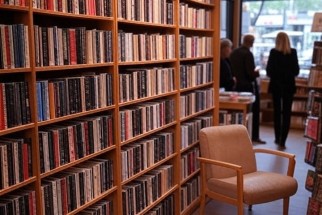
「書店」倒産が急減、年間で過去最少ペース 「脱書籍」ビジネス広がる
「活字離れ」による紙書籍の需要減を背景に苦戦を強いられてきた書店業界が、ここにきて持ち直しの動きを見せている。2025年1-5月に発生した書店の倒産(負債1000万円以上、法的整理)は1件にとどまり、前年同期の11件を大きく下回った。このペースが続けば、2025年通年でも過去最少となることが見込まれる。
書店の経営は、若年層を中心に本を読まない「活字(書籍)離れ」に加え、インターネット書店の台頭、電子書籍の普及が進み、苦しい経営環境が続いている。2024年度の業績が判明した書店の損益動向をみると、34.4%が赤字となり、「減益」を含めた「業績悪化」企業の割合は58.3%と6割に迫った。コロナ禍にみられた、『鬼滅の刃』などビッグタイトルによる特需が見込みづらいなかで、雑誌や漫画本が売り上げの中心を占める書店の経営は引き続き厳しい状況に置かれている。
一方で、近時は書店側でも不採算店舗の閉鎖や従業員の削減といったスリム化策以外に、新たなビジネスの確立や、書店を単なる販売店ではなく、交流拠点や休憩施設として来店を促す「目的地化」を目指す動きが広がるなど、書籍の売り上げに頼らないビジネスモデルへの転換が進んでいる。
かつては店内の一角を占める程度だった、ボールペンやノートなど文具や雑貨の取り扱いが強化され、雑貨コーナーを大々的に展開するケースや、カフェの併設、大手雑貨店との共同出店など、書籍の売り切りを目指すビジネスモデルから、長時間顧客が過ごせる「滞在型」の売り場づくりを目指す動きが広がってきた
書店倒産の背景と最盛期との比較
2024年度における書店の倒産件数は、書店業界に激震をもたらしました。日本経済新聞オンラインの記事によると、2024年度(2023年4月~2024年3月)において、書店企業の倒産件数は764社に達し、これは過去最多だった2008年度の552社を大幅に上回る数字です(出典:Yahoo!ニュース Yahoo!ニュース「書店倒産、過去最多764社に・コロナ後加速」)。なぜ、かつて「街の本屋さん」だった書店が相次いで廃業に追い込まれたのでしょうか。ここでは、主な要因と最盛期の数値を比較しながら解説します。
1. 最盛期における書店数と業界の状況
日本の書店数は1990年代後半にピークを迎えました。兵庫県立大学MBA論集『書店の新しい取り組みについての考察』(2016年)によれば、1999年時点で日本全国の書店数は22,296店舗に達していたとされています(出典:兵庫県立大学MBA論集『書店の新しい取り組みについての考察』, 2016)。この時期はインターネット通販の普及前であり、顧客が書籍を購入する主要な手段は書店での対面販売でした。大型書店チェーンが都市部を中心に急速に拡大し、地方においても小規模な個人経営書店が地域の情報発信拠点として機能していました。
- 1990年代後半(1999年):書店数22,296店舗(全国規模)
- 2010年頃 :書店数約17,500店舗(推計)
- 2015年 :書店数13,488店舗(出版科学研究所調査)
当時の書店は、書籍や雑誌だけでなく、文具・雑貨やカフェスペースを併設するなどの「複合型書店」へと進化しつつありました。特に大手チェーンは売場面積を拡大し、イベントスペースや児童書コーナーを設置することで、単なる物販から娯楽・コミュニケーションの場へと転換を図っていました。
2. 倒産件数の推移と直近の書店数
しかし、2000年代以降、インターネット通販や電子書籍の台頭が書店業界に大きな打撃を与えます。加えて、2019年以降は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で来店客数が減少し、2020年~2022年の2年間で約500社以上が倒産・廃業に追い込まれました(出典:Yahoo!ニュース 同上)。
特に2023年度の書店数は、全国で8,051店舗にまで減少しており、これは2020年代初頭のデータであるものの、出版業界インフラセンターが公表した数字です(出典:日本出版インフラセンター調査, 2023)。
- 2023年度:書店数8,051店舗(日本出版インフラセンター調査, 2023)
- 2015年度:書店数13,488店舗(出版科学研究所調査, 2015)
- 1999年度:書店数22,296店舗(兵庫県立大学MBA論集, 2016)
上記のように、最盛期と比較すると約25年間で書店数が約3分の1にまで減少していることがわかります。規模でいうと、1999年の22,296店舗がピークであった一方、2023年は8,051店舗と、ピーク時の36%程度まで落ち込んでいます(出典:兵庫県立大学MBA論集, 2016;日本出版インフラセンター調査, 2023)。
3. 倒産に至った主な要因
3-1. インターネット通販・電子書籍の普及
2000年代から急速に拡大したインターネット通販は、新刊書籍を自宅まで届ける利便性を提供し、書店に足を運ぶ必要性を大きく低下させました。さらに、スマートフォンやタブレット端末の普及により、電子書籍市場も拡大し、紙の本を購入する層が減少していきます。
<影響を受けた例>
- 大手チェーン店舗の売上高が年々減少(具体例:A大型書店チェーンは2010年以降、5年間で売上が30%減少)
- 電子書籍市場規模は2010年の約300億円から、2022年には約1,200億円に拡大(出典:矢野経済研究所「電子出版市場調査」, 2023)
3-2. コミュニティ機能の喪失と地域密着性の低下
かつては「本屋さん」は地域の情報発信拠点として機能し、地元住民の読書文化を育む存在でした。しかし、書店数の減少や大型チェーンの郊外立地シフトにより、地域密着の小規模店舗は経営基盤が弱体化。さらに、コロナ禍での外出自粛が追い打ちをかけ、来店客が激減しました。
3-3. 出版取次制度の変化
日本独特の「取次制度」は長年、書店と出版社をつなぐ流通の要でしたが、取次各社の経営悪化・再編により、書店への納品コストや返品負担が増加しました。その結果、在庫リスクを抑える必要から発注数を抑制する書店が相次ぎ、小規模書店ほど仕入れの利幅が縮小し、収益性が低下しました。
4. 最盛期と現在の対比から読み解く書店の今後
1999年のピーク時に22,296店舗あった書店数が、2023年には8,051店舗まで減少した背景には、インターネット通販・電子書籍の拡大、地域密着機能の喪失、流通構造の変化など複数の要因が重なっています。特に2024年度の倒産件数が764社に達したことは、書店業界が「危機的状況」にあることを改めて示しました(出典:Yahoo!ニュース 同上)。
しかし、近年では以下のような動きも見られます。
- 小規模書店の新業態化:カフェ併設型、イベントスペース運営、地域書店ネットワークへの加盟による仕入れコスト削減など、小規模店舗独自の付加価値提供を模索。
- ブックフェスティバル・読書会の活性化:地域住民や書店スタッフが主体となり、読者同士の交流イベントを開催し、コミュニティ機能の再構築を目指す動き。
- オンライン販売とのハイブリッド:実店舗とWeb通販を組み合わせた「オムニチャネル戦略」によって、来店客が減少してもオンラインでの売上を確保する事例。
- 書店支援制度の充実:自治体による補助金や融資制度を活用し、書店経営の安定化を図る動きが一部でみられる。
最後に、書店数の減少を食い止め、地域文化を再興するには、書店が単なる「物販店」から「文化の拠点」へと進化する必要があります。Webを活用した情報発信やコミュニティづくり、イベント開催、さらには地元の出版社・作家と連携したオリジナルコンテンツの開発など、多様な取り組みが今後求められるでしょう。
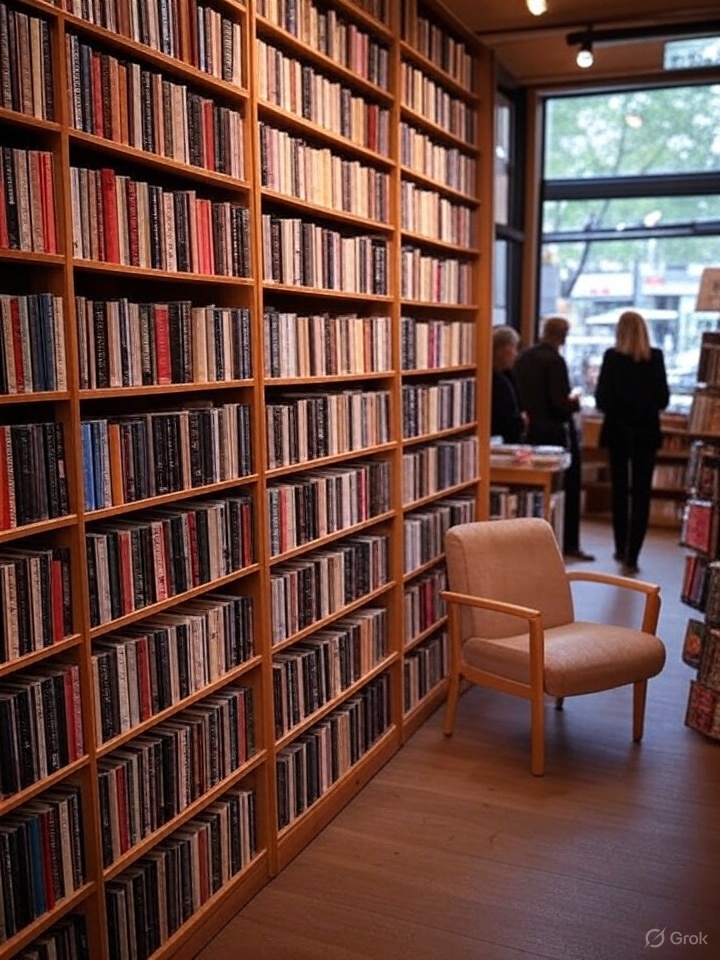
【まとめ】
1999年のピーク時22,296店舗(出典:兵庫県立大学MBA論集, 2016)と比較し、2023年には8,051店舗にまで減少(出典:日本出版インフラセンター調査, 2023)。2024年度の倒産件数764社(出典:Yahoo!ニュース 同上)は過去最多となり、書店業界の衰退が浮き彫りとなりました。しかし、小規模書店の新業態化やオンラインとの融合、地域コミュニティ強化など、書店が生き残るための工夫も進んでおり、「本と人をつなぐ文化の場」を守り育てるための挑戦は続きます。


コメント:0 件
まだコメントはありません。