「死亡した警備員は国策の犠牲者」 警備員死亡の辺野古ダンプ事故1年で追悼・抗議集会
「死亡した警備員は国策の犠牲者」 警備員死亡の辺野古ダンプ事故1年で追悼・抗議集会
2025/06/28 (土曜日)
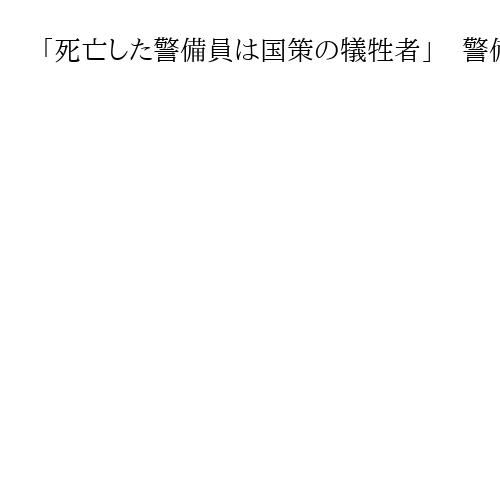
主催者側によると、集会には約100人が参加。参加者は献花し、1分間の黙禱をささげた。男性警備員とともにダンプカーに巻き込まれ重傷を負った女性側の弁護士が事故後の経過を説明し、「事故の責任は(防衛省)沖縄防衛局にある」との見解を示した。
女性は集会の参加者に宛てたメッセージで「二度と戦争をさせないために、一日も早く元気になって皆さんとともに現場に戻って頑張っていきたい」とし、「事故は防衛局による、
辺野古ダンプ事故1年──追悼・抗議集会に込められた想いと責任追及の動き
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設先として建設が進む名護市辺野古の「安和桟橋前」道路で、昨年6月28日にダンプカーに巻き込まれて警備員が死亡し、抗議行動中の70代女性も重傷を負った事故からちょうど1年を迎えた。2025年6月28日、市民団体が事故現場で「追悼・抗議集会」を開き、約100人の参加者が献花と1分間の黙祷を捧げた。
集会の経過と当事者の声
- 主催者の呼びかけで集まった参加者は、事故で亡くなった男性警備員の冥福を祈り、遺族や被害者支援を訴える横断幕を掲げた。
- 集会には重傷を負った女性側の弁護士も出席し、「事故の責任は沖縄防衛局にある」との見解を示し、工事の安全管理体制に対する厳しい追及を行った。
- 松田美智子さん(仮名)は、集会参加者に向けて直筆メッセージを寄せ、「二度と戦争をさせないために、一日も早く元気になって現場に戻りたい」と意欲を語った。
弁護士は、事故後の経過について「規制区域での工事車両運行ルールが守られていなかった」と指摘し、防衛省沖縄防衛局に対する行政責任の追及を強調した。
事故原因の検証──「2台出し」の危険性
事故を引き起こした主原因として注目されるのが、工事車両を2台並列で走らせるいわゆる「2台出し」の手法だ。現場では土砂運搬用ダンプカーが交互に進入する際、後続車両の視界確保が不十分な状態で先行車両との隙間を詰めて走行していたとされる。
これにより、道路を横断しようとした女性がダンプの死角に入り込み、先行車両から後続車両へ弾かれる形で巻き込まれた。工事関係者の証言によれば、「作業効率優先で安全確認が疎かになっていた」との内部告発もある。
辺野古移設を巡る経緯と地域の葛藤
辺野古新基地建設は、2009年に政府が調査計画を示し、2014年に埋め立て承認を得た後も、知事による埋め立て違反訴訟や住民土地取引訴訟が継続。反対派の抗議行動は海上だけでなく陸上にも及び、ゲート前での座り込みやデモが日常化している。
抗議現場の警備を担う民間警備員は、機動隊員と共に車両誘導や抗議者との距離確保を任されるが、十分な安全対策や研修が行われているとは言い難い。今回の事故は、国策として推進される基地建設に伴う「公的リスク」を浮き彫りにした事例である。
他地域での類似事例との比較
| 地域 | 事案 | 主要問題点 |
|---|---|---|
| 高江(2016年) | ヘリパッド反対デモ中の機動隊負傷事故 | 暴力衝突、警備体制の不備 |
| 辺野古海上(2018年) | 抗議船と作業船接触事故 | 海上安全確保策の欠如 |
| 辺野古陸上(2024年) | 今回のダンプ事故 | 車両管理と視界確保不足 |
いずれも、国・県・市の連携や警備規準の策定遅れが共通の課題となっている。
法的責任と行政対応の現状
警視庁は事故発生後、業務上過失致傷の疑いで調査を進めたが、2024年末には不起訴処分とした。一方、女性側は民事裁判で工事差止めや損害賠償を求める訴訟を継続中で、2025年秋の第一審判決が注目される。
沖縄防衛局は、「安全確認手順は遵守されていた」と主張しつつも、集会を契機に現場の安全対策強化を表明。今後、作業手順の見直しや警備員研修の充実が求められる。
まとめ
辺野古ダンプ事故から1年を経て行われた追悼・抗議集会は、亡くなった警備員の冥福を祈ると同時に、同様の悲劇を繰り返さないための安全管理体制の抜本的見直しを訴える場となった。参加者や被害者側弁護士が「事故の責任は沖縄防衛局にある」と明言したように、国策を背景とする辺野古移設に伴うリスク管理と責任の所在が改めて問われている。工事効率を優先するあまり安全確認が軽視される状況を是正するには、行政が明確なガイドラインを制定し、警備員・警察・防衛局が一体となった研修・監督体制を構築する必要がある。今後の民事訴訟や行政対応、そして地域住民との協議の行方が、辺野古問題の解決プロセスに大きな影響を与えるだろう。二度と犠牲を出さないために、安全を最優先とした工事運営と公的責任の明確化を強く求めたい


コメント:0 件
まだコメントはありません。