川崎市、川崎駅東口駅前広場の路上ライブ、事前登録制を試行実施 8月1日から
川崎市、川崎駅東口駅前広場の路上ライブ、事前登録制を試行実施 8月1日から
2025/07/02 (水曜日)
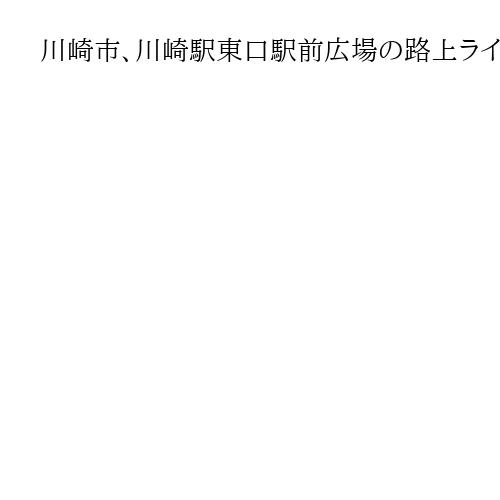
市市民文化振興室によると、昨年11月下旬から12月上旬にかけて実施した調査では、同広場で1週間当たり約70組が演奏した。令和4年ごろから活発化し、大音量を出す行為や通行の妨げになる行為などの苦情が県警や市に寄せられているという。
これを受け、同室では「路上演奏を文化として守っていくためには一定のルールが必要」として、登録制の試行実施に踏み切った。
運用ガイドラインなどによると、演奏者は事前に「
路上演奏登録制試行──公共空間と音楽文化の調和をめざす取り組み
2025年7月2日、●市市民文化振興室は、路上演奏の苦情増加を受け、市内中心部の公共広場における演奏活動を「登録制」によって一定ルールのもとで運用する試行を開始すると発表した。昨年11月下旬から12月上旬に実施した調査では、同広場で1週間当たり約70組が演奏し、通行の妨げや大音量への苦情が県警や市役所に寄せられていたことが背景にある(出典:産経新聞2025年7月2日)。
1. 調査結果:演奏頻度と苦情の実態
市の調査によれば、令和4年ごろから路上演奏が活発化し、特に週末にはギターやベース、PA機器を使用したバンド演奏が増加。幅広い年代の演奏者が集まる一方で、通行人から「狭い歩道で立ち止まり過ぎて危ない」「深夜の演奏で近隣から騒音苦情が絶えない」といった声が連日寄せられていた。
2. 路上演奏文化の歴史と意義
日本におけるストリートミュージックは、1970年代のフォーク・ニューウェーブ世代が原点とされる。その後、1990年代にはヒップホップやジャズといった多彩なジャンルが路上に広がり、都市空間を舞台にした表現活動として定着。観光地や商店街、駅前広場で市民や観光客が気軽に生演奏を楽しめる文化的資産となっている。
3. 他都市の登録制・許可制事例
- 川崎市:川崎駅東口駅前広場で2025年8月から「ストリートミュージックパス」登録制を試行。登録者には演奏枠・時間帯を指定し、ガイドライン順守を義務付け(出典:時事通信2025年7月1日)。
- 札幌市:大通公園周辺で一定の音量以下に抑制する「音響基準」を設け、申請者に対して事前講習を実施。
- 大阪市:道頓堀や心斎橋筋で公認ストリートパフォーマンスエリアを設定し、安全管理や通行確保を条例で明文化。
4. 法的枠組みとガイドラインの内容
路上演奏は道路交通法上「道路使用」に該当し、無許可で行うと通行妨害や騒音規制条例違反となる可能性がある。今回の試行では、以下のポイントを盛り込んだ運用ガイドラインを策定した:
- 演奏時間帯:午前10時~午後8時
- 演奏エリア:広場内の指定ゾーン(歩行動線から1.5m以上離隔)
- 使用機材:スピーカー出力は70dB以下に制限
- 登録・許可:演奏者は事前にオンライン登録し、登録証を携帯
- 苦情対応:苦情発生時は速やかに演奏を中断し、翌日の演奏申請時に報告義務
5. 試行の目的と評価指標
試行期間中(令和7年8月~令和8年3月)は、
– 総演奏登録件数
– 苦情件数の推移
– 通行量・滞留時間のデータ
– 演奏者・来場者の満足度
を定量的に測定し、ルールの適正性や文化振興への効果を検証する。
6. 今後の展望と再発防止策
- ガイドライン違反者には登録取消・演奏禁止措置を適用
- 登録者向けに「公共空間利用研修」を実施しマナー啓発
- 周辺商店街・地域住民との協議会を定期開催し意見交換
- 音響センサーやCCTVによる自動モニタリング技術の導入検討
- 試行結果を踏まえ、条例化も視野に長期的ルール整備
まとめ
公共空間での路上演奏は都市の賑わいと文化的魅力を高める一方、通行妨害や騒音トラブルも深刻化している。本市が先進事例を参考に導入する登録制試行は、演奏文化を守りつつ公共秩序を維持する重要な一歩だ。試行終了後には定量的データと関係者の意見を総合的に分析し、ルールの恒久化・条例化を目指す。路上演奏者と市民が共生できる持続可能な文化環境の構築に向け、地域全体で取り組みを進めたい。


コメント:0 件
まだコメントはありません。