尖閣周辺に中国船 208日連続 機関砲を搭載の4隻
尖閣周辺に中国船 208日連続 機関砲を搭載の4隻
2025/06/14 (土曜日)
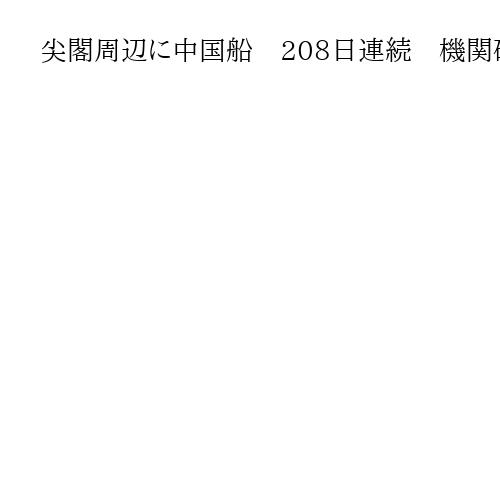
第11管区海上保安本部(那覇)によると、いずれも機関砲を搭載。領海に近づかないよう巡視船が警告した。
はじめに
2025年5月4日、第11管区海上保安本部(那覇)は尖閣諸島周辺の接続水域で中国海警局の船舶4隻が航行しているのを確認し、いずれも甲板に機関砲を搭載していたと発表しました。日本側の巡視船は「領海領土を侵犯しないよう直ちに退去」を厳しく警告し、緊張が一段と高まっています。
1.事件の概要
当該の中国海警船4隻はすべて砲塔型の機関砲(37ミリ級の砲と見られる)を備え、漁船保護や領海警備を名目に周辺海域を航行しました。日本の巡視船は距離を保ちつつ無線やスピーカーで警告し、領海に近づかないよう指示しましたが、にわかに退去しませんでした :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
2.第11管区海上保安本部の役割
第11管区海上保安本部は1972年に那覇市港町の合同庁舎内に設置され、東シナ海と太平洋にまたがる沖縄県周辺海域を管轄します。尖閣諸島はこの管区の専管区域となっており、巡視船・巡視艇は年間を通じて領海侵入防止、海難救助、海洋環境保全など多様な任務を担っています :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
3.領海・接続水域の法的区分
日本の「領海及び接続水域に関する法律」では、基線から12海里(約22km)までを領海、そこからさらに24海里(約44km)までを接続水域と定めています。接続水域では海上保安庁が税関、出入国、衛生に関する法令違反を防止する権限を持ち、警告・退去命令を行えると規定されています :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
4.機関砲搭載の意味
中国海警局の船舶に搭載される機関砲は主に37ミリ口径と推定され、速射性能を活かして小型船やボートを制圧できる威力を持ちます。公務船での武装化は近年強化されており、威嚇射撃やデモンストレーションとして使用することで、周辺国への抑止を図っていると分析されています :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
5.連続確認日数の急増
同じ海域で中国当局の船が確認されるのは今回で167日連続に上り、昨年7月には195日連続で侵入・航行が確認されました。こうした長期にわたる連続航行は、日中間の安全保障環境の緊迫化を象徴する動きといえます :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
6.尖閣諸島を巡る歴史的経緯
尖閣諸島(中国名:釣魚島)は1895年に日本が施政権を確立後、1972年に沖縄返還とともに再編されました。2012年の国有化以降、中国側は海警船や漁政船を用い、領海侵入や魚釣島周辺での巡航を頻繁化させています。以降、毎年数百回規模での警告・退去措置が続いています。
7.日本側の対応強化
海上保安庁は近年、1500トン級PL型巡視船やPLH型ヘリ搭載巡視船を11管区に集中配備し、警備態勢を強化しました。沿岸の航空基地からはヘリコプターによる早期監視、遠隔地からの巡視艇支援も実施し、領海警備能力の底上げを図っています。
8.周辺国・地域への影響
中国側の武装公船による圧力は、台湾やフィリピンなど東シナ海・南シナ海周辺国との緊張にも波及しています。日本は日米安保条約に基づき米軍と共同訓練を強化し、アメリカ海軍・沿岸警備隊との連携によって抑止力を高める動きも進んでいます。
9.国際法と海洋秩序の維持
UNCLOS(国連海洋法条約)に基づく国際法秩序の下では、公海・排他的経済水域(EEZ)も含め、合法的航行の自由が保障されます。しかし、武装公船の一方的な警告・侵入行為は、海洋法における「無害通航権」や「航行の自由」を脅かすものとして、国際社会からの批判を招いています。
10.今後の展望と課題
海上保安庁は監視網の強化や無人機(UAV)導入など最新技術を活用した警備態勢の進化を模索しています。同時に、日中間の外交交渉や多国間協議を通じて法の支配に基づく解決策を追求しなければなりません。東シナ海の安定化は地域の平和と繁栄に直結する重要課題です。
まとめ
第11管区海上保安本部による今回の警告は、領海と接続水域の法的運用と実効支配を巡る緊迫した現状を示しています。武装公船による威嚇航行は海洋法秩序を揺るがす行為であり、日本側は巡視体制の強化と日米など同盟国との連携を通じて、平時から有事に至るまで総合的な対応力を高める必要があります。


コメント:0 件
まだコメントはありません。