一律2万円給付はバラマキ? 解説
一律2万円給付はバラマキ? 解説
2025/06/18 (水曜日)
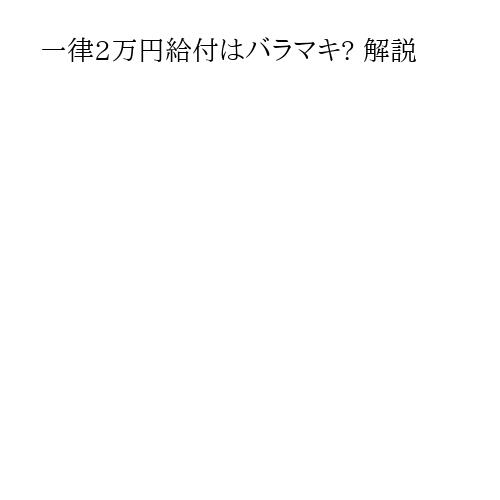
「一律2万円」給付で「予算3兆円台」“国の借金”1442兆円の中で“バラマキ”の是非【Bizスクエア】
はじめに:参院選公約「一律2万円」給付の波紋──3兆円規模の現金給付は「バラマキ」か
2025年6月13日、石破総理は7月に予定される参議院選挙に向け、全国一律で1人あたり2万円を給付する方針を表明しました。給付総額は「3兆円台半ば」とされ、政府が掲げる「財政健全化」に逆行するとの指摘が出ています。国と地方を合わせた政府債務残高は2023年度末で1,442兆円に上り、対GDP比は約237%と主要先進国で最悪水準です。この巨額債務のもとでのばらまき政策に、財政規律の観点から是非が問われています。
「一律2万円」給付の財政規模と財源
給付対象は約1億2,000万人の国民と見込まれ、単純計算で2兆4,000億円、関連事務費を含めれば3兆円を超えます。予算案では、2025年度二次補正予算として3兆3,000億円を充当予定で、国債発行を主財源とする見通しです。日銀による国債買取が続く中、財政規律を重視する骨太方針との齟齬が批判されています:contentReference[oaicite:0]{index=0}。一方で、低所得層への迅速支援策としての側面もあり、給付要件の簡素化と即時給付を評価する声も根強い状況です。
過去の現金給付と財政への影響
同様の一律給付は2020年の新型コロナ対策で「特別定額給付金」1人10万円が実施され、約12兆円規模の補正予算が組まれました。当時も「ばらまき」との批判があったものの、迅速支給による消費喚起とマイナンバー制度普及の契機になりました。緊急支援の有効性を挙げる一方で、事務費総額4,500億円のうち自治体負担分1,200億円が発生し、地方財政を圧迫した事例もあります。この経験から、給付総額だけでなく事務コストや地方負担の軽減策も検討課題です:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
政府債務残高1,442兆円の現状と課題
財務省によると、政府債務残高は国債・借入金・政府短期証券を合わせて1,442兆円に達し、年々増加傾向が続いています。令和臨調は「債務残高25~30%削減」を提言し、GDP比240%台からの脱却を掲げていますが、プライマリーバランス黒字化の見通しは立っていません。高齢化による社会保障費の膨張もあり、給付財源を国債頼みにする構図は中長期的な財政持続性をさらに厳しくします:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
財政健全化論とばらまき論の交錯
政府は「給付は緊急性が高く、景気押し上げ効果が大きい」と主張し、ばらまき批判をかわそうとしています。一方、みずほ銀行の試算では、2万円給付によるGDP押し上げ効果は0.1%程度にとどまり、費用対効果の低さが指摘されています。さらに、金利上昇リスクが高まる中で追加国債発行は財政コストを増加させ、将来世代への負担先送りとの批判を免れません。
海外の一律現金給付事例との比較
欧州各国ではコロナ禍に一律給付を実施したが、給付額は日本より小規模(例:英国300ポンド、ドイツ300ユーロ)でした。欧州連合(EU)の平均支給額は約200~250ユーロで、原資はEU復興基金で賄われ、加盟国間の財政連携で負担を分散しました。財政余力が限られる日本では、同様の多国間補助はなく、全額を国内借入れで賄う構造の違いが浮き彫りになっています。
選挙対策か、実効的景気刺激策か
時期が参院選直前であるため、「選挙目当てのばらまき」との批判は根強いです。与野党の世論調査でも賛否が割れ、「必要」と回答する層は約45%、「不要」は約50%と拮抗しています。低所得層や中小企業支援を訴える与野党内からは、給付対象を絞り込む給付付き税額控除や子育て世帯支援への再配分を求める声も上がっています。
今後の展望と政策提言
- 給付手続きのオンライン化とマイナポータル活用による事務費削減
- 低所得・子育て世帯への重点的支援策とのセット化で効果向上
- 中長期的な税財政改革ロードマップの提示と、複数年予算枠の導入
- 社会保障と成長戦略を両立させるプライマリーバランス改善計画の明示
結論:短期支援と財政持続性の両立を探る
一律2万円給付は、経済的困窮層への緊急支援として一定の意義がある一方、3兆円規模の追加国債発行は、1,442兆円の政府債務残高を抱える財政運営に逆風を吹き込むリスクも孕んでいます。将来世代への負担を最小化しつつ、短期的な景気下支えと中長期的な財政健全化を両立させるため、給付要件の精緻化と税・社会保障改革をセットで進める“ハイブリッド型”政策が求められます。


コメント:0 件
まだコメントはありません。