関税交渉 米が引き下げに柔軟姿勢
関税交渉 米が引き下げに柔軟姿勢
2025/06/06 (金曜日)
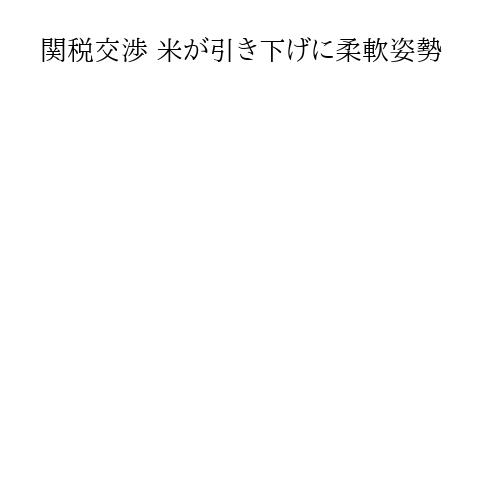
【ワシントン時事】トランプ米政権の関税措置見直しを巡る日米交渉で、米側が日本に課している相互関税の上乗せ分について、引き下げに柔軟な姿勢を示していることが5日、分かった。
要約
2025年6月5日、日本と米国は関税措置見直しをめぐる閣僚級交渉の第5回会合をワシントン郊外で行い、米国側が日本に課している「相互関税」上乗せ分について、引き下げに柔軟な姿勢を示していることが明らかとなりました。しかし、日本側は自動車や鉄鋼・アルミニウムの追加関税を含む一連の措置そのものの撤廃を主張しており、依然として両国間には大きな隔たりがあります。交渉は難航が予想されますが、先進7カ国首脳会議(G7サミット)に合わせた日米首脳会談での合意も視野に入れ、貿易拡大や非関税措置、経済安全保障上の協力など幅広いテーマで歩み寄りを探ることになります。以下では、今回の相互関税問題の背景、歴史的経緯、法的根拠、日米交渉の焦点、そして今後の見通しについて詳しく解説します。
1. 相互関税導入の背景と法的根拠
相互関税の源流は、トランプ米政権が2018年に発動した「セクション232」(安全保障を理由とする追加関税)にあります。トランプ政権は鉄鋼・アルミニウムの輸入について「国家安全保障上の脅威」を理由に、ターゲット国に対して一律25%(鉄鋼)、10%(アルミニウム)の追加関税を課しました。日本を含む同盟国も例外ではなく、「相互関税」という形で日本からの輸入品にも見返りとして関税がかけられることになりました。
さらに、2024年4月には、米国は国際緊急経済権限法(IEEPA)を根拠として「相互関税第2弾」(相互関税上乗せ)を発動しました。この措置は米国が安全保障上の理由で国際的に輸入制限を行うもので、「一律10%の基本税率」に加え、「国・地域ごとに異なる上乗せ分」が設定されました。日本には上乗せ分として14%が課され、合計で24%もの関税率に跳ね上がる見込みでした。しかし、上乗せ部分は2025年1月末から90日間停止されており、7月9日までに交渉次第で変更や撤廃が可能となっています。
2. 日米交渉の経緯とこれまでの動き
日本と米国はセクション232措置発動直後から交渉を継続してきましたが、トランプ政権の強硬姿勢もあって難航を極めました。バイデン政権に代わってもメッセージは大きく変わらず、「同盟国にも厳しい措置を適用する」という方針は維持されました。その結果、1回目の閣僚級交渉(2024年6月)、2回目(同年秋)、3回目(2025年2月)、4回目(同年3月)と段階的に話し合いが重ねられてきました。
当初、日本政府はまず「鉄鋼・アルミニウムのセクション232関税措置の全面撤廃」を強く要求。しかし、米国は「日本の安全保障協力を評価しつつも、経済的利益とのバランスを優先する」という立場で、追加関税を維持しつつ上乗せ分の引き下げに応じる形を模索してきました。特にG7サミット前を意識しており、2025年6月中旬の伊勢志摩サミットを念頭に日米首脳会談で何らかの合意を得たい狙いが透けていました。
交渉では、日本側は鉄鋼・アルミニウムだけでなく、自動車や電子機器、農産品など幅広い品目への関税影響を訴え、単なる関税調整を超えた「非関税協力」「経済安全保障上の共同対処」を提案。具体的には、米国産車の日本向け輸出を促進するための安全基準見直し、投資規制や輸出管理での日米協調、サプライチェーンの強靭化に関する連携強化などを打ち出しました。一方、米国は上乗せ部分を削減する代わりに、10%の基本税率は維持する考えを示しており、日米間での隔たりは大きい状況が続いています。
3. 貨物自動車運送事業法との対比で考える「点呼問題」の重要性
今回のニュースにある「点呼問題」とは直接関連しませんが、同じく運輸分野で「法令遵守が経営存続に直結する」事例として参考になります。貨物運送事業法では、運転手を雇用する事業者に対して、安全運行のための「点呼義務」が厳格に課されており、違反が累積すると事業許可取り消しにもなります。これは国民の安全確保を目的とし、違反点数を基に厳しく処分される仕組みです。日本郵便が違反点数200点超で許可取り消し相当の処分を受けるニュースが示したように、運輸・物流事業者は法令遵守を徹底しなければ事業継続が危うくなるため、日米交渉でも「法令遵守」「透明性」「安全性」を担保する姿勢は重要な共通テーマとなります。
同様に輸送インフラやサプライチェーンの安全性は、貿易交渉においても「信頼確保」の基盤となります。例えば、輸入業者が関税原産地証明を偽造した場合には、通関で問題となり、それが大規模な貿易摩擦に発展することにもつながります。貨物運送事業法の例は、法令違反のリスクがいかに事業に甚大なダメージを与えるかを示しており、日米貿易交渉でも「ルールに則った適正な取引」が求められる理由と重なる部分があります。
4. 相互関税撤廃の要求と米国の思惑
日本政府は、セクション232措置の撤廃を一貫して求めており、追加関税の撤回なくしては「自由で公平な貿易環境」は実現できないとの立場を崩していません。特に自動車業界は、米国向け輸出の柱であり、24%もの関税がかかると日本メーカーの価格競争力が大きく損なわれるため、最も敏感な分野となっています。実際、米国市場における日本車のシェアは高く、関税負担が大きくなればシェア低下や雇用削減などの二次的影響も懸念されます。
一方、米国の狙いは、貿易赤字の削減だけでなく、国内製造業の保護や中国をはじめとする外国製品への牽制にあります。特に安全保障を理由に関税を引き上げるセクション232措置は、半導体やハイテク部品の輸入にも波及する可能性があり、自国の製造業の再興を政策目標の一つとして掲げるバイデン政権は、関税の全廃には慎重な姿勢を示しています。したがって、上乗せ部分の引き下げは譲歩しつつも、基本税率10%は維持して「自国産業を守る」というメッセージを対外的に発信する政治的意図が強いと考えられます。
また、一部専門家は「相互関税の上乗せ分を削減する見返りに、日本が半導体や再生可能エネルギーなど重点産業での協力を強化する可能性がある」と指摘。日米間で相互関税を材料にした「産業政策協調」や「サプライチェーン再構築」の枠組み形成が進むことで、中国を念頭に置いた経済安全保障分野での連携も深まると見られています。
5. 非関税措置と経済安全保障上の協力
関税交渉では関税率そのものが焦点となりますが、同時に非関税措置(NTM: Non-Tariff Measures)や経済安全保障分野での協力も重要な論点です。日本側は、米国産自動車が日本市場に参入しやすくなるよう、安全基準や認証制度の相互承認、型式認定の簡素化などを提案してきました。これにより、関税率が多少維持されたとしても、輸入手続きを円滑化することでコストを抑え、価格競争力を保つ狙いがあります。
さらに、経済安全保障に関しては、半導体やバッテリー、希少金属など戦略物資の供給網を強化するための日米協力も議論されています。特に中国をはじめとする国際情勢が不安定化する中で、重要素材や部品サプライチェーンの多元化・強靭化が求められています。これに関連して、「クリーンエネルギー車(EV)の部品サプライチェーン」「次世代通信(6G)向け半導体」「量子コンピューティング向け材料」などの分野で、日米共同研究や製造拠点の相互展開を進めることで、関税交渉以外のメリットを引き出そうという発想です。
加えて、経済安全保障の名の下に、情報・サイバー分野での協力や外資規制の整合性強化なども日米間で議論されています。具体的には、外国投資による重要インフラへのリスクを共有し、相互に規制緩和しつつも安全保障上のリスクを最小限に抑える枠組み構築が検討されています。関税協議を入口に、広範な経済安全保障の連携が進むことが、今回の交渉のもう一つの大きな特徴です。
6. 交渉の焦点と現時点での立ち位置
現時点での交渉における主な焦点は以下の3点です。
- 相互関税の上乗せ分の引き下げ幅
米国は上乗せ分(日本には14%)を「一部引き下げる」意向を示しているものの、10%の基本税率は残す方針です。日本側は「基本税率そのものの撤廃」を求めており、譲歩を迫られるかどうかが最大の焦点です。10%の関税が残ることで、日本車や鉄鋼・アルミ産業は依然として大きなコスト負担を抱えることになります。 - 自動車分野の非関税措置
日本から米国への自動車輸出の拡大には、型式認定の相互承認や安全基準の整合化が欠かせません。米国はこれまでNAFTA(現USMCA)加盟国以外には厳しい安全基準を適用してきましたが、日本車メーカーは「日本の認証で米国市場に参入できる仕組み」を求めています。これが実現すれば、関税負担は残るものの輸入手続きの時間短縮・コスト削減に寄与します。 - 経済安全保障上の共同宣言や追加協定
日米はサプライチェーン強靭化や半導体分野での協力を進めていますが、具体的には「半導体材料の共同調達」「EV用バッテリーの原材料確保・リサイクル技術協力」「重要インフラに対する外資規制の共通ルール」などが検討されています。交渉の場でこれら協力を束ねた枠組みづくりを進めることで、関税問題だけではない「包括的な経済連携」の道筋が示される可能性があります。
日本側はこうした交渉を「G7サミットでの首脳合意に持ち込みたい」との意向を強く示しています。G7での共同文書に相互関税引き下げや非関税協力、経済安全保障分野での連携が盛り込まれれば、日米間の具体的な作業を大きく後押しすることになります。一方で、米国側にも大統領選を控えた政治的事情が絡むため、「国内産業を守りたい」という強い圧力が働いており、譲歩は容易ではありません。
7. 日本企業・産業界への影響
相互関税が全面適用されれば、自動車、鉄鋼、アルミニウム、電子部品、機械など幅広い分野で大きなコスト増が見込まれます。具体的には以下のような影響が想定されます。
- 自動車メーカー:日本から米国への輸出関税は現行2~3%程度ですが、24%に跳ね上がると部品を含めてコスト競争力が大幅に低下し、米国内生産へのシフトを余儀なくされる可能性があります。
- 鉄鋼・アルミメーカー:すでにセクション232関税で25%(鉄鋼)、10%(アルミ)がかかっており、24%の相互関税が追加されるとトータルで約50%の関税負担となり、輸出そのものが困難になります。国内需給逼迫や雇用への影響が深刻化する恐れがあります。
- 電子部品・半導体:スマートフォンや自動車向け半導体なども関税の対象となる可能性があり、シリコンウェハーや電子部品の輸出コストが急増します。これにより、グローバルサプライチェーンの見直しを余儀なくされる企業が続出する恐れがあります。
- 農産物・食品加工:日本産の果物、酒類、加工食品なども追加関税がかかる可能性があり、米国市場での価格競争力が一気に低下します。輸出農家や加工業者は新たな販路開拓を迫られることになります。
これらの影響を軽減するため、日本政府は「関税削減が実現するまでの間、輸出企業への支援金や補助金を検討する」とともに、「米国産品の輸入拡大」を条件にすることで米国側との交渉を優位に進めようとしています。例えば、日本国内において米国産自動車の関税を段階的に引き下げる代わりに、米国が相互関税を引き下げるという相互依存的な交渉戦略です。しかし、国内自動車産業保護の観点から自動車関税を容易に削るわけにはいかず、産業界の意見は分かれています。
8. 米国国内政治の影響と大統領選の見通し
2024年11月に行われる米国大統領選挙を控えて、バイデン大統領(または共和党の候補者)が就任後も保護主義的な姿勢を維持したい意向が背景にあります。選挙対策として、米国の製造業や労働組合からの支持を維持するため、関税を容易には撤廃できない圧力があります。特に製鋼業や自動車関連産業の多くが中西部や南部に集中しており、地域経済への影響を考慮すると、関税は選挙期間中に緩和される見込みは低いと専門家は予測しています。
したがって、日本側が「G7サミットを利用して早期合意を得たい」としても、米国内の政治的事情が左右し、両国間の歩み寄りは容易ではありません。一方、ハリス副大統領や米通商代表部(USTR)などは「日米同盟の重要性」を訴えつつも、選挙後の情勢次第で交渉の進展速度が大きく変わる可能性が高いと言えます。
9. 今後の交渉シナリオと見通し
現段階で想定される交渉シナリオは主に三つあります。
- 上乗せ分のみ引き下げ、基本税率10%維持
最も現実的な見通しであり、米国が「相互関税の一部緩和」を示したため、日本は上乗せ14%部分のみを削減し、2025年7月9日以降の適用を回避する方向で協議を進める。しかし10%部分は維持されるため、日本産品への関税負担は依然として残る。 - 基本税率の削減を含む包括合意
理想的ではあるものの実現可能性は低く、米国が日米首脳会談を契機に関税全廃を約束し、両国の貿易・安全保障協力を強化する内容の包括合意を結ぶ。ただし米国内での政治的反発が強く、選挙後まで先送りとなる可能性が高い。 - 交渉決裂・相互関税全面適用
日本が上乗せ分削減に折り合いをつけられず交渉が決裂し、7月9日以降に24%の税率が全面適用されるシナリオ。最悪のケースでは日本企業・産業界に深刻な打撃を与え、日米関係にも長期的な緊張を招くことになる。
日本政府は交渉決裂を回避するため、非関税措置や経済安全保障分野での協力を無償提供することで譲歩を引き出そうとしています。特に、日米共同での半導体製造拠点誘致やEVバッテリー供給網構築での協力策を追加するなど、関税以外の分野でのメリットを強調しています。これにより、米国側が国内産業界からの圧力を一定程度和らげつつ、合意材料を提供する戦略です。
10. まとめと今後の課題
日米間の相互関税問題は、トランプ政権時代から続く貿易摩擦の一環であり、米国の保護主義と日本の輸出依存経済がぶつかる構図を象徴しています。今回の交渉では、米国が上乗せ分引き下げに柔軟な姿勢を示したものの、基本税率10%の維持方針に変わりはなく、日米間の隔たりは依然として大きい状況です。日本側は「一連の関税措置撤廃」を主張し続けていますが、米国国内の政治的事情や選挙を控えたタイミングもあって交渉は難航が予想されます。
今後7月9日までに上乗せ分の適用を回避できるかどうかが最大のポイントであり、日本政府はG7サミットでの首脳合意を目指して交渉を続ける方針です。万が一全面適用となれば、日本企業のコスト負担は一気に増大し、雇用や投資に対する悪影響が懸念されます。ただし、非関税措置の見直しや経済安全保障分野での協力を通じて、日米同盟を基盤とする包括的なパートナーシップを構築する機会ともなり得ます。日米双方が「貿易と安全保障の両輪」をいかに両立させるかが、今後の交渉の最重要課題となるでしょう。


コメント:0 件
まだコメントはありません。