「新香港人」が急増 専門家の指摘
「新香港人」が急増 専門家の指摘
2025/07/06 (日曜日)
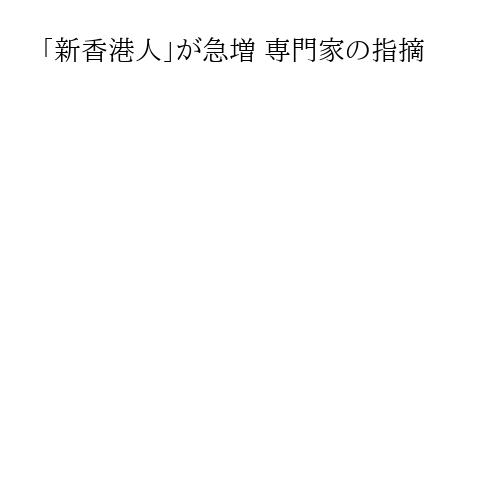
総合ニュース
中島恵ジャーナリスト7/6(日) 10:01(写真:アフロ)7月1日、香港は中国に返還されて28年を迎えたが、祝日であるこの日を香港市民の多くは複雑な心境で迎えた。近年、香港から海外に移民する人が増加する反面、香港政府の政策により、香港には中国大陸からの移民(新香港人)が増えた。
彼らの多くは中国からの人々だ。香港に住むことで得られる「権利」は享受しつつ、香港への理解は薄く、頻繁に中国に帰るなど
香港返還28年――増加する「新香港人」が浮き彫りにする共生の難しさ
7月1日、香港はイギリスから中国に返還されて28年を迎えたが、多くの市民は祝賀ムードと複雑な思いを抱えたままこの節目を迎えた。近年、香港から海外に移民する人が増える一方で、香港政府は中国本土からの移住を促進し、「新香港人」と呼ばれる中国人移住者の数が急増している。
「新香港人」とは何か
「新香港人」とは、主に単程証(ワンウェイパーミット)や各種人材・労働力計画を通じて中国本土から香港に定住した移住者を指す。香港政府の統計処では、1997年の返還以降2046年までの累計で約203万人の単程証保持者が移入し、各種計画による人材輸入を加えると250万人に達すると推計される。この数値は、2046年時点で3~4人に1人が「新香港人」となることを意味する。
歴史的背景:返還と「一国二制度」の約束
香港は1841年から99年間イギリスの植民地となり、1997年7月1日に中国に返還された。返還の枠組みは1984年の中英共同声明(Sino-British Joint Declaration)で合意され、「一国二制度」の下で50年間、香港の資本主義制度と高度な自治を保持することが明記された。
統計が示す急増する移住潮
香港特区政府の人口推算によれば、返還後も天然増(出生-死亡)よりも移入者が人口増加の主因となっており、特に中国本土からの移住が顕著だ。2013年以降、移住者は現地で「新香港人」と呼ばれ、その多くが広東語よりも普通話を母語とし、生活習慣やビジネス行動に香港本土住民とのギャップが生じている。
経済への影響:繁華街シャッター化と「北上消費」
返還28周年の祝賀行事の一方で、ネイザンロードをはじめとする繁華街は多くの店舗が閉店し、「シャッター街」と化している。市民や観光客が物価の安い中国本土へ買い物に出向く「北上消費」が常態化し、香港の小売・飲食業は深刻な打撃を受けている。
文化・社会的摩擦:言語と習慣のギャップ
本土住民は「新香港人」に対し、普通話優先や公共マナーの違いなどを理由に摩擦を感じることが多い。地元メディアで報じられるところでは、住民同士の言語トラブルや、ゴミ出しルール違反、公共施設での振る舞いを巡るクレームが増加している。また、政府トップは言論統制の中で「香港らしさ」の維持を強調し、市民の不安をさらに高めている。
類似事例:移民増加と共生課題の国際比較
- カナダの多文化主義
カナダは1971年に多文化主義を国是とし、1988年に「Canadian Multiculturalism Act」を制定。移民受け入れと文化の多様性を尊重しながら、言語・教育支援や職業訓練を通じて統合を図る制度を整備している。しかし最近は住宅不足や公共サービスへの負荷から、移民数制限の議論が高まっている。 - シンガポールの市民権政策
シンガポールは少数民族国家として、永住権保有者に対し一定の言語テストや教育参加を義務付ける一方、都市計画や居住地区の配慮で民族バランスを維持。社会的包摂のための「民族統合計画」を実施し、移民と先住民の対話機会を制度化している。
今後の展望と提言
- 制度の透明化と支援強化:新移住者向けに広東語・習慣教育プログラムを拡充する。
- 多言語広報と相談窓口設置:行政・医療・教育の各機関で多言語対応を義務付ける。
- 地域住民との交流促進:NPOや企業と連携し、文化イベントやボランティア活動を共同開催する。
- 経済活性化策:中小店舗支援や観光振興による地元市場の再活性化を図る。
- 法改正検討:移住者の権利義務を明文化し、生活ルール違反時の行政処分を整備する。
結論
香港返還28年を迎え、かつての「東洋の真珠」と称された活力は薄れつつある。祝賀ムードの陰で急増する「新香港人」は、香港社会に『権利』を享受する一方、『責任』としての文化理解や地域貢献に対する期待とのギャップを生んでいる。経済面では「北上消費」が地元産業を圧迫し、社会面では言語・習慣の違いから摩擦が顕在化している。
歴史的には中英共同声明と基本法で保障された「一国二制度」が機能してきたが、近年は安全条例や言論規制強化で「香港らしさ」の維持が困難となり、市民の帰属意識は揺らいでいる。人口統計上も2046年には3~4人に1人が「新香港人」となると推計され、地元住民と移住者の比率は大きく変化する見込みだ。
国際的な事例を見ても、多文化主義や統合政策は制度化と運用の両面で課題を抱える。カナダのような法整備と支援プログラム、シンガポールのような多様性配慮の居住政策を参考に、香港は移住潮流を受け入れつつ、地元文化と経済を守る「ハイブリッド共生モデル」を構築する必要がある。
今後は、行政・企業・市民社会が一体となって多層的な対話と制度改革を推進し、「新香港人」と「本土香港人」が互いに理解と尊重を深める場を創出することが急務だ。香港が歩む次の四半世紀は、単なる人口移動の問題を超え、多様性を力に変える「共生都市」への挑戦となる。変化を恐れず、歴史の宿命を背負いながらも前へ進む香港の姿が、改めて世界に示されることを期待したい。


コメント:0 件
まだコメントはありません。