入管の「原則収容主義」「無期限収容」に裁判官の判断は?「入管収容と入管法は国際法違反訴訟」6月17日判決、焦点を解説【“知られざる法廷”からの報告】
入管の「原則収容主義」「無期限収容」に裁判官の判断は?「入管収容と入管法は国際法違反訴訟」6月17日判決、焦点を解説【“知られざる法廷”からの報告】
2025/06/08 (日曜日)

日本の入管収容制度と入管法は恣意的な(思うがままの)拘禁を禁じた国際法に違反している--1300日以上、入管施設に収容された2人の外国人男性が訴えた裁判の判決が6月17日に言い渡される。国際法違反という判断が出れば、入管行政への影響は大きい。判決のポイントを国際人権法の専門家に聞いた。(元TBSテレビ社会部長 神田和則/裁判結審時の記事に追加取材をして再構成)
はじめに
2025年6月17日、東京地方裁判所で「日本の入管収容制度と入管法が、恣意的拘禁を禁じた国際人権法に違反しているか」が問われる判決が言い渡されます。トルコ国籍のクルド人とイラン国籍の原告が、それぞれ約1,300日を超える長期収容を強いられたとして訴訟を起こしました。判決が国際法違反と判断されれば、入管行政に大きな影響を与える可能性があります。
裁判の概要と原告の主張
原告の二人は、難民認定申請が不許可となった後、「帰国可能となるまで」として無期限に収容されました。原告側は市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)第9条が禁止する「恣意的拘禁」に該当すると主張し、収容の違法確認と損害賠償を求めています。
日本の現行入管収容制度の法的根拠
入国管理及び難民認定法(入管法)第34条は、「送還可能となるまで」の収容を認め、収容期間に上限を設けていません。この「原則収容主義」に基づき、法務省は長期収容を続けています。
無期限収容の実態と人権侵害の指摘
長期収容は身体的・精神的ストレスを招き、実際に収容施設内での死亡事例も発生しています。無期限かつ一方的な拘禁は、国際人権法の禁止規定から逸脱するとして、国内外の人権団体や学界から批判が続いています。
2018年の仮放免運用方針の変更
かつては一時的に仮放免を認めていた入管当局が、2020年東京五輪を控えて仮放免運用を厳格化。「送還見込みがない者も原則収容継続」としたことで、救済の道が狭まりました。
国際人権法の基準―自由権規約第9条
自由権規約第9条は「恣意的拘禁」を禁止し、拘禁は法に定める理由と手続きに従うことを要求します。国連の作業部会も日本の長期収容を「恣意的拘禁」と認定し、改善を求めています。
裁判官の役割と国際法の適用責任
裁判官は当事者の意見を裁定するだけでなく、国際法を順守する義務を負います。本判決では、国際人権法をどう評価し適用するかが問われ、司法の国際法認識が明らかになります。
海外制度との比較:カナダの審査制度
カナダなどでは、独立機関が収容の必要性を定期的に再審査し、不当と判断されれば即時釈放します。日本の制度はこれと対照的に「収容が原則」とされており、国際基準から乖離しています。
歴史的経緯:戦後から現在まで
1952年の法務省移管以降、収容所は全国に拡大し、原則収容主義が定着しました。過去の抗議や事件にもかかわらず、制度改革は後手に回ってきました。
裁判に至るまでの経緯
原告は数度の難民申請を経て収容を繰り返し、2020年に国連の勧告を受けながらも仮放免を重ねました。2022年1月に訴訟を提起し、今夏の判決を迎えます。
判決のポイントと今後の影響
論点は、①恣意的拘禁か否か、②入管法第34条が国際法に抵触するか、③損害賠償責任の有無、です。違法と判断されれば、法改正や運用見直しが不可避となります。
今後の課題と改革の方向性
- 定期的審査制度の導入
- 収容期間の上限設定
- 仮放免運用の弾力化
- 情報公開と透明性向上
- 難民申請者の法的支援強化
まとめ
6月17日の判決は、日本の収容制度が国際人権法に適合するかを示す重要な判例になります。恣意的拘禁禁止の原則をどのように国内法制度に組み込むかが、今後の司法・立法・行政の責任であり、改革の指針となるでしょう。
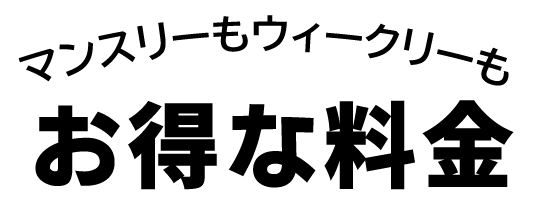

コメント:0 件
まだコメントはありません。