尖閣周辺に中国船 230日連続 海警局の船4隻 いずれも機関砲を搭載
尖閣周辺に中国船 230日連続 海警局の船4隻 いずれも機関砲を搭載
2025/07/06 (日曜日)
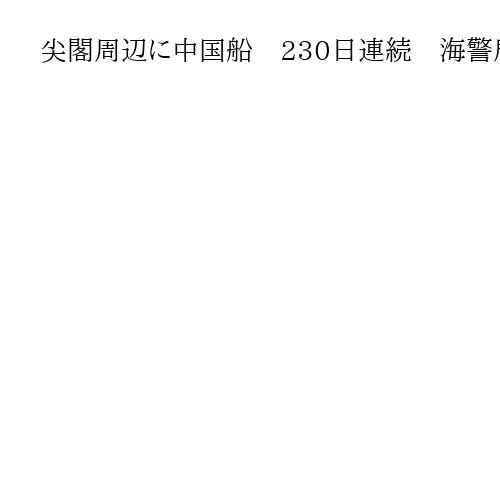
第11管区海上保安本部(那覇)によると、いずれも機関砲を搭載。領海に近づかないよう巡視船が警告した。
尖閣諸島周辺で機関砲搭載船に警告──第11管区海保の対応と海洋安全保障の課題
2025年7月6日、第11管区海上保安本部(那覇)は尖閣諸島周辺の接続水域で中国海警局の公船4隻が航行し、いずれも機関砲を搭載していることを確認しました。巡視船は領海に近づかないよう警告し、我が国の主権と国際法に基づく領海警備の意志を示しました。
国際法と領海警備の枠組み
日本の領海は基線から12カイリ(約22.2キロ)までと定められ、国連海洋法条約(UNCLOS)に準拠しています。領海では沿岸国が主権を行使でき、外国船舶は無害通航権のみが認められます。公船の武装は近接警備での威嚇手段とされ、中国の海警局公船の機関砲搭載はUNCLOS附属書第4の趣旨から問題視されます。
第11管区海上保安本部の役割と装備
第11管区海保は沖縄県を含む東シナ海・太平洋側を担当し、1972年に設立されました。海保は大型巡視船(PLH)、中型巡視船(PL)により領海警備を行い、ヘリ搭載巡視船も保有します。近年は機関砲や高圧放水装置の搭載、資機材の遠隔監視装置導入など装備の近代化を進めています。
中国海警局の公船活動の背景
中国は2013年に海警局を海洋法執行機関として統括し、2018年からは国内法に基づき武器使用を認めています。2020年以降、南シナ海や東シナ海で機関砲や高圧放水銃を使用し、フィリピンやベトナムの漁船にも警告射撃を行っています。尖閣周辺でも挑発行為が常態化しており、日本の領海・接続水域での抑止力維持が課題です。
過去の事例と類似ケース
2016年には海警2302が30mm機関砲を搭載し、尖閣周辺で連続航行。その翌日には領海侵入が確認され、巡視船が高圧放水で応戦しました。また、2023年には同地域で中国海警の大口径放水が複数回行われ、漁船や巡視船に被害が生じています。これらは警告と威嚇の境界を超える行為とされています。
日中間の外交的摩擦と対応
日本政府は領海警備の強化と同時に、中国側に外交ルートで抗議し、法と規則の順守を求めています。外務省は中国大使館へ抗議文を提出し、UNCLOSに基づく対話を訴えています。一方、中国側は「公船の正当な業務」と主張し、日本の主張を否定。軍事的緊張を避けつつ法の支配を尊重させる外交努力が続いています。
海洋安全保障戦略と多国間協力
日本はインド太平洋戦略に基づき、豪州・米国・ASEAN諸国と連携して自由で開かれた海洋秩序の維持を図っています。定期的な共同訓練、情報共有、海賊対処や災害救援活動を通じ、法執行機関間の協力枠組みを強化。海保は豪州沿岸警備隊とも合同訓練を行い、高圧放水対処や射撃管制のノウハウを共有しています。
地域社会への影響と課題
沖縄県・石垣市を含む地域では、中国船接近による漁業被害や観光客の不安が報告されています。海保の警戒強化に伴い、漁業者の生活や海上観光業が影響を受ける一方、基地機能強化に反対する住民の声もあります。安全確保と日常生活維持のバランスが地域共生の課題です。
今後の展望と提言
- 巡視船・レーダー設備の追加強化と装備更新の継続
- UNCLOSに基づく国際法理解促進と法律外交の一層活用
- 地域住民との情報共有や合同訓練による相互理解促進
- 多国間海洋法執行機関ネットワークの拡充と司法協力
- 民間の海難救助・海洋調査への連携強化
まとめ
中国海警局の機関砲搭載公船4隻の尖閣周辺航行は、日本の主権と国際法への挑戦であり、海洋安全保障の重大な課題を浮き彫りにしました。第11管区海上保安本部は巡視船による警告と監視を強化し、即応能力を高めていますが、装備・人員のさらなる充実が求められます。日中間の外交摩擦を回避しつつ法の支配を守るには、多国間協力、地域連携、国際法枠組みの徹底が不可欠です。今後は装備更新と訓練強化、地域対話の深化、法的紛争未然防止策を総動員し、自由で開かれた海域秩序の維持に向けた包括的取り組みを急ぐ必要があります。


コメント:0 件
まだコメントはありません。