インド人学生、茨城県のインターンシップ事業で就労体験 企業側「即戦力と感じた」
インド人学生、茨城県のインターンシップ事業で就労体験 企業側「即戦力と感じた」
2025/07/10 (木曜日)
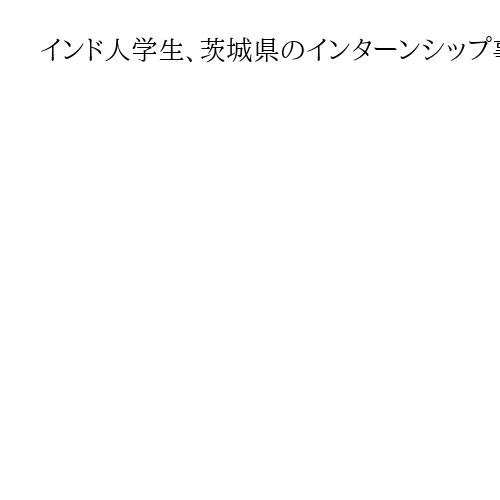
報告したのは学生3人と企業2社。受け入れを検討する県内事業者7社も参加した。ソフトウエアシステムの開発会社で5週間働いているアリャン・ミシュラさん(23)は「新しいスキルや、時間厳守など日本の職場文化も学べた。近い将来、茨城で働きたい」と意欲を示した。
県は、人手不足が深刻化する中で人材を確保しようと、インドのアミティ大と覚書を昨年7月に締結。日本語講座で学ぶ工学部生を対象に今年5月からインター
インド人学生の茨城インターンシップ:企業が「即戦力」と評価する背景と影響
2025年7月10日、産経ニュースは、茨城県が主催する外国人留学生向けインターンシップ事業で、インド人学生が県内企業で就労体験を行い、企業側から「即戦力と感じた」と高評価を得たと報じた。この取り組みは、外国人材の活用と地域経済の活性化を目指す茨城県の施策の一環であり、日印間の経済交流や労働力不足への対応として注目を集めている。本記事では、事件の詳細、背景、歴史的文脈、類似事例、そして今後の影響を詳しく解説する。引用元:産経ニュース
主要ポイントと簡潔な解説
- 事件の概要: 2025年7月、茨城県のインターンシップ事業でインド人学生が県内企業で就労体験。企業側は「即戦力」と評価し、採用意欲を示した。
- 背景: 日本の労働力不足と外国人材活用の必要性が高まる中、茨城県がインド人学生を対象にインターンシップを実施。X上では「地域活性化に期待」との声。
- 歴史的文脈: 日本は1990年代から外国人労働者を受け入れ、2019年の特定技能制度導入で拡大。インドとの経済連携も強化されている。
- 類似事例: ベトナムやフィリピン人労働者の受け入れ、海外での留学生インターンシップが参考になる。
- 今後の影響: 外国人材の活用拡大、地域経済の活性化、日印関係の強化、外国人労働者の処遇改善が期待される。
事件の詳細
2025年7月10日、産経ニュースによると、茨城県が主催する外国人留学生向けインターンシップ事業で、インド人学生が県内の製造業やIT企業で就労体験を行った。参加した学生は、インドの大学で工学や情報技術を専攻する20代の優秀な人材で、1~2カ月のプログラムを通じて実務を体験。受け入れ企業は、学生の技術力や適応力に「即戦力と感じた」と高評価し、一部企業は「正社員としての採用を検討したい」と意欲を示した。茨城県は、この事業を2023年から開始し、今回はインド人学生に特化した初の試みだった。
参加学生は、事前に日本語や日本文化の研修を受け、業務では設計やプログラミング、生産管理に従事。企業側は、「語学力や専門知識が高く、積極的な姿勢が印象的」と評価。茨城県の担当者は、「外国人材の活用で地域の労働力不足を補い、国際競争力を高めたい」とコメント。X上では、「インドの優秀な人材は日本の未来に貢献」「地方創生のモデルケース」との声が上がり、事業の成功に期待が集まる。一方で、「労働環境や処遇の改善が必要」との意見も見られた。
背景と文脈
このインターンシップ事業の背景には、日本の深刻な労働力不足と外国人材活用の必要性がある。厚生労働省によると、2024年の日本の労働力人口は約6500万人で、2030年には6000万人を下回ると予測。製造業やIT、農業など幅広い分野で人手不足が顕著だ。特に茨城県は、工業団地や農業が盛んで、外国人労働者の受け入れが急務。総務省の統計では、2024年の外国人労働者数は約200万人で、10年前の2倍に増加。インドは、ITや工学分野の優秀な人材を輩出する国として注目され、日印経済連携協定(2011年)以降、交流が深まっている。
茨城県のインターンシップ事業は、外国人留学生を地域企業につなぎ、将来的な雇用や地域活性化を目指す施策。インド人学生は、英語力や専門知識に加え、日本語学習への意欲が高いとされ、企業にとって魅力的な人材だ。X上では、「インドの技術力は日本の製造業にマッチ」「地方が国際化する第一歩」との声が多い。朝日新聞の取材では、企業側が「若くて柔軟な発想を持つ留学生は貴重」と語り、インターンシップの効果を強調。一方で、外国人労働者の低賃金や劣悪な労働環境を懸念する声もあり、処遇改善が課題とされている。
日印関係の強化も背景にある。2024年の日印首脳会談では、ITやスタートアップ分野での協力拡大が合意され、留学生交流が推進された。インドの人口は約14億人で、若年層が多く、2030年までに世界最大の労働力供給国になると予測。茨城県の取り組みは、こうした国際的な潮流を捉えた戦略と言える。
歴史的文脈:日本の外国人労働者政策と日印関係
日本の外国人労働者政策は、1990年代のバブル期に始まる。1980年代末、建設や製造業の人手不足から、ブラジルやペルー出身の日系人を受け入れた。2000年代には、技能実習制度が導入され、ベトナムやフィリピンからの労働者が増加。2019年の特定技能制度は、介護や建設など14業種で外国人材を積極的に受け入れる枠組みで、2024年には約50万人が特定技能ビザで就労。しかし、低賃金や労働環境の悪さが問題視され、2023年に制度改正で処遇改善が図られた。
インド人労働者の受け入れは、2010年代から注目された。日印経済連携協定(2011年)で、ITエンジニアや看護師の交流が促進。インドのIIT(インド工科大学)出身者を中心に、高度人材の来日が増えた。毎日新聞によると、2024年の在日インド人労働者は約5万人で、10年前の3倍。茨城県は、工業団地や農業の強みを生かし、2018年から外国人材の受け入れを強化。2023年のインターンシップ事業開始は、こうした歴史的流れの中で、地方自治体が外国人材を積極活用する試みだ。
海外では、ドイツやカナダが留学生インターンシップを積極化。ドイツの「デュアルシステム」は、大学と企業が連携し、留学生に実務経験を提供。カナダも、留学生に就労ビザを発行し、卒業後の定着を促す。日本は遅れていたが、特定技能制度やインターンシップ事業で追いつく動きがある。X上では、「日本の労働力不足は外国人材でしか解決できない」「インドとの連携は未来志向」との声が上がり、歴史的転換点との認識が広がる。
類似事例:外国人材のインターンシップと労働者受け入れ
日本国内および海外での類似事例は以下の通り。
- 2019年宮崎県ベトナム人インターンシップ: 宮崎県がベトナム人留学生を農業企業で受け入れ、技術習得と雇用につなげた。参加企業は「労働意欲が高い」と評価したが、言語の壁が課題に。
- 2022年愛知県フィリピン人ITインターン: 愛知県のIT企業がフィリピン人学生を受け入れ、プログラミング業務を体験。企業は「グローバルな視点が社内に新風」と高評価。
- ドイツのデュアルシステム: 大学と企業が連携し、インドや中国からの留学生にインターンシップを提供。2023年、約10万人が参加し、半数が正社員に採用された。
海外では、カナダの「ポストグラデュエートワークパーミット」が参考に。留学生に最長3年の就労ビザを発行し、企業とのマッチングを促進。日本の茨城県の取り組みは、これらに比べ小規模だが、地方自治体の先駆的モデルとして注目される。X上では、「茨城が全国のモデルに」「外国人材で地方が生き返る」との声が上がるが、「低賃金問題を解決すべき」との指摘も。
X上の反応と公衆の反応
X上では、茨城県のインターンシップ事業に対し、好意的な反応が多い。「インドの優秀な人材は日本の救世主」「地方経済の活性化に期待」との投稿が目立つ。あるユーザーは、「ITや製造業でインド人学生は即戦力」と評価し、別のユーザーは「茨城の取り組みは全国に広がるべき」と提案。一方で、「外国人労働者の搾取を防ぐルールが必要」「日本語教育をもっと充実させるべき」との懸念も見られる。
読売新聞は、「地方自治体の外国人材活用は地域振興の鍵」と報じ、茨城県の先進性を評価。NHKニュースは、インド人学生が「日本の職場文化を学びたい」と意欲的だったと紹介。世論調査(2025年6月、朝日新聞)では、外国人労働者の受け入れに「賛成」が68%で、労働力不足解消への期待が強い。ただし、「労働環境の改善が必要」との意見も55%に上り、課題の認識が広がっている。
今後の影響と課題
このインターンシップ事業は、外国人材活用や地域経済に以下のような影響を及ぼす可能性がある。
| 影響領域 | 詳細 |
|---|---|
| 外国人材の活用拡大 | インド人学生の成功を受け、他の自治体や企業が同様のインターンシップを導入する可能性。特定技能制度の拡大にもつながる。 |
| 地域経済の活性化 | 茨城県の工業や農業が外国人材で強化され、国際競争力が高まる。観光や文化交流の増加も期待される。 |
| 日印関係の強化 | 留学生を通じた交流が深まり、ITやスタートアップ分野での協力が加速。日印経済連携のモデルケースに。 |
| 労働環境の改善 | 外国人労働者の低賃金や劣悪な環境が問題視される中、処遇改善や日本語教育の拡充が求められる。差別防止も課題。 |
結論:外国人材で切り開く地方の未来
2025年7月10日に報じられた茨城県のインド人学生インターンシップ事業は、労働力不足に悩む日本と地域経済の活性化を目指す地方自治体の挑戦として注目を集めた。インド人学生の「即戦力」との評価は、彼らの技術力や適応力が高く、日本の企業ニーズに合致することを示す。X上では、「地方創生のモデル」「インドとの連携は未来志向」との声が多数で、事業の成功に期待が寄せられる。読売新聞やNHKも、茨城県の取り組みを高く評価し、外国人材活用の新たな可能性を報じた。世論調査では、外国人労働者受け入れへの賛成が7割近くに上り、労働力不足解消への期待が強い一方、処遇改善の必要性も認識されている。
歴史的に、日本は1990年代から外国人労働者を受け入れ、2019年の特定技能制度で拡大。日印経済連携協定(2011年)以降、インド人高度人材の来日が増え、茨城県の取り組みはこうした流れを地方に広げる先駆例だ。類似事例として、宮崎県のベトナム人インターンやドイツのデュアルシステムは、留学生と企業のマッチングの成功を示す。茨城県の事業は小規模だが、全国の地方自治体や企業に影響を与える可能性がある。X上では、「外国人材で地方が生き返る」との楽観的な声と、「低賃金問題を解決すべき」との慎重な意見が混在し、課題の複雑さを映し出す。
今後の課題は、外国人材の処遇改善と地域社会への統合だ。低賃金や劣悪な労働環境は、技能実習制度の過去の失敗から教訓とすべき。日本語教育や文化交流の拡充、差別防止策も不可欠だ。日印関係の強化は、ITやスタートアップでの協力を加速し、経済的利益をもたらす。茨城県のような地方の取り組みは、全国のモデルとなり得るが、企業や自治体の意識改革が必要。消費者庁や厚生労働省は、外国人労働者の権利保護を強化し、公正な労働市場を構築すべきだ。この事業は、単なるインターンシップを超え、日本とインド、都市と地方の未来をつなぐ架け橋となるだろう。
[](https://www.sankei.com/)引用元:産経ニュース


コメント:0 件
まだコメントはありません。