尊敬する「空海」の一生を交響曲に 中国人経営者が私財で制作 大阪、香川で公演へ
尊敬する「空海」の一生を交響曲に 中国人経営者が私財で制作 大阪、香川で公演へ
2025/07/02 (水曜日)
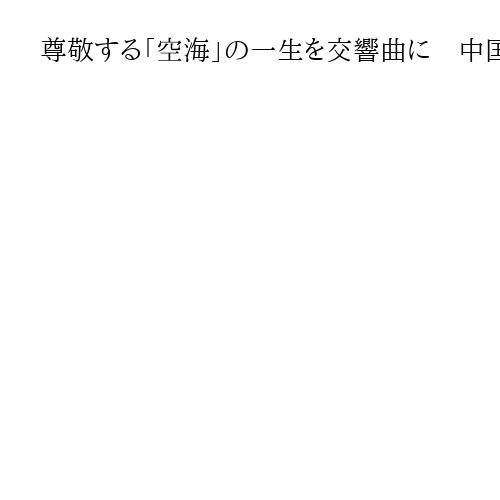
北京で工業用ソフトウエア会社を経営する岳さんは多忙な中、心身を整えるため仏教に関心を持った。空海が中国に渡り、約3カ月で師匠から密教を託されたエピソードなどに感銘を受けてほれ込んだ。
2019年から空海の著作集の出版やドキュメンタリー映像の制作に没頭した。「日本に良い感情はなかったが、空海の関係地の撮影を通じて日本人と交流が広がり、日本が好きになっていった」と語った。
ドキュメンタリーのBGM
中国企業経営者・岳氏が仏教文化に魅せられた背景
北京で工業用ソフトウエア会社を経営する岳さんは、多忙な日々の中でストレスと疲労を感じ、自らを見つめ直す手段を模索していた。そんな折、唐から日本へ渡った弘法大師・空海(805~806年頃)の「密教伝受」のエピソードに強く心を動かされ、仏教に関心を抱くようになった。空海が中国・長安で師匠・恵果阿闍梨から真言密教を授かり、わずか三カ月で高弟と謳われた事実は、岳さんにとって「修行と学びの速さ」「師弟関係の尊さ」を象徴するものとなった。
空海研究とドキュメンタリー制作への没入
2019年以降、岳さんは空海に関する日本語・漢文の著作集を自費出版し、翻訳や解説を手掛けるとともに、ドキュメンタリー映像の制作にも取り組んだ。取材では高野山や善通寺、東大寺など空海ゆかりの地を訪れ、現地の僧侶や研究者、檀家らから聞き取りを行った。映像に用いるBGMは、インド起源の真言密教の読経音や、日本の雅楽、四川の梵呪音などを組み合わせ、空海が感じたであろう異文化融合の響きを表現している。
文化交流を通じた日本への理解と好意の深化
当初、岳さんは「日本は近年の対中メディア報道で批判的なイメージが強い」と語っていたが、ドキュメンタリーのロケを通じて出会った日本の住民、僧侶、観光ガイド、大学教授らと心を通わせるうちに、日本文化への理解と好意が深まった。特に高野山の朝勤行での「一木一石に宿る仏性」の教えや、善通寺での修行僧との雑談を通じて、「日本人の慎ましやかな礼節」「伝統と革新の両立」に感銘を受け、自社の企業文化にも取り入れたいと考えるようになった。
歴史的背景:空海と密教の中国伝来と日本への展開
密教は7世紀末から8世紀にかけてインドから中央アジアを経て中国に伝来し、唐代に最盛期を迎えた。長安の青龍寺や大雁塔は密教の集大成の場とされ、恵果から両足密印や金剛薩埵の真言を伝承された空海は、日本へ帰国後、816年に東寺(教王護国寺)を賜わり、真言宗を開いた。以来、平安時代において密教は公家や武家の厚い信仰を受け、国家鎮護の仏教として発展した。
同様の事例:外国人の日本仏教探求と文化理解
類似の例としては、イギリス人僧侶のマーティン・ストーン氏がある。1970年代に日本禅宗に傾倒し、僧侶として得度後は京都・大徳寺にて修行し、日本人僧侶と共同で英訳の禅書を出版した。また、韓国人仏教学者の李明蘭教授は、奈良仏教研究を通じて日本の仏教美術や建築技術を研究し、日韓学術交流の橋渡しを行っている。これらの事例は、宗教を媒介とした文化交流が両国間の相互理解に寄与する好例と言える。
企業経営への波及効果と今後の展望
岳さんは、仏教文化に触れたことで企業ビジョンを「人間中心主義」へと転換し、社員研修に禅のワークショップを導入。心身の健康管理と集中力向上を図り、社員の離職率低減や生産性向上に成果を上げている。今後は中国国内外の顧客向けにも「禅体験ツアー」を企画し、ビジネス×文化交流の新たなモデルを提案する予定だ。
まとめ
岳さんのように、ビジネスの最前線に立つ実業家が仏教に傾倒し、企業文化や人生観を刷新するケースは近年増加している。空海の中国での修行と師弟関係に感銘を受けた岳さんは、自らの企業経営とドキュメンタリー制作を通じて日中の文化交流を体現した。こうした取り組みは、単なる宗教的関心に留まらず、組織の活性化や異文化理解の促進、地域経済の発展にも寄与し得る。今後は、宗教・文化の枠を超えた企業と社会の協働がより一層重要になるだろう。岳さんの事例は、その先駆けとして多くの企業家や文化人に示唆を与えるものと言える。


コメント:0 件
まだコメントはありません。