土用のウナギ食べられない? EUが国際取引規制を提案へ 日本の流通にも影響の恐れ
土用のウナギ食べられない? EUが国際取引規制を提案へ 日本の流通にも影響の恐れ
2025/06/26 (木曜日)
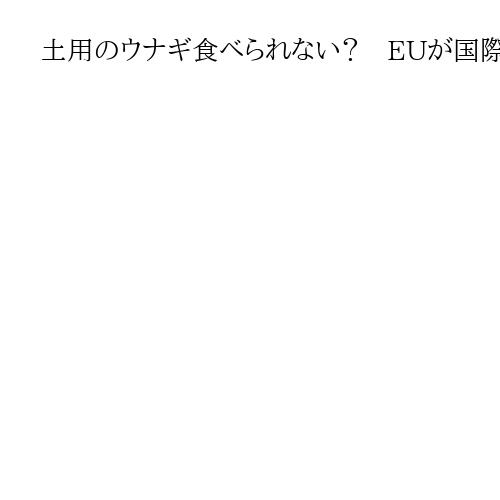
6月27日が提案の期限。承認には締約国会議で投票国の3分の2以上の賛成が必要だが、現時点での情勢は不明だ。日本は「国際取引による絶滅の恐れはない」との立場で、ニホンウナギの主要漁獲国である中国や韓国などと協力して、提案否決に向けて条約加盟国に働きかける。
ワシントン条約では、「付属書1」は商業目的の国際取引は禁止、「付属書2」は取引は可能だが輸出国の許可書が必要になる。EUはニホンウナギやアメリ
EUが提案するウナギ科19種の付属書Ⅱ掲載案──国際取引規制の狙いと日本の対応
欧州連合(EU)は、6月27日を期限としてワシントン条約(CITES)付属書Ⅱへのウナギ科19種掲載を提案している。対象には、国内で「ニホンウナギ」と呼ばれるAnguilla japonicaをはじめ、アメリカウナギ、ヨーロッパウナギなどが含まれ、すべて輸出国政府発行の許可書なしに国際取引が禁じられる見込みだ。提案を承認するには11~12月にウズベキスタンで開かれる条約締約国会議で、投票国の3分の2以上の賛成が必要となるが、現状は採否の行方が不透明である。出典:Yahoo!ニュース 2025年6月26日
ワシントン条約付属書の仕組み
ワシントン条約は絶滅のおそれがある野生動植物の国際取引を規制するもので、付属書は3種類に分かれる。
- 付属書Ⅰ:商業目的のいかなる国際取引も原則禁止
- 付属書Ⅱ:商業目的取引は可能だが、輸出国の「Non-Detriment Finding(取引継続の無害性証明)」許可が必要
- 付属書Ⅲ:締約国から要請のある種について、加盟国が協力義務を負う
ウナギ科19種を付属書Ⅱに掲げることで、稚魚(シラスウナギ)の出荷や加工品・成魚の輸出入すべてに対して許可書が求められる仕組みとなる。
深刻化するウナギ資源の現状
ニホンウナギは1980年代の年間漁獲量約1万7000トンから、2020年代にはわずか1000トン台まで激減した。天然資源の減少要因としては、河川改修やダム建設による回遊経路の遮断、乱獲によるシラスウナギ(稚魚)漁の過度な依存、さらには地球規模の海水温変動が挙げられる。IUCN(国際自然保護連合)は、ニホンウナギを「Critically Endangered(絶滅寸前)」に指定している。
EU提案の背景と狙い
EU側は、「三大大陸型ウナギすべての絶滅危機に対処するためには、共通の国際取引管理が不可欠」との立場を示す。付属書Ⅱ掲載により、シラスウナギの違法取引抑止、漁獲量の適正管理、さらには加盟国内における養殖事業者のトレーサビリティ強化を図り、長期的な資源回復を目指す狙いがある。
日本政府と漁業界の反応
日本政府は「国際取引単独で絶滅に至るとは考えない」との立場をとり、提案の否決に向けて中国、韓国など主要漁獲国と連携し、条約加盟国へ働きかける方針を示している。農林水産省は国内で進む稚魚漁獲規制や放流事業、陸上養殖技術の研究開発を根拠に、「資源管理は日本を含む沿岸各国が責任をもって行っている」と強調している。また、漁業者側からは「許可手続きの煩雑化によって流通が停滞し、養殖業者や加工業者に深刻な影響が出る」と懸念の声が上がっている。
国内の養殖・回復施策
日本では稚魚捕獲量を漁獲枠で制限するとともに、全国の河川において放流強化を実施。とくに鹿児島県大崎町では、循環型陸上養殖システムによって稚魚から成魚まで生育し、人工的な種苗生産に成功しており、国内資源の自給率向上を図っている。
過去のCITES魚類規制事例
CITESに基づく魚類の国際取引規制は例が少ないが、アロワナや「ナイルパーチ」などの掲載事例がある。これらでは、規制後に書類手続きが厳格化されて密漁や密輸の抑止に一定の成果をあげた反面、漁業コミュニティへの影響や貿易業務の混乱が問題化した。ウナギの場合も同様の課題が予測される。
今後の見通しと影響
6月27日の締切後、書類審査を経てEU提案は条約事務局へ提出される。条約締約国会議では3分の2以上の賛成が必要であり、採決は11~12月に行われる予定だ。承認されれば、加盟国は迅速に許可書制度を整備しなければならず、各国の行政コストや業界の対応負担は大きい。一方、採択が見送られた場合でも、国際社会からの資源保護圧力は強まることが予想され、国内外での管理強化策が不可避となる。
まとめ
EU提案によるウナギ科19種の付属書Ⅱ掲載は、絶滅危惧種の保護と漁業者の生業維持という二律背反的課題を浮き彫りにする。日本政府と漁業界は主に「国際取引単独の要因ではない」との公論を展開しつつ、中国や韓国と協調して否決を目指す。しかし、提案の審議過程で明らかになる各国の賛否や議論の中身、最終決定後の運用体制整備が、ウナギ資源の将来を大きく左右することは間違いない。


コメント:0 件
まだコメントはありません。