原口氏古古古米発言 残念と小泉氏
原口氏古古古米発言 残念と小泉氏
2025/06/10 (火曜日)
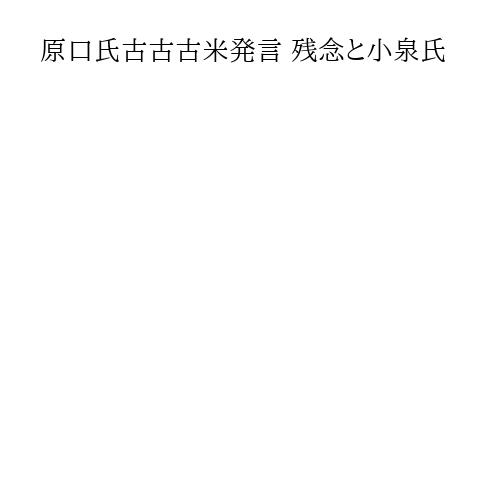
原口議員の備蓄米巡る「人間様食べてない」発言 小泉農相「大変遺憾」
記事概要
2025年6月7日、立憲民主党の原口一博衆院議員が参院選に向けた自民党の公約批判の中で、政府が放出を検討している備蓄米を「人間様は食べてないんですよ。ニワトリさんが一番食べている」と発言し物議を醸しました。これに対し小泉進次郎農林水産大臣は「大変遺憾だ」とコメント。議員発言の是非と備蓄米政策の根本的課題が改めて議論の焦点となっています。
備蓄米制度の仕組みと目的
政府による米の備蓄制度は、主に凶作や災害時の食糧緊急供給を目的として1995年の「需給安定法」施行時に本格化しました。棚上げ備蓄として全国約300カ所の倉庫に最大約100万トンを確保し、毎年約20万トンを市場調整用に放出できる仕組みです。平時の米価安定と、有事の食料安全保障を両輪で担う重要な政策となっています。
古古古米とは何か
備蓄米のうち「古古古米」と呼ばれるものは収穫後3年以上が経過したものを指します。生鮮米と比べて香りや食感が劣るため飼料用とされてきましたが、コロナ禍以降の国内消費減や余剰備蓄の増大を受けて、随意契約による民間販売での流通拡大が検討されています。これにより在庫コスト削減と市場価格への影響緩和を図る狙いがあります。
原口議員の発言と政治的波紋
原口議員は参院選公約で消費税減税を訴える立憲民主や維新の政策を批判する文脈で、「あれは人間用ではない」「人間様は食べていない」と表現しました。与党からは「国民を愚弄する発言だ」「備蓄米の価値を軽視している」との批判が相次ぎ、SNS上でも賛否が飛び交いました。
小泉農相の「遺憾」コメント
小泉大臣は記者会見で「備蓄米は緊急時に国民を支える重要な資源であり、農家の苦労を踏まえた言葉選びをしてほしい」と指摘。発言を「遺憾」としつつ、備蓄米放出は農家支援と価格安定の両立を目指す政策であることを強調しました。
食料安全保障と市場安定策
備蓄米放出策は物価高対策の側面も持ち、米価が高騰したタイミングで市場に放出することで価格抑制を図ります。ただ、放出量や販売価格、タイミングが市場に与える影響は複雑で、農家の所得を守りつつ消費者負担を軽減する「せめぎあい」の中で政策設計が行われています。
農家の視点と受給バランス
稲作農家からは「市場に流れるのが古古古米ばかりではブランド米の価値が下がる」「適正価格での流通ルート構築を」という声が上がります。また、米価下落を懸念し放出量の規模や頻度の見直しを求める農協もあります。需給バランスをどう調整するかが持続可能なコメ政策の鍵です。
制度的課題と改革の方向性
備蓄制度には下記の課題が指摘されています。
- 古古古米の品質劣化と食味の低下
- 放出後の市場価格への過度な影響
- 農家の所得安定策との整合性
- 消費者理解の不足と情報発信の課題
これらを踏まえ、政府は備蓄の質を見直し、食味向上技術の活用、放出タイミングの高度化、民間流通ルートの整備、消費者への情報発信強化などを検討しています。
海外の備蓄政策比較
アメリカは戦略的穀物備蓄(SGR)制度でトウモロコシや小麦を備蓄し、価格高騰時に放出。EUも共通農業政策(CAP)の枠組みで備蓄調整を行いますが、ふるい分け放出や品質維持の工夫など、日本以上に市場メカニズムに応じた柔軟運用が特徴です。
まとめ
原口議員の発言は物議を醸しましたが、備蓄米政策の本質的課題—緊急時の食料安全保障と平時の市場安定策の両立—を浮き彫りにしました。今後は農家支援と消費者保護を両立させるための制度改革が急務です。関係者間で十分な議論を重ね、持続可能なコメ政策の構築に向けた具体策を示すことが期待されます。


コメント:0 件
まだコメントはありません。